相続の知識
62年の実績を持つ相続専門税理士事務所が
相続に関する知識を辞書としてお使いいただけるよう
取りまとめました。ご活用ください。
62年の実績を持つ相続専門税理士事務所が
相続に関する知識を辞書としてお使いいただけるよう
取りまとめました。ご活用ください。
相続に関する様々な手続きや注意点、スケジュールなど相続について知るには、こちらから。
生前対策のメリットや、相続税申告完了後でもできることも取り上げています。
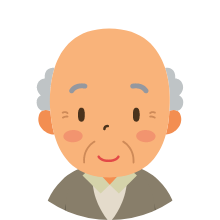
被相続人の立場として、どうすれば家族に良い相続ができるのかと心配な方が多くおられます。生前対策など役立つ知識をまとめています。

どんな場合でも相続人となります。手続きをしなければならないことも多いです。注意点などをまとめました。

親からの相続される資産をどのように継ぐことが効果的か、手続きの手順などの必須なことついても取り上げています。

特に兄弟姉妹が多い場合は相続をどうするかよく協議する必要があります。

日本の相続を考えると、2次相続を考慮してプランを立てると結果としてうまくいくことがあります。

養子縁組が節税対策として行われることがあります。
生活の多くがオンライン化する現代、スマートフォンやパソコンに蓄積された個人情報や契約データなどの「見えない資産」を生前に整理する「デジタル終活」に注目が集まっています。 本記事では、デジタル終活の概要や対象となるデジタル遺品について解説します。整理の流れや注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参...
会社売却とは、自社の経営権や事業を第三者に譲渡することを指します。後継者不在や事業の選択と集中、創業者利益の獲得などを目的に、小企業経営者が選択する経営戦略のひとつです。本記事では、会社売却の基本的な仕組みから、M&Aとの違い、売却方法、メリット・デメリット、売却時の注意点までわかりやすく解説します...
都市化や人口減少により、かつて農地だった土地を住宅や駐車場、事業用地などとして活用したいと考える人が増えています。しかし、農地は農業のために保全された土地であるため、用途を変えるには「農地転用」の許可が必要です。 この記事では、農地転用の基本的な仕組みや、農地法第4条・第5条の違い、場所別の許可基...
医院継承とは、既存のクリニックや医院を引き継いで開業する方法であり、ゼロから新規開業するのとは異なる特徴があります。本記事では、医院継承の概要や継承と承継の違い、メリット・デメリット、具体的な進め方や注意点について解説します。 医院継承とは? 医院継承とは、経営している医院やクリニックの経営権を...
生前贈与は、相続税を減らす方法として知られています。しかし「贈与はいくらまでが非課税なのか?」「生前贈与は相続税の対象になる?」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、相続税対策として生前贈与を実行するための流れをステップごとに解説します。 【基礎知識】相続税対策について正しく理解し...
所有する土地を有効に活用しようと考えたとき、多くの人が最初に直面するのが「誰に相談すべきか」という疑問です。相続対策や節税、将来の安定収入の確保など、土地活用の目的は人によって異なるため、それに応じた相談先を見極めることが求められます。 本記事では、税務や資金計画といったお金に関する側面から、賃...
遊休地は、固定資産税の負担や雑草の処理、不法投棄などの管理面で多くの所有者を悩ませており、「何か有効な活用方法はないか」と考える方も少なくありません。そこで本記事では、遊休地の基本的な定義から、活用によって得られるメリット、代表的な活用方法、検討する際に押さえておくべき注意点までをわかりやすく解...
企業の資金繰りや事業承継を検討する際に注目される手法が「DES(デット・エクイティ・スワップ)」です。債務の削減と資本増強を同時に実現できる仕組みであり、日本語では「債務の株式化」と呼ばれます。本記事では、DESの仕組みやDDSとの違い、種類、メリット・デメリットなど、さまざまなトピックをわかりやすく解説...
サクセッションプランとは、企業の将来を担う後継者を計画的に選定・育成する経営戦略です。後継者不在が注目される昨今、多くの企業が導入を検討しています。本記事では、サクセッションプランの基礎知識や取り組むメリット・デメリット、さらに具体的な進め方まで解説します。 サクセッションプランとは? ...
株式保有特定会社とは、一定の条件を満たすと株式の評価が厳しくなる会社を指します。企業オーナーにとっては、株価評価の方法や課税額に直結するため、正しく理解することが重要です。本記事では、株式保有特定会社の定義や特徴、株価の評価方法、メリット・デメリットを整理したうえで、「株特外し」を詳しく解説しま...
誰かが亡くなると相続が発生します。亡くなった方(被相続人)の親族が相続人となり、遺産相続をするわけですが、そもそも親族の定義とはどんなものなのか、いったいどこまでの親族が相続人となるのか、疑問に思う方も多いでしょう。 ここで覚えておきたいのが「親等」の考え方です。この記事では「親等」の基礎知識や誰...
相続が発生した際、必ずしもスムーズに相続できるケースばかりではありません。管理の難しい不動産や多額の負債がある場合などは、相続人全員が「相続放棄したい」となるケースもあります。本記事では相続人全員が相続放棄をした場合にどうなるのかをテーマに、財産の行方や管理義務などについて解説します。 「相続放棄...
相続登記が義務付けられるものの、その詳しい内容についてなかなか理解できず、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。この記事では、相続登記の義務化に至った経緯から、法改正後の変更点、手続きを行わない際に起こり得るリスクを解説するとともに、手続きの流れやかかる費用について解説します。 まず相続...
成年後見人等が法定後見や任意後見契約の登記をしていると、その登記事項の証明書を法務局に請求できます。この証明書を「成年後見登記事項証明書」といいます。登記事項証明書は各法務局の窓口で請求するほか、郵送やオンラインでの請求も可能です。また、請求を代理人に委任することもできます。取得する際は必要書類...
高齢化が進む現代、認知症などの発症リスクもあり、相続の問題はもとより、老後の財産の管理の問題も深刻となってきました。 財産管理に関わる制度はいろいろありますが、費用の面でもハードルが低いのが「家族信託」です。比較的新しい制度ですが、注目の制度なので耳にしたことがあるのではないでしょうか。ただし、...
「遺贈」とは、故人の残した遺言に則って、その遺産の一部、あるいはすべてをゆずることを指します。相続との違いは、遺言を残す必要があるということ、そしてゆずる相手は法で定められた相続人でなくてもよいうえに、特定の個人でなくてもよいということです。また、受けとる遺産にかかる税金も大きく異なってきます。 ...
相続税の計算には財産をすべて金額に直す必要があります。そのときに大きな障害となるのが土地の評価です。土地の評価額の計算には大きく二つの方法がありますが、基本は相続税路線価を使うやり方です。路線価は土地の面する道路(路線)ごとに決まっていて、国税庁のホームページで公開しているので、住所からすぐ調べ...
親から子へ、祖父母から孫へと生前に財産を少しずつでも渡すことは珍しくありません。血縁関係のあるなしにかかわらず、個人が個人へと無償で財産を与えることを「贈与」といいます。そしてその贈与額によっては、受けとった側が「贈与税」を支払わなければならなくなります。 となると、気になってくるのは「いくらも...
亡くなった方(被相続人という)が遺した財産が一定の額を超えていた場合、その財産を受け継ぐ相続人には相続税の支払い義務が生じます。その相続税ですが、いつまでに払わなければならないのかをご存じでしょうか。 被相続人が亡くなった直後は葬儀などで慌ただしく過ごすため、相続税どころではなくなります。しかし...
※令和6年度税制改正大綱により、2023年以降も特例が延長されることが発表されました。その他の改正点など、詳しくは【2024年改正情報】をご覧ください。 また令和4年度税制改正において、非課税限度枠は最大1,500万円→1,000万円に変更されています。詳しくは【2022年改正情報】をご覧ください。 財産が無償で...