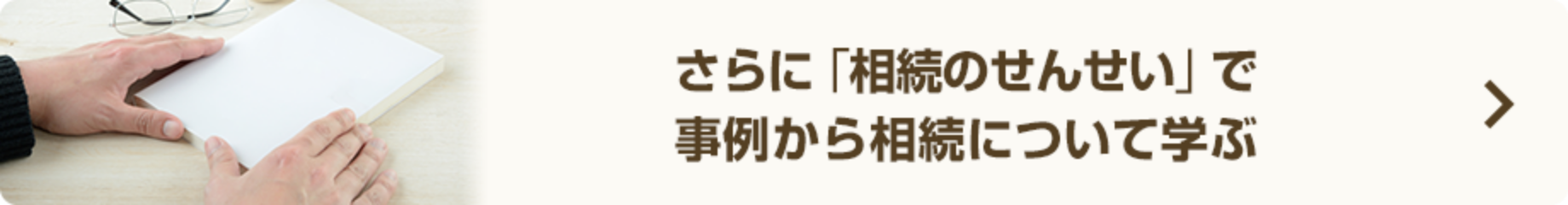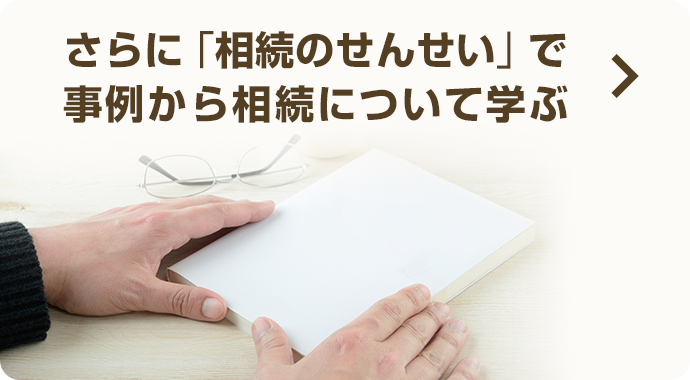遺贈寄付とは?3つの種類やメリットを徹底解説!
Tweet自分の死後に財産を受け継ぐ人たちの相続税負担については、できれば少なくしたいものです。そんな時、「遺贈寄付」や「贈与」を活用してみるという方法があります。
相続や遺贈によって課せられる相続税を、非課税にしたり、減らすことができる可能性があります。
この記事では、遺贈寄付や贈与の種類、それぞれどんなメリットがあるのかなどを徹底解説いたします。
目次
そもそも遺贈とは?
「遺贈」とは、亡くなった方(被相続人という)の遺言に則り、法定相続人やそれ以外の人や団体にその遺産の一部、または全部をゆずることです。法定相続人にも「遺贈」することはできますが、相続人の場合には「遺贈」にするよりも「相続」のほうがメリットがあります。(詳細は後述します)
遺贈する側を「遺贈者」、遺贈する相手のことを「受遺者」といいます。受遺者には生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの人以外の団体や法人を設定することもできます。
また、遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。その内容や遺贈の方法によって大きな違いがあり、受けとる側や相続人にも大きな影響を与えるので注意が必要です。
包括遺贈
「包括遺贈」とは、遺産の具体的な内容を特定せずに、全部あるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって与える遺贈を指します。たとえば、「Aさんに自分の資産の2分の1をゆずる」というように遺言書には記載されます。
ただし、その遺産のなかには、借金などのマイナスの資産(負債)が入っている場合もあります。受けとる側は、その負債も割合に応じて併せて引き継ぐことになるので、ありがたくない場合もあります。
特定遺贈
「特定遺贈」とは、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定して、与えることです。たとえば、「Aさんには不動産を、B法人には現金を、Cさんには株式を与える」というように遺言書には記載されます。
遺贈にかかる税金
遺贈にも税金が課せられます。
遺贈に課せられる可能性がある税金は、
- 相続税
- 不動産取得税
- 登録免許税
となります。
この三つの税金について見ていきましょう。
相続税
遺贈とは、財産を相続人、あるいは第三者にゆずるという点で贈与と似ています。しかし、「贈与税」ではなく、「相続税」の課税対象です。ただし、納税義務があるのは、課税価格の合計額が基礎控除を超える場合のみです。
不動産取得税
相続税以外にも、不動産を遺贈した場合には「不動産取得税」が課せられる場合があります。
不動産取得税とは、文字どおり不動産を取得した時にかかる税金のこと。不動産売買や贈与などのケースで発生しますが、遺贈の場合に不動産取得税が課せられるのは、「特定遺贈」で相続人以外の人が不動産を受けとった場合のみです。
包括遺贈の場合や相続人が不動産を取得する場合には、不動産取得税は課せられません。 たとえば、「(相続人ではない)Aさんに、○○の土地をゆずります」というように書かれている場合には、特定遺贈になり、不動産所得税が課せられます。
登録免許税
不動産を遺贈した場合には、「不動産取得税」以外にも「登録免許税」が課せられます。
「登録免許税」とは、不動産の所有権移転登記をした時に必ずかけられる税金です。
つまり、登録免許税は相続人でも相続人以外でも発生しますし、特定遺贈でも包括遺贈でも課せられます。
ただし税率は、受遺者が相続人の場合と第三者の場合では異なります。
相続人の場合、固定資産税評価額の1,000分の4で、第三者の場合は固定資産税評価額の1,000分の20となっています。固定資産税評価額とは、固定資産税を決定するために各自治体が個別に算定する「不動産の評価額」のことです。
たとえば、遺贈で固定資産税評価額が2,000万円の不動産をゆずり受けたとした場合、相続人にかかる登録免許税は8万円で、第三者にかかる登録免許税は40万円になります。
遺贈で得た財産にかかる相続税の計算方法
相続税の計算方法は、遺贈の場合でも、遺産分割協議により取得した場合でも基本的に変わりはありません。相続税には基礎控除があるので、課税されるのは、遺産の合計額が基礎控除額を超える場合です。
相続税の計算では、まず課税遺産総額を算出します。計算式は次のようになります。
課税遺産総額 = 遺産の合計額 − 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
法定相続人だけが相続する場合には、相続人全員が基礎控除の計算対象に含まれます。しかし遺贈の場合には、遺贈者全員が基礎控除の計算対象になるわけではありません。法定相続人の人数しか基礎控除の対象にならないのです。
詳しくは「相続税の税率と計算方法|事例付きでわかりやすく解説」の記事をご覧ください。
「遺贈寄付」とは?
遺贈寄付とは、社会貢献活動に役立てることなどを目的に、被相続人の遺産を遺言によって特定の団体(個人)にゆずることです。この遺贈寄付には、遺産のほかにも生命保険や信託による寄付も含まれます。遺贈寄付をした財産は相続税の控除対象に含まれるので、納めるべき税金を減らすことができます。特別な手続きも不要です。
ただしどの団体(個人)に遺贈寄付をしても優遇措置が受けられるというわけではありません。優遇が受けられるのは、国や地方公共団体、認定NPO法人、特定公益増進法人(公益社団、財団法人、社会福祉法人、学校法人など)などに限られます。
つまりこれら以外の団体や個人に遺贈寄付をしても相続税の節税効果はありません。
遺贈寄付の3つの種類
「遺贈寄付」は、「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」「生命保険・信託による遺贈寄付」の大きく3種類に分けられます。
遺言による遺贈寄付
「遺言による遺贈寄付」とは、遺言書に自身の財産を寄付する旨を記載しておくことで、死後にその遺言書に従って寄付することを言います。寄付する団体等には、あらかじめ何を寄付するのかを伝えておくことが大切です。もし伝えていなかった場合、手続きに時間がかかったり、受け取りを拒否されることもあります。
相続財産による遺贈寄付
「相続財産による遺贈寄付」とは、亡くなった方からではなく、遺産を受け取った人が寄付することを言います。事前に遺産を受け取る予定の人に寄付したい旨を伝えておく必要があります。遺言による遺贈寄付と同様に、寄付する団体等にあらかじめ何を寄付するのかを伝えておくことが大切です。
生命保険・信託による遺贈寄付
「生命保険・信託による寄付」とは、死亡保険金や生命保険契約によって生じた利益部分を寄付するものです。保険会社との契約や保険契約の管理・運用を信託銀行に任せることによって行うことが可能になります。
遺贈で得た財産にかかる相続税を計算する際の注意点
必ずしも納税義務があるわけではない
遺贈されたすべての受遺者が相続税を納めなければならないわけではありません。ここまで述べてきた遺贈寄付された団体がそれにあたります。しかし遺贈寄付を受けた団体の性格によっては、相続税を不当に減少するために寄付されたもので、相続税を納めるべきとみなされる場合もあります。
たとえば、運営組織が不適正であることや特定の一族の支配を受けている、または、遺贈者の関係者が運営に関わり、遺贈することでその関係者に特別の利益を与えるような組織などです。
また、遺贈寄付を受けた側が、個人もしくは法人格を持たない団体の場合は、原則として相続税が課されます。ただし、例外として、その団体等が公益事業を行っており、受け取った財産をその事業に使った場合には相続税が非課税になります。
相続税が2割増になる場合がある
遺贈を受けるのが、遺贈者の配偶者や子といった法定相続人ではない場合には、一般の相続人と比べて相続税が2割加算されます。
お世話になった方などに遺贈する場合、相続税が2割加算になる可能性があるので、注意が必要になります。
相続税の2割加算については下記の記事をご参照ください。
基礎控除の計算に第三者は含まない
法定相続人だけが相続する場合、相続人全員が基礎控除の計算対象に含まれます。しかし遺贈の場合には、受遺者全員が基礎控除の計算対象になるわけではありません。
法定相続人の人数だけしか基礎控除の対象にならないのです。
たとえば遺贈されるのが4人でそのうち法定相続人が3人の場合には、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
遺贈予定の人が行うべき節税対策
将来的に遺贈を検討しているなら、押さえておいたほうがよい節税対策がいくつかあります。
- 毎年少しずつ贈与する「暦年贈与」
- 受遺者が子どもや孫の場合には「一括贈与」
- 受遺者が配偶者の場合には「今すぐ贈与」
それぞれ詳しく見ていきます。
暦年贈与を活用する
「暦年贈与」とは、贈与税の基礎控除枠を利用して毎年少しずつ贈与していく方法です。一番スタンダードな節税対策といえるでしょう。
贈与税の基礎控除枠は、毎年110万円までとなっています。つまり、1年に110万円分までの贈与であれば贈与税が課せられないということです。
そこで、遺贈を予定している相手に毎年110万円分ずつ贈与していくことが考えられます。何年かかければ贈与額も大きくなり、しかも贈与した分、遺産も減らせることになるので、死亡後の相続税を減額できます。時間をかければ残った遺産額が基礎控除内に収まる可能性もあります。
財産を受け取る受贈者は親族に限らないので、この節税対策は受遺者に予定している人が第三者のケースでも適用できます。
ただし「毎年同じ人物から同じ時期に同じ額を贈与されている」場合、税務署が「定期贈与」と判断する可能性が高くなります。たとえば父親が娘の誕生日に100万円を10年間にわたって贈与した場合、「最初から1,000万円を贈与する意図があった」と税務署は考え、税務調査に入ることもあるのです。こうした事態を回避するには贈与額や贈与の時期を変更することがポイントとなります。
一括贈与を検討する
受遺者を子どもや孫などの直系の卑属に予定している場合には、目的を定めた「一括贈与」を検討するのも一つの手です。贈与するお金の目的ごとに非課税制度が設けられています。
たとえば孫への教育資金として遺贈を検討している場合、「教育資金の贈与税非課税制度」が考えられます。この制度を使えば、入学金や授業料、学用品の購入、修学旅行の費用など教育に関わる資金を贈与された場合に1,500万円までが非課税となります(塾や習い事、通学のための定期券代などは500万円までが非課税)。対象となるのは令和5(2023)年3月31日までに30歳未満であり、両親や祖父母から資金を贈与された人たちです。
次に贈与する目的が親族の「結婚・子育て資金」の場合、「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」があります。この制度を使えば、子どもの結婚や子育て(孫)に使うために贈与された資金に対しては、1,000万円までが非課税となります。ただし、結婚のための資金の非課税枠は300万円までです。対象となるのは、令和5(2023)年3月31日までに20歳以上50歳未満で、直系の両親や祖父母から資金を贈与された人たちです。つまり配偶者の両親や祖父母では適用できません。
そして、マイホームを購入する子や孫に対して、資金面でサポートを行うケースは多いといえます。その際に活用したいのが「住宅取得等資金の非課税の特例」です。令和2(2020)年4月1日以降に住宅の取得に関する贈与があった場合は、最大1,500万円までが非課税となります。
非課税限度枠はマイホームの購入時期や消費税率、住宅の性能(耐震性やバリアフリーなど)によって変わってきます。
目的を定めた贈与を考えておられる方は、一度これらの特例制度を調べてみることをおすすめしますが、これらの制度にはさまざま条件があるうえに、場合によっては将来の相続税が跳ね上がる可能性があるというデメリットもあります。活用したいと思った時はまず税理士に相談するとよいでしょう。
これら贈与税が非課税になる制度の詳細については下記の記事をご覧ください。
遺贈せずに今すぐ贈与する
自分の死後、配偶者に家を遺贈しようと考えているならば、今すぐに贈与してしまうほうがよいかもしれません
20年以上連れ添った夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、2,000万円までが贈与税非課税になります。通称で「おしどり贈与」と呼ばれる非課税制度です。毎年110万円までの基礎控除枠も適用されるので、合計で2,110万円分までは非課税で贈与できるということです。先に遺産を減らしておけば、自分の死後の相続税を減額できる可能性が高まります。
おわりに:遺贈寄付は3種類の中から自分に合った方法を選択しましょう
遺贈や贈与をうまく活用して節税をするとともに、社会貢献できるというのは一石二鳥以上の価値があります。
とくに今、「おひとりさま」が増えています。独身者が亡くなった場合に法定相続人がいない場合、利害関係人に遺産が分配されたり、最終的には国庫に納められたりします。ただし、手続きが煩雑なので、少額の財産だった場合などには自治体が保管することになるのです。この「引取り手がない遺産」は「遺留金」といい、自治体を悩ます問題になっています。そうした「遺留金」を出さないためにも、「遺贈寄付」を検討してみるのも一つの手段です。
この記事では相続や遺贈、贈与にかかる税金と、その節税の方法を解説してきました。ぜひお役立ていただきたいと思います。
ただ、なかには自分だけで遺贈や贈与を決断することに不安を感じたり、受遺者や受贈者に課せられる税金に関してもっと詳しいアドバイスがほしい方もいるかもしれません。そういう場合は専門知識が豊富な税理士への相談も検討してみてください。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表