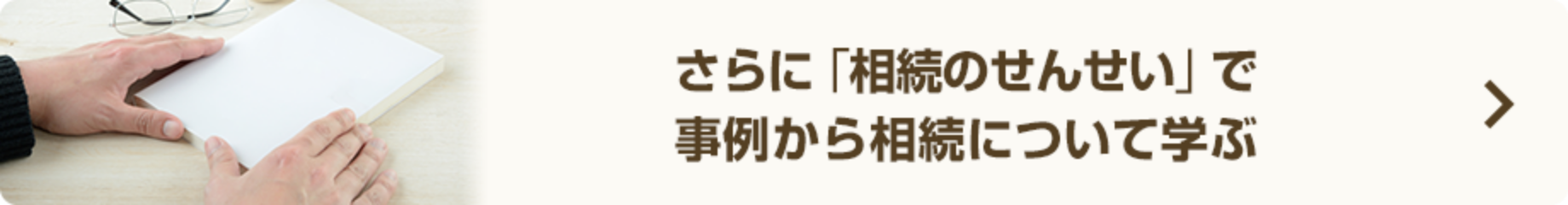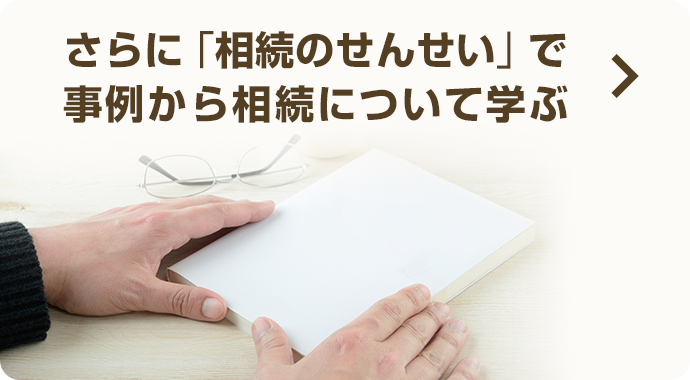贈与税が非課税となる夫婦間の住宅贈与の特例とは|相続が起きた際の取り扱いも解説
Tweet「贈与」は、それがたとえ夫婦間や親子間のように家族の間で行われるものであっても該当します。そして、一定の額を超える贈与があった場合は、財産を受けとった人が「贈与税」を支払わなければなりません。
贈与税の対象となる財産は現金に限らず、不動産や有価証券、貴金属なども含まれます。
今回の記事ではそのなかでも「夫婦間の住宅の贈与における特例(贈与税の配偶者控除)」について解説いたします。夫婦間における居住用不動産の贈与は非課税になる場合があるので、そのような贈与を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
贈与税は原則として夫婦間の贈与も対象
通常、夫婦は財産を共有しており、「贈与」は存在しないと考えている人も多いかもしれません。しかし原則として夫婦それぞれが自分で管理している財産(結婚前からもっていた貯金や自分の能力で働いて得たお金など)は「夫婦別産制」により、夫婦それぞれの財産と考えるため、一方が一方に財産を与えた場合は贈与となります。
その贈与額が一定の額を超えると贈与税の申告義務が生じ、税務署に申告をしなければなりません。以下、見ていくことにしましょう。
贈与税の計算方法
まず、どれくらいの額の贈与があれば贈与税の申告義務が生じるかということから始めましょう。贈与税は原則として「暦年課税」により計算されます。
暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与財産の総額に対して課税するもので、年間110万円までの非課税枠が設定されています。この枠を超えない限りは贈与税はかかりません。
したがって、贈与税の申告義務が生じるのは年間110万円を超えた時です。この場合、贈与財産の総額から110万円を差し引いた残りの部分に一定の税率を乗じて贈与税額を計算することになります。その計算方法は次のとおりです。
【贈与税額=(受けとった額−110万円)×税率−控除額】
夫婦間の場合、税率は「一般税率」が適用されます。以下の表を参考にしてください。
一般税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
生活費は、原則非課税
年間110万円超の贈与には贈与税がかかるということで、「毎月の生活費に関して贈与税の申告をしなければならなかった……?」と心配になった人がいるかもしれません。しかし、ご安心ください。贈与税はすべての贈与に対して課税されるわけではなく、扶養義務者(配偶者や親など)からの「生活費」や「教育費」のうち、通常必要と認められるものは非課税となっているのです。生活費や教育費は暮らしに必要なお金ですから、これらに対する課税は妥当ではないという考えがあります。
生活費とは具体的には家賃や食費、水道光熱費、日用品・家電製品の購入費など。ほかに医療費も含まれます。教育費は受験料や入学金、授業料、教材費、文具費などです。ただし、もらった生活費を別の目的で使うと贈与とみなされます。たとえば、不動産や車などを購入するといったケースです。
夫婦間の住宅(居住用不動産)の贈与
自分が存命中に配偶者に不動産を贈与しておきたいという人も少なからずいることでしょう。贈与は現金だけではなく、不動産も贈与税の課税対象となります。
夫婦間の居住用不動産の贈与には非課税となる特例があるのですが、もしそれを使わなかった場合、贈与税はどうなるのかをまずは見てみることにしましょう。
夫婦間の住宅(居住用不動産)の贈与も課税対象
夫から妻へ、あるいは妻から夫へ不動産を無償で与えた場合も贈与となり、その評価額が基礎控除額の110万円を超えると贈与税が課されることになります。不動産の評価額が110万円以下になることは現実的に考えにくいので、贈与税の申告義務が生じるケースがほとんどだといっていいでしょう。その意味でも、不動産の贈与は慎重に行う必要があります。
配偶者のことを思っての不動産の贈与ですから、実際に贈与税額がどれくらいになるかも気にかかってくるところです。次に、参考までに仮に非課税を適用しなかった場合について、具体的な数字を計算してみることにしましょう。
不動産の贈与で、贈与税はどのくらいかかるのか
夫から妻に、土地と建物の評価額が合わせて2,000万円となる不動産が贈与されたと仮定します。この場合、贈与税はいくらになるでしょうか。先に挙げた贈与税の計算式を用いて計算してみます。
まず、受けとった不動産の評価額2,000万円から、基礎控除額の110万円を差し引きます。すると1,890万円になりますから、これに該当する税率を当てはめます。税率は50%で、控除額は250万円が設定されています。以上の数字を計算式に落とし込むと、次のとおりです。
【(2,000万円−110万円)×50%−250万円=695万円】
贈与税は695万円となり、贈与された2,000万円相当のおよそ3分の1を税金として払わなければならないことがわかります。なお、贈与税は現金による一括納付が原則ですから、その負担についても考えておく必要があります。
夫婦間の住宅の贈与における特例「贈与税の配偶者控除」
上記の例で「せっかく贈与をしても、3分の1が税金になって、しかも現金で納めなければならないのなら、しないほうがいいのでは……」と思った人もいることでしょう。
しかし、じつは夫婦間の住宅(居住用不動産)の贈与に関しては税負担が軽くなる特例が設けられているのです。場合によっては贈与税がゼロになることもあります。以下、その内容について説明いたします。
特例適用の効果
夫婦間の住宅贈与に関して税負担が軽減される特例は、「贈与税の配偶者控除」と呼ばれています。これは配偶者に対して「居住用の不動産あるいはその購入資金」を贈与した場合は2,000万円までが非課税になるというものです。贈与税の基礎控除額110万円をあわせて使うこともできるので、2,110万円までが非課税となります。
たとえば、先に例として出した「土地と建物の評価額が合わせて2,000万円となる不動産」の場合は、そのまま非課税枠に収まるため、贈与税を支払わなくてもいいということになります。この特例を使わなかった場合の贈与税は695万円でしたから、大変な差が生じるというわけです。
特例適用の要件
「贈与税の配偶者控除」は別名「おしどり贈与」と呼ばれています。この特例を使う要件としては次の三つが挙げられます。
①婚姻関係が20年以上であること
おしどり贈与という名の由来ともいえますが、要件の一つは婚姻期間が20年以上の夫婦であることです。この場合の夫婦とは法的な婚姻関係にあることを指します。そのため、事実婚の場合は対象外となります。
②居住用の不動産または購入資金の贈与であること
対象となる不動産は「居住用」でなければなりません。したがって別荘やセカンドハウスは対象外となります。居住用であれば、不動産そのものでも購入用の資金でも大丈夫です。
③翌年の3月15日までに住み始めること
対象となる不動産には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住み始めることが必要です。すでに暮らしている自宅や建て売り住宅の購入なら問題はないでしょうが、新たに建築する場合は入居時期に気を付けましょう。
そのほかの注意点としては、「対象は国内の不動産であること」「同じ配偶者からの贈与は一生に一度のみ」ということが挙げられます。
また、おしどり贈与には贈与税の申告が必要です。たとえ贈与税の納税が生じない場合でも、申告はしてください。申告に必要な書類は以下のとおりです。
おしどり贈与の申告に必要な書類
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本または抄本
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の附票の写し
- 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書(贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことが分かるもの)
- 固定資産税評価証明書など居住用不動産を評価するための書類(不動産の購入資金ではなく居住用不動産を贈与された場合)
その後相続が起きた際の取り扱い
相続税のことに詳しい方は「贈与をした後に贈与者が亡くなった時は、その3年前まで(相続開始前3年以内)の贈与は相続税の対象になる」ということをご存じかもしれません。これは亡くなる直前に生前贈与を進めると、行き過ぎた相続税対策になりかねないので、その抑止策として設定されているルールです。
おしどり贈与を使った後、贈与者が亡くなってしまい、相続が発生することは十分に考えられます。この場合、贈与された不動産の扱いはどうなるのでしょう?
以下で、考えてみることにしましょう。
税金計算上の持ち戻し
基本的に贈与された財産は、その時点で受贈者(贈与を受けた人)のものとなります。しかし行き過ぎた相続税対策を防ぐことを目的として、贈与者(贈与をした人)が亡くなった場合は、その3年前まで(相続開始前3年以内)の贈与はなかったこととし、相続税の課税対象に組み込まれることになります。このことを「相続税の持ち戻し」といいます。
ただし、これには例外があり、おしどり贈与はまさにその例外に該当します。したがって、贈与された居住用不動産をあらためて相続財産としてカウントする必要はありません。
特別受益としての持ち戻し(改正)
相続にはまた「特別受益」という考え方もあります。複数いる相続人のうちの一人が亡くなった方(被相続人という)から生前贈与などを受けていた場合を指します。
たとえば、3人兄弟のうち長男と次男が何ももらっておらず、末っ子だけが生前贈与として1,000万円をもらっていたとすると、これが特別受益に当たります。
長男と次男にしてみれば、1,000万円を差し引かれた残りの相続財産を兄弟で三等分することに不公平を感じてしまうのも無理はありません。そこで特別受益に関しても持ち戻しが行われることになっています。
従来、特別受益の持ち戻しには時効がなかったのですが、令和元年(2019)の民法改正によって、原則として死亡前10年以内の贈与に関しては持ち戻しを行うことになりました。
では、おしどり贈与による配偶者への居住用不動産の扱いはどうなるのでしょうか。
じつは、これも例外措置がとられ、特別受益には該当しないことになっています。したがって、贈与された居住用不動産をあらためて相続財産としてカウントする必要はありません。
おわりに:夫婦間の住宅贈与の特例「贈与税の配偶者控除」を使う場合は税理士に相談を
財産を無償で渡すことを贈与といい、贈与額が年間110万円を超えると贈与税の申告義務が生じます。たとえ夫婦間であっても例外ではありません。
ただし夫婦間の居住用不動産の贈与に関しては、2,000万円までの非課税枠が設定されており、これを活用することで税負担を大きく軽減することができます。この記事では夫婦間の住宅(居住用不動産)贈与に関するポイントを解説いたしました。
とはいえ、夫婦間の住宅贈与を検討するなかで、申告手続きなどの面において不安や疑問を感じる方も少なくないでしょう。記事でもふれたとおり、特例を使う場合はいくつかの要件があり、それらを満たさないまま申告をすると、想定外の贈与税を支払うことになります。
もし心配な方は税の専門家である税理士に相談することが有効な解決手段となります。確かな実績をもつ税理士であれば「おしどり贈与」の適用を受けるための手続き準備もしっかりとサポートしてくれますし、有効な節税対策もさまざまに提供してもらえます。まずは気軽に相談することから始めてみましょう。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表