スクイーズアウトとは?実施メリットや手法、 TOBとの違いについて解説
Tweetスクイーズアウトは、企業(または支配株主)が一定の持株比率要件を満たした場合に、法的手続を通じて少数株主に株式の売却を求める仕組みです。全株式の支配を実現するために、事業承継やM&Aの最終段階などでよく用いられています。本記事では、スクイーズアウトの基礎知識、TOBとの違い、メリット・デメリット、代表的な手法について解説します。
目次
スクイーズアウトとは
スクイーズアウトとは、企業(または支配株主)が一定の持株比率要件を満たした場合に、法的手続を通じて少数株主に株式の売却を求める仕組みです。事業承継やM&Aの場面で活用され、企業統治の効率化や経営の自由度向上を目的とするケースが増えています。
意味
英語の「squeeze out」には「締め出す」「押し出す」といった意味があります。企業の買収や経営統合が進む過程では、上場企業の株式を一定条件で買い付けるTOB(株式公開買付け)などを通じ、大半の株式を取得するのが一般的ですが、100%に到達しない限りは、少数株主が残ります。スクイーズアウトは、M&Aの最終段階で用いるケースが多くなっており、組織再編の合理化やスムーズな経営判断を図るための施策として重要な役割を果たします。
スクイーズアウトとTOBの違い
TOBは「自主的な売却」を前提とする手段です。これに対し、スクイーズアウトは「法的強制力を伴う排除手段」であるという点が大きく異なります。TOBでは、市場外で不特定多数の株主から任意で株式を買い取ります。提示された価格で売却するかどうかは、あくまで株主の自由に委ねられるのが特徴です。
一方で、法的な強制力を持つスクイーズアウトでは、残った少数株主の同意を得ずに、株式を取得することが可能です。例えば80〜90%以上の株式を取得した後、さらに残る10〜20%の株主から株式を取得して完全子会社化したい場合、TOBだけでは対応できません。
そこで、法的な強制力を持つスクイーズアウトを活用して少数株主の株式を買い取れば、支配権を100%に近付けられます。上場企業M&Aでは初期段階でTOB、その後スクイーズアウトという流れが一般的です。一方、非上場の中小企業M&AではTOBは用いられず、スクイーズアウト手法のみで株主整理を行うのが一般的です。
スクイーズアウトを実施するメリット
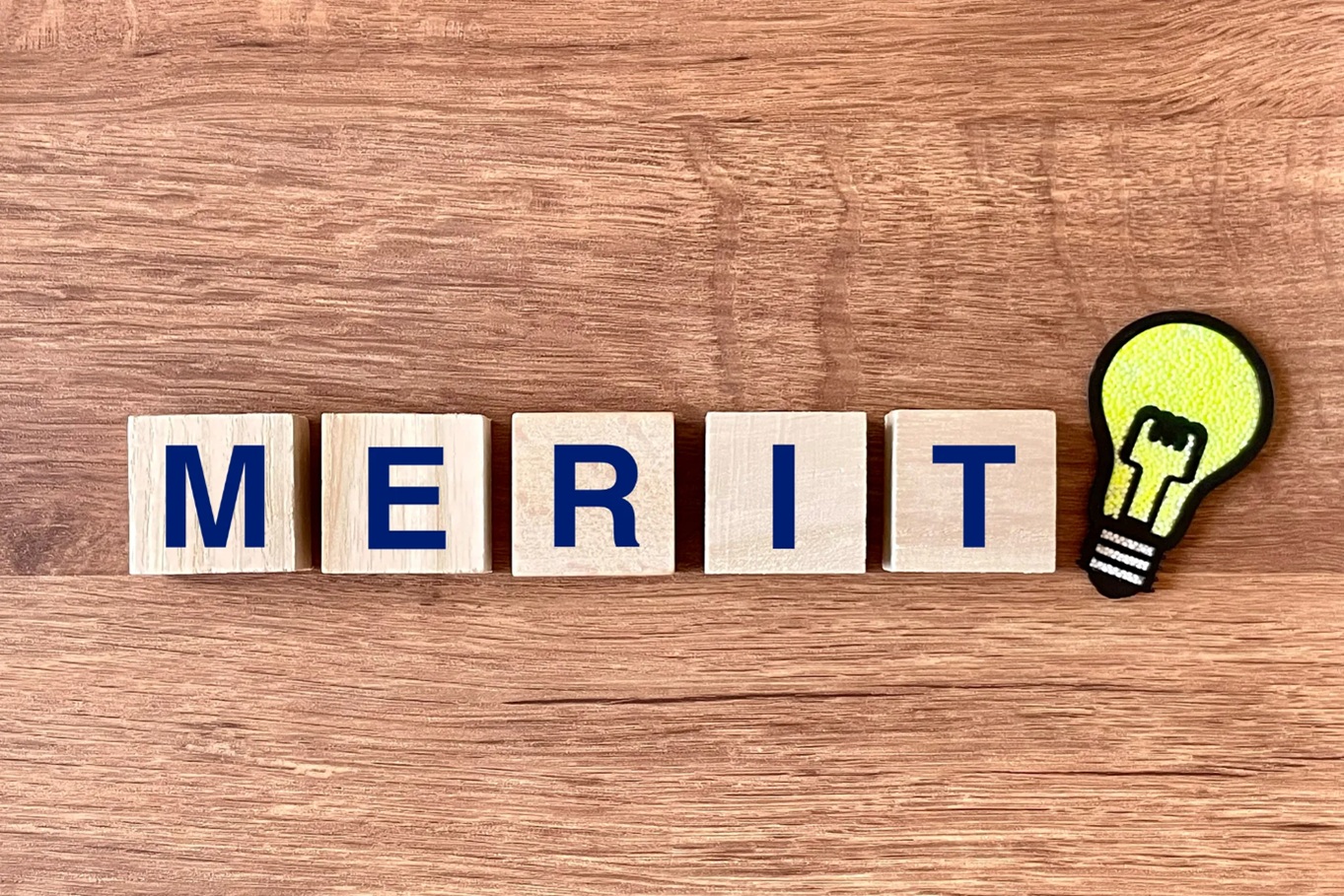
スクイーズアウトはM&Aや事業承継の場面で活用されており、実施によって、経営の自由度や効率が大きく向上することが期待できます。主なメリットとして、以下の五つが挙げられます。
- 株式の100%取得による完全支配の実現
- 少数株主とのトラブル回避・訴訟リスクの低減
- 税制面での合理化と優遇措置の活用
- 意思決定の効率化と経営効率の向上
- 上場廃止による管理負担の軽減
スクイーズアウトは、単に少数株主を排除するものではなく、企業の将来戦略や経営の質を向上させるための重要な選択肢です。
持ち株比率を100%にできる
スクイーズアウトを実施すれば、企業は少数株主の保有する株式を強制的に買い取り、全株式の支配を実現できます。すべての議決権を経営側が持つため、株主総会での承認手続きや意見調整の手間もかかりません。経営上の重要な意思決定をスムーズに行えるだけでなく、グループ経営全体のガバナンス強化や内部統制の一体化も図れます。企業再編や資本構成の見直しを検討している企業にとっては、大きなメリットとなります。
少数株主を排除し訴訟リスクを低減させられる
企業経営において、少数株主の存在が思わぬトラブルの火種となるケースは少なくありません。経営方針に反対する声が上がったり、配当や資産処分に関して意見が分かれたりした場合、株主代表訴訟などのリスクが生じます。スクイーズアウトにより少数株主を整理すれば、上記のような法的リスクを未然に防げます。株主総会の運営や株主管理もよりシンプルになるため、柔軟な企業活動を行えるようになるのは大きな利点です。
税制上のメリットを得られる
スクイーズアウトによって完全子会社化することによりグループ通算制度の適用が可能となるなど、税務処理の効率化が期待できます(ただし制度適用には一定の要件を満たす必要があります)。
例えば、連結納税制度(現行ではグループ通算制度)では、グループ間での利益や損失の通算が可能となり、納税額を最適化できます。M&A後の組織再編時も株主構成が整理されていれば、株式移転や会社分割などの手続きがよりシンプルになることもメリットです。
企業の意思決定を円滑化させられる
スムーズな意思決定が可能になることも、スクイーズアウトの魅力です。株式が分散している状態では、経営上の重要な判断を下すたびに株主との調整や合意形成が必要です。特に少数株主の理解を得られない場合、成長戦略や再編計画が思うように進まないリスクがあります。スクイーズアウトによって株式を集中させれば、経営陣は外部の干渉を受けずにスムーズかつ柔軟な意思決定が可能です。変化の激しい市場環境に対応するためにも、経営戦略の自由度を高めることは大きな強みになります。
上場廃止を行える
上場企業がスクイーズアウトを実施する場合、その主な目的は上場廃止の実現です。すべての株式を取得し、少数株主が存在しない状態にすれば、証券取引所のルールに基づいて上場廃止の手続きを進められます。企業は上場廃止によって、証券取引所が求める厳格な開示義務や、内部統制の運用義務から解放されます。そのため、上場維持に伴うコストや人的リソースを大幅に削減することが可能です。また、上場企業が求められる透明性・公平性を重視した経営判断や、機関投資家の意見を配慮する意思決定からも解放されます。
スクイーズアウトのデメリット

スクイーズアウトの実施は、一定のリスクや負担も伴います。論点となるのは、主に以下の3つです。
- 手続きが複雑で完了までに時間がかかる
- 少数株主への対価が発生し、費用がかさむ
- 訴訟などの法的トラブルに発展する可能性がある
スクイーズアウトを行うには法的手続きが必要であり、少数株主の権利にも配慮しなければなりません。専門家のサポートを得ながら、慎重に準備を進めましょう。
手続きに時間がかかる
スクイーズアウトは、法的に認められた手続きであり、実施までにさまざまな段階を経る必要があります。例えば「株式併合」では株主総会の特別決議が必要ですが、「特別支配株主の株式等売渡請求」では株主総会決議を経ずに実行可能です。ただし、いずれも公告や通知、債権者保護手続きなど一定の法的ステップを踏む必要があり、完了までには時間がかかります。
関係者への説明や社内調整も並行して行われるため、実務上の負担も大きく、想定以上にスケジュールが延びるケースも珍しくありません。加えて、少数株主からの異議申し立てや調停・訴訟が発生した場合は、法廷手続きが必要です。早めの段階で、法務・会計の専門家を交えたスケジューリングを検討するようにしましょう。
少数株主への対価が必要となる
スクイーズアウトを行う際は、少数株主に対して保有株式に見合う公正な対価を支払う法的義務が発生します。つまり、企業側が少数株主にとって不公平なほど低い価格を設定し、株式を買い取って排除するような恣意的行為は許されません。スクイーズアウトでは、少数株主への対価として、専門家による株式価値の評価(バリュエーション)が行われます。
その過程で、外部の会計士・金融機関・M&Aアドバイザーなどの専門家を起用する必要があり、さまざまなコストが発生します。また、少数株主に対価を提示する際は、説明や根拠を明確に示さなければなりません。上場企業の場合、市場価格との乖離が問題視されるため、客観性と透明性を十分に担保する必要があります。
裁判に発展する可能性がある
スクイーズアウトの性質上、少数株主が法的手段に訴えるリスクを伴います。株式併合後に、対価の不公正を理由とする訴訟が提起される事例は珍しくありません。裁判では、企業の評価方法やその合理性などが詳細に問われます。訴訟が長期化すれば、コストの増加だけでなく、メディア報道や風評リスクによって企業イメージが低下するおそれもあります。
社内の労務環境や、従業員の士気に影響する可能性もあるため、スクイーズアウトを実施する際は、株主や内部への丁寧な説明や透明性を確保することが重要です。あらかじめ訴訟リスクを織り込んだうえで、どのような経営判断をすべきか検討しましょう。
スクイーズアウトの四つの手法

スクイーズアウトは、法的に認められた複数の手法から目的や状況に応じたものを選択して実施します。対象企業の株主構成やスケジュール、訴訟リスクなどを総合的に勘案して決定するのが一般的です。それぞれ法的な要件や実務内容が異なるため、自社にとって最適な手法を選択するようにしましょう。
1. 特別支配株主の株式等売渡請求制度
会社法第179条以下に定められた制度です。買収者(親会社など)がそのターゲットとなる会社の議決権の90%以上を持っている場合、その特別支配株主は、他の少数株主に対して株式を手放すよう求める権利を持ちます。最大の特徴は、裁判所の許可が不要であり、手続きが比較的シンプルである点です。
実務上は、売渡請求を行う旨を会社側から通知・公告し、一定の期間内に異議がなければ手続きは完了します。ただし、対価の内容やその「公正性」は、後から争点になる可能性があるため、事前に評価資料や価格算定根拠を整えることが重要です。比較的簡単にスクイーズアウトを行えるため、多くの場面で活用されている制度です。
会社法 第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求 (株式等売渡請求)第百七十九条 | e-GOV
2. 全部取得条項付種類株式
会社が一定の条件を満たせば、株式を一括して取得できる条項が付与されたものです。まず会社は株主総会の特別決議で、少数株主が持っている普通株式を、全部取得条項付種類株式へと変更します。その後は、あらかじめ設定された条件に従って、該当する種類株式を取得してから対価を支払い、株式を回収するのが基本的な流れです。全部取得条項付種類株式を用いるメリットは、取得のタイミングや、対価の設計に柔軟性がある点です。
しかし手続きが複雑であり、会社法上の詳細な要件を正確にクリアしなければなりません。さらに株主総会での特別決議が必須なため、議決権の構成によっては成立が困難な場合もあります。あらかじめ取得条件を設計できるため、段階的なスクイーズアウトの計画を立てる際には便利な手法です。
全部取得条項付種類株式については以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参考ください。
種類株式とは_ 事業承継に活用するメリットと方法について
会社法 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)第百七十一条 | e-GOV
3. 株式交換
自社の株式を対価として交付し、その見返りに相手企業の株式を取得する手法です。会社法に基づいたM&Aスキームであり、非上場会社の整理や、持ち株比率の調整にも活用されます。スクイーズアウトの文脈では、すでに過半数以上の株式を保有している親会社が、残りの少数株主の株式を自社株と交換するために用いる制度です。親会社が残りの少数株主の株式を株式交換で取得する際には、対象会社側で株主総会の特別決議が必要となります。対象企業の株主は、交換比率に基づいて親会社の株式を受け取り、結果的に旧会社の株主ではなくなるという仕組みになっており、これが「少数株主の排除」に該当します。
ただし、株式交換の対価が親会社株式である以上、現金対価での整理には向いていない点に注意が必要です。さらに、交換比率の設定やその根拠の説明が不十分である場合、株主からの反発を招く可能性もあります。
株式交換については以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参考ください。
会社法 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(株式交換契約の締結)第七百六十七条 | e-GOV
4. 株式併合
発行済みの株式のうち複数の株式を統合して1株にまとめ、発行済株式総数を減らす手法です。例えば10株を1株に併合する場合、10株未満を保有している株主は、1株未満(端数)しか保有できない状態となります。会社法により、1株未満の端数株式は、原則として会社による買い取りが必要です。結果的に、少数株主の持ち株が強制的に消滅する形になるため、スクイーズアウトの一形式として用いられています。上場・非上場を問わず、多くの企業で利用されている制度です。
株式併合の特徴は、併合比率を調整して、排除対象を柔軟に変えられる点です。例えば「5株を1株に併合する場合」と「10株を1株に併合する場合」では、排除対象が異なります。株式併合には、株主総会の特別決議が必要です。さらに、株主からの反発を受けやすいため、事前に丁寧な情報開示と合意形成が欠かせません。排除される株主に対して公正な金銭対価の支払いが必要であり、その妥当性について争われるケースもあります。
上記四つの手法は、いずれも最終的に持ち株比率を100%に近付け、企業の支配権を完全に掌握するために用いられます。どの手法を採用するかによって、手続きの難易度やコスト、訴訟リスクが異なるため、実施前には十分な検討が求められます。
会社法 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(株式の併合)第百八十条 | e-GOV
事業承継・M&Aのお悩みはレガシィにご相談ください
スクイーズアウトは、少数株主の排除によって株式を100%保有し、企業の完全支配を実現するための手段です。事業承継やM&Aの最終局面において、経営の自由度向上や意思決定の合理化といった多くのメリットが期待できます。中小企業の経営者にとっては「どの手法が適切か」「どこまで費用をかけるべきか」など、判断に迷う場面があるかもしれません。相続専門税理士法人レガシィは、これまで中小企業の事業承継・M&Aを多数支援してきました。企業にとって最適なスキームをご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













