特別目的会社(SPC)とは? 設立メリットやスキームを解説
Tweet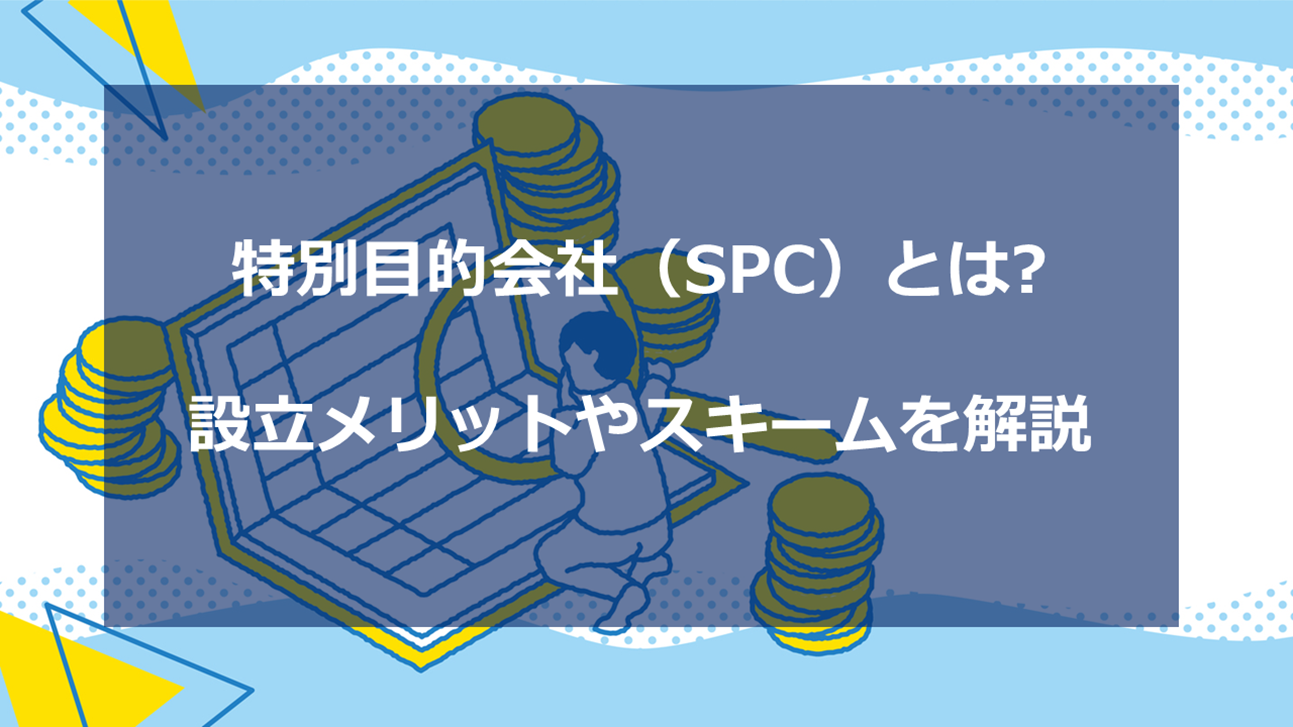
特別目的会社(SPC)は、主に資産管理や証券化、不動産投資、あるいは特定のプロジェクトにおける資金調達手段として活用されています。本記事では、特別目的会社(SPC)について理解しておきたいと考える経営者の方に向けて、基本的な仕組みや設立のメリットとデメリット、活用スキーム、設立の流れを解説します。
目次
特別目的会社(SPC)とは
特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)とは、特定の目的を達成するために設立される法人です。主に資産の流動化や不動産投資の分野で活用されており、投資家や企業にとって資金調達やリスク管理の手段として大きな役割を担います。特別目的会社(SPC)を設立するメリットは、事業リスクを限定しつつ効率的な資金調達が可能となる点です。
例えば、不動産投資の分野で特別目的会社(SPC)を活用した場合、投資対象の不動産を証券化することが可能となり、多くの投資家から資金を集めやすくなります。また、企業のM&A(合併・買収)においても、特別目的会社(SPC)設立は有効な選択肢であり、買収資金のスムーズな調達と買収後のリスクを最小限に抑えられます。
特別目的会社(SPC)の活用方法
特別目的会社(SPC)の活用方法は多岐にわたりますが、特に不動産の分野で幅広く利用されている傾向にあります。また、M&Aにおいても買収後のリスクを限定できるため、取引をスムーズに進められる可能性が高い点も魅力です。
不動産投資などが目的の場合
特別目的会社(SPC)を活用し、不動産を証券化すると、金融機関からの融資に加えて多様な投資家からの資金を調達できるようになります。特別目的会社(SPC)に対象の不動産を移転することで、企業の倒産リスクを特別目的会社(SPC)内にとどめることが可能です。この仕組みにより、投資家や関係者にとって安全性が高まり、効率的な運営が実現されます。
M&Aが目的の場合
M&Aにおいても、取引の円滑化やリスク管理に有効な特別目的会社(SPC)が多く活用されています。企業が他社を買収する際、設立した特別目的会社(SPC)を通すことで買収資金を調達しやすくなります。
特定のプロジェクト専用に設立される特別目的会社(SPC)は、資金の流れが非常に明確です。設立した特別目的会社(SPC)へ買収対象企業の株式や事業を移転し、その資産や将来予測されるキャッシュフローを担保に融資や出資を受けることで、買収に必要な資金を調達します。
金融機関や投資家にとって、財務状況を把握しやすい特別目的会社(SPC)は投資判断を行いやすいといった特性があります。また、買収後のリスクを特別目的会社(SPC)に限定することで、買収元の企業をさまざまなリスクから保護できるのも特徴です。
買収後に起こり得る法的なリスクから買収元を隔離し、予期せぬ損失が発生した際も特別目的会社(SPC)内に問題を留められます。特別目的会社(SPC)を利用したリスク分離により、M&Aの実施をより円滑に進めることが可能です。
なお、買収の範囲が明確な特別目的会社(SPC)を用いることで、買収手続きが簡素化されるケースがあります。契約の範囲が特定されることにより、無駄な交渉を削減できます。
特別目的会社(SPC)の活用スキーム
特別目的会社(SPC)には、異なる目的を持ったいくつかの活用スキームがあり、状況や目的に応じて慎重に選定する必要があります。
代表的なスキームは以下のとおりです。
- 資産の流動化を目的とした「特定目的会社(TMK)」
- 不動産投資に特化した「投資法人(REIT)」
- 投資家の匿名性を確保しながら出資できる「合同会社匿名組合(GK-TK)」
- 企業買収において活用される「レバレッジド・バイアウト(LBO)」
各スキームの特徴について、理解しておきましょう。
特定目的会社(TMK)
特定目的会社(TMK)は、資産の流動化を目的に設立されます。主に不動産や債権などの証券化を行う際に用いられ、企業が保有する資産を投資家向けの証券として発行し、流動性を高める役割を果たします。
このスキームを活用することで、企業は保有する資産を市場で売買しやすくなるため、資金調達の手段の多様化が可能です。また、資産の管理と運用を分離することにより、専門的なマネジメントを行いながらリスクを適切に分散させられるのも利点です。
投資法人(REIT)
投資法人(REIT)は、投資家から集めた資金をもとに不動産に投資し、それによって得た賃貸収入や売却益を投資家へ配当する投資信託の一種であり、「不動産投資信託」とも呼ばれています。少額からの分散投資を可能にし、不動産市場への投資を簡便にする点が大きなメリットです。
投資対象となる主な不動産は、景気変動の影響を受けにくいオフィスビルやマンション、商業施設で、ひとつの物件に投資するよりもリスクが分散される仕組みになっています。REITは、法律上の規制により、収益の大部分を投資家へ還元しなければならないため、配当は継続的に安定しやすい傾向にあります。
合同会社匿名組合(GK-TK)
合同会社匿名組合(GK-TK)は、合同会社(GK)と匿名組合(TK)を組み合わせた投資スキームです。投資家と事業者の双方にメリットをもたらす仕組みとして、主に不動産投資や事業投資の分野で活用されています。
投資家(TK出資者)は、合同会社に匿名で出資できるため、出資者の情報を公開せずに投資を行えるのが特徴です。また、税務上のメリットがあるため、より多くの利益を得る可能性があります。
通常、法人が得た利益には法人税が課されますが、GK-TKスキームを活用すると、匿名組合契約を通じて利益を分配できるため、法人税の軽減が期待できます。そのため、海外の投資家やファンドが日本国内の不動産や事業に投資する際に、合同会社匿名組合(GK-TK)がよく用いられています。
レバレッジド・バイアウト(LBO)
レバレッジド・バイアウト(LBO)は、買収対象企業の資産を担保に資金調達を行い、企業を買収する手法です。買収資金の大部分は金融機関からの融資によって賄われるため、少ない自己資金で大規模な買収を実行できる点が特徴です。
このスキームでは、買収を目的として特別目的会社(SPC)を設立し、資金調達を行った後に企業の買収を実施するケースが多くなっています。買収対象企業のキャッシュフローを活用して買収資金を返済していくため、資金力が限られている企業でも戦略的なM&Aを実現しやすくなります。
特別目的会社(SPC)を設立するメリット

特別目的会社(SPC)は、特定の資産を保有する特性により、親会社に依存せず迅速に資金を確保できます。企業が保有する資産を特別目的会社(SPC)に移転することで、親会社の財務諸表から対象となる資産を分離できるため、会計上のメリットも享受できます。
また、法的に独立しているため、親会社が倒産したとしても資産を保護できるのも利点です。海外では、タックスヘイブン(租税回避地)を利用して設立するケースも多くあります。
資金調達を行いやすい
特別目的会社(SPC)を活用すると、通常の銀行融資に依存せず、証券市場を通じて資金調達できるため、資金調達の選択肢が広がります。また、プロジェクトごとに設立すると資金の流れが明確になるため、投資家の信頼を得やすいのもメリットです。特定の事業や資産に焦点を絞った資金調達が可能になり、効率的な財務戦略を構築できます。
資産のオフバランス化を行える
設立した特別目的会社(SPC)に市場リスクや資産価値変動のリスクが高い資産を移転することで、企業の財務諸表から切り離すことが可能です。これにより、ROA(総資産利益率)の向上が期待できるため、財務指標の健全化が実現します。
特に、不動産や設備投資が多い企業にとって、不要な固定資産の売却や負債を減らすバランスシートのスリム化は、経営の柔軟性を高めるための重要な手段です。また、リスク分散の面でも特別目的会社(SPC)設立が有利に働きます。事業ごとに設立することで、特定の資産に関するリスクを限定し、企業全体の財務安定性を向上させることが可能です。
本体企業の倒産隔離を行える
特別目的会社(SPC)を活用すると、本体企業が倒産した場合でも、保有する資産や事業は影響を受けにくくなり、逆に特別目的会社(SPC)が倒産した場合も同じ効果が期待できます。そのため、ステークホルダーに対して事業の継続性を保証しやすくなり、企業の信用力向上が期待できます。また、プロジェクトの独立性を確保できるため、金融機関や投資家からの評価も高まり、長期的な事業運営の安定化を図ることも可能です。
海外では設立国の法制度(タックスヘイブン等)を利用できる
特別目的会社(SPC)を海外に設立することで、税制上のメリットを享受できるケースがあります。特にタックスヘイブンと呼ばれる法人税率の低い地域では、投資や資産管理の効率化を図る目的で多くの企業が特別目的会社(SPC)を設立しています。
タックスヘイブンを活用し、税負担が軽減されることにより、資産運用の自由度を高めることが可能です。また、国際的な投資スキームを構築する際も、現地の法制度を活用することで柔軟な資金調達や事業展開を行えるようになります。
ただし、タックスヘイブンを利用する際は、一定のリスクを伴うことも理解しておく必要があります。各国の税務当局が厳しい監視を行っているため、不適切な節税スキームとみなされた場合には、課税リスクが生じかねません。
税制の適用範囲やコンプライアンスを十分に理解した上で、適切に活用することが重要です。タックスヘイブンに関する詳細は、以下の関連記事をご覧ください。
特別目的会社(SPC)のデメリット

特別目的会社(SPC)は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのでデメリットも存在します。特に、設立や運用にコストに関することや、悪用される可能性があることに対しては、十分注意しなければなりません。デメリットを正しく理解して、適切な管理を行うことが重要です。
運用コストがかかる
特別目的会社(SPC)を設立・維持するには、一定のコストが発生します。法人の設立時には、登録免許税や資本金の準備が必要になるほか、弁護士や会計士などの専門家に依頼する場合、報酬も考慮しなければなりません。
また、設立後も継続的な事務管理が求められるため、経理処理やコンプライアンス対応のための管理コストが増加します。特に、不動産証券化やM&Aに関連したSPCの場合、定期的な報告書の作成や監査を受ける必要があり、通常の法人運営と比較して負担が大きくなるケースがあります。
不正利用される恐れがある
特別目的会社(SPC)は、資産管理や投資スキームにおいて有効な手段となるものの、一部では不正な目的で利用されるケースがあります。例えば、租税回避や脱法行為のために設立される特別目的会社(SPC)は、国際的な税制規制の対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、資産の所在が不明瞭になりやすい特別目的会社(SPC)の仕組みを利用し、不正資金の隠蔽やマネーロンダリングに使われる事例も報告されています。このような背景から各国の法規制は強化される傾向にあり、適切な運用が求められています。
特別目的会社(SPC)の設立方法
特別目的会社(SPC)の設立には、主に「SPC法」と「会社法」に基づく2つの方法があります。
どちらの方法を選択するかは、目的や事業内容、資金調達の手段によって決まります。それぞれ手続きや要件が異なるため、正しく理解しておきましょう。
SPC法に基づく場合の設立方法
SPC法に基づいて設立する場合、以下の手順で行われるのが一般的です。
| ①資本金の準備 | SPCを設立するために10万円以上の資本金を用意する |
| ②登録免許税の支払い | 設立時に3万円の登録免許税を納付する |
| ③定款の作成と定款印紙代の支払い | 定款を作成し、公証役場で定款印紙代4万円を支払う |
| ④取締役・監査役の選任 | 会社の運営に必要な取締役や監査役を各1名以上選出する |
| ⑤資産流動化計画の作成 | 証券化や投資の目的に応じた資産流動化計画を策定し、関係機関に届け出を行う |
| ⑥業務開始の届出 | 設立後は関係当局へ業務開始の届け出を行い、適法に運営できる体制を整える |
SPC法に基づいて設立するケースは、特に不動産証券化や金融商品としての運用を目的とする際に適用されることが多く、厳格なルールのもとで設立・運営することが求められます。
会社法に基づく場合の設立方法
会社法に基づく場合は、一般的な法人設立の手続きを踏みます。
| ①定款の作成 | 取締役を1人以上選任し、定款を作成する |
| ②登記申請 | 法務局に対して登録免許税を支払い、会社設立の登記申請を行う |
| ③登記完了後の運営開始 | 法務局から登記が完了した通知を受けた後、特別目的会社(SPC)としての運営を開始する |
株式会社を設立する際の登録免許税は資本金額の0.7%ですが、15万円に満たない場合は15万円が課税されます。また、合同会社の場合も資本金額の0.7%を登録免許税として支払いますが、6万円に満たない場合の課税額は6万円です。
株式会社は定款印紙代として4万円が必要ですが、電子定款や合同会社の場合は不要です。会社法に基づく手続きは、比較的シンプルな特別目的会社(SPC)の設立に適しており、M&Aやファンド運営を目的に活用されるケースが多くなっています。
No.7191 登録免許税の税額表-会社の商業登記(主なもの) | 国税庁
特別目的会社(SPC)に関する相談は専門家まで
特別目的会社(SPC)は、資産管理や資金調達において非常に有効な手段ですが、その設立や運営には専門的な知識が求められます。設立方法や税務戦略を誤ると、想定外のコストが発生する可能性もあるため、事前に必要な知識を身に付けてから準備を進めましょう。
「税理士法人レガシィ」は、60年以上の歴史がある、相続・事業承継専門の税理士法人です。特別目的会社(SPC)の設立を検討されている場合は、専門家に相談しながら最適なスキームを構築することをおすすめします。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













