顧問税理士とは?依頼できる業務やメリット、相場を解説
Tweet税務管理や会計業務は法的な要件に基づく専門知識が必須であり、こうした業務領域をサポートしてくれる存在が「顧問税理士」です。税理士と顧問契約を結ぶことで、決算書の作成や記帳代行、税務調査への対応といった幅広い支援を受けられます。本記事では顧問税理士に依頼できる業務やメリット、顧問料の相場などを紹介します。
目次
顧問税理士とは
顧問税理士は、法人や個人事業主などの事業者と継続的な顧問契約を締結した税理士のことです。顧問とは、組織や個人に対して専門的なアドバイスやサポートを提供する役職を指します。顧問税理士は税務の専門家として、決算書の作成や税務調査への対応、税務相談といった業務の代行やアドバイスすることが主な役割です。
顧問税理士に依頼できる業務内容
税理士法第2条により、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務と定められています。顧問税理士に依頼できる代表的な業務として挙げられるのが以下の4つです。
- 日常的な税務管理
- 節税対策
- 税務書類の作成
- 税務調査の対応
日常的な税務管理
法人や個人事業主は、事業活動で発生する日々の取引を詳細に記録し、法令で定められた形式に従って帳簿を作成・保管しなくてはなりません。こうした税務管理や会計業務を支援するとともに、月次・年次の財務状況を把握し、経営判断に役立つ情報を提供することが顧問税理士の役割です。
具体的には記帳の指導や代行、仕訳内容の確認、会計ソフトへの入力支援、月次試算表の作成、資金繰りの助言、補助金・助成金の申請支援、消費税や法人税の申告業務など、税務と会計に関連する幅広い業務をサポートしてくれます。
節税対策
顧問税理士は、節税効果の高い経費処理や税制優遇制度の活用方法、損金として算入できる項目の助言など、税法に基づく節税対策を提案してくれます。たとえば4年落ちの中古車の法定耐用年数は2年ですが、定率法を選択した場合は1年での減価償却が可能です。そのため、4年落ちの中古車を期首に購入すれば、取得価額全額を当期の経費として計上できるため、より高い節税効果が期待できます。税理士と顧問契約を締結することで、こうした節税対策に関する指導や支援を受けられます。
税務書類の作成
税務書類とは、企業や個人事業主が税務の申告や手続きを行う際に作成・提出する書類の総称です。具体的には損益計算書や貸借対照表などの財務諸表、法人税申告書や消費税申告書、各種控除や特例の申請書類などが該当します。これらの税務書類は法令に基づいて厳格に作成する必要があり、要件を満たしていない場合はペナルティーの対象となる可能性があります。こうした税務書類の正確性を担保し、税務リスクを最小化することも税理士の代表的な業務です。
税務調査の対応
顧問税理士に依頼できる業務のひとつが税務調査の対応です。税務調査とは、国税局や税務署が事業者の申告内容や会計処理が適正かどうかを確認するために行うもので、 数年に一度実施される可能性があります。税務調査の対象となった事業者は、帳簿や契約書などの証憑資料を提示するとともに、調査官の質問に対して的確に答えなくてはなりません。顧問税理士は、調査前の準備段階から実際の立ち会い、必要な資料の整理や質疑応答への助言、調査結果に基づく修正申告への対応など、一連の対応を全面的にサポートしてくれます。
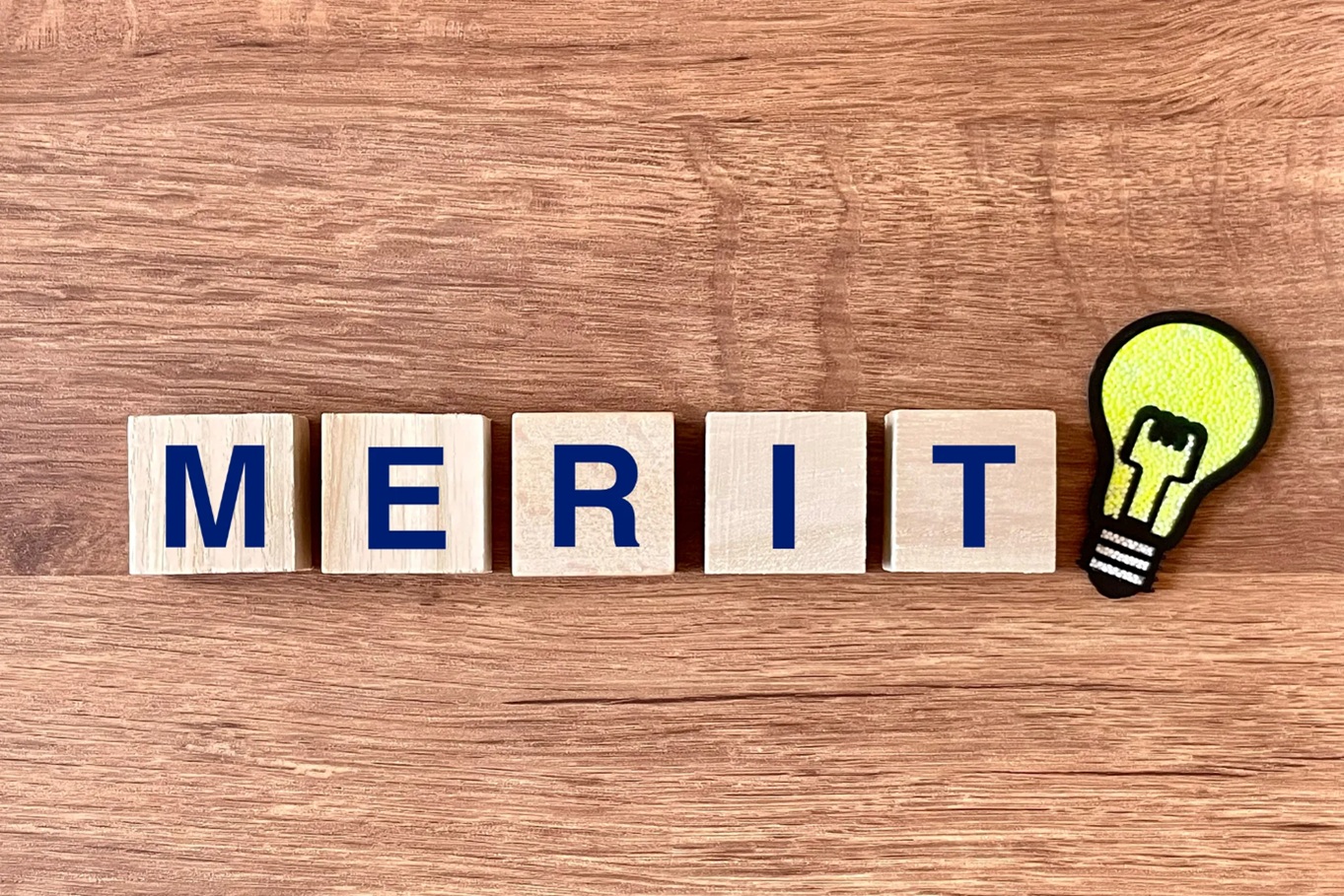
顧問税理士をつけるメリット
税理士と顧問契約を締結する代表的なメリットは以下の5つです。
- 税務管理から解放され本業に集中できる
- 効果的な節税対策を行える
- 申告を正確に行える
- 税務調査を安心して対応できる
- 経営の相談を行える
税務管理から解放され本業に集中できる
税務管理や会計業務は、事業を営む上で欠かせないものですが、その反面、専門的な知識や煩雑な手続きへの対応が求められます。こうした負担を軽減する手段として有効なのが税理士との顧問契約です。仕訳、記帳、月次報告、税務申告、納税スケジュールの管理など、税務会計に関わる実務を一任できるため、税法や会計基準の知識を常に更新する必要がなくなります。その結果、本業に専念しやすくなるという大きなメリットがあります。
効果的な節税対策を行える
税理士と顧問契約を結ぶことで、事業者の実情に即した節税対策を提案してくれる点もメリットのひとつです。所得税や法人税、消費税などの納税はキャッシュフローに大きく影響するため、合法的かつ計画的な節税対策が欠かせません。しかし税制は頻繁に改正され、その内容も専門的かつ複雑であるため、最適な節税策を見極めるのは容易ではありません。そうした中でも最新の税法や優遇税制を熟知した顧問税理士がいれば、将来の税負担を見据えた中長期的な視点で、最適なアドバイスを受けることができます。
申告を正確に行える
税務申告では税務会計に関する高度な専門知識と正確な計算、さらに法令にのっとった手続きが必要です。申告内容や手続きに不備があれば、修正申告や追徴課税などのペナルティーを受ける可能性があります。税務申告を顧問税理士に依頼すれば、複雑な会計処理や申告書の作成を代行してもらえるため、記入ミスや計算違いなどによる税務リスクを大幅に軽減できます。このように税務申告の正確性と信頼性を確保できる点も税理士と顧問契約を結ぶメリットのひとつです。
税務調査を安心して対応できる
税務調査では、税務署の調査官が事業者のオフィスや事務所を訪問し、事業者は質疑応答や証憑書類の提示を求められます。調査官の質問は専門的な内容が多く、経営者や経理担当者では対応しきれない場合が少なくありません。そのため、顧問税理士が税務調査に立ち会うことで、適切な資料を準備・提示できるとともに、知識不足に起因する誤解や不利な発言を防止できる可能性が高まります。また、不当な指摘や課税処分があった場合も、税理士が異議申し立てなどの法的手続きを含めた対応を支援してくれるため、安心して税務調査に対応できます。
経営の相談を行える
税理士のスキルや契約内容によっては、税務会計の枠を超えて資金調達や事業計画、M&Aなどの経営全般に関するアドバイスを受けられることも顧問契約のメリットです。たとえば月次決算の報告や定期的な面談の場を通じて、資金繰りの見通しや投資判断、融資申請に必要な財務書類の作成などについて専門的な支援を受けられます。さらに弁護士や司法書士など、顧問税理士がもつ専門家とのネットワークを活用することで、幅広い分野のサポートが期待できる点もメリットです。
顧問税理士をつけるデメリット
顧問契約の締結で生じるデメリットは固定費の増加です。税理士と顧問契約を結んだ場合、原則として月額または年額の顧問料が発生します。特に創業期の小規模事業者や資金に余裕のない個人事業主にとって、税理士報酬の負担は決して小さくありません。しかし税務と財務の正確性が確保され、税務署や金融機関からの信用向上につながることを考慮すれば、コスト以上のメリットを得られる可能性があります。
顧問税理士の報酬の相場
税理士の顧問料は、法人であれば「2〜5万円/月」、個人事業主の場合は「1〜3万円/月」が目安です。ただし、顧問税理士の報酬額は税理士事務所や契約内容によって異なり、年間売上高や従業員数、記帳代行の有無、面談の頻度などの要素でも変動します。一般的に事業規模が大きくなるほど仕訳の作業量が増加し、会計処理や月次報告などの負担も大きくなるため、それに応じて顧問料も高くなります。また、基本的に決算申告は別途で費用が発生し、その相場は「顧問料の4~6カ月分」が目安です。
■年間売上高による顧問税理士の報酬相場(月額)
| ~3,000万円 | 2万円~ |
| 3,000万~5,000万円 | 2万5,000円〜 |
| 5,000万~1億円 | 3万円〜 |
| 1億~3億円 | 3万5,000円〜 |
| 3億~5億円 | 4万円 |
| 5億~10億円 | 4万5,000円〜 |
| 10億円~ | 5万円〜 |
| ~1,000万円 | 1万円〜 |
| 1,000万~3,000万円 | 2万円〜 |
| 3,000万~5,000万円 | 2万5,000円〜 |
| 5,000万〜 | 3万円〜 |
※別途で決算申告費用や記帳代行料金などが発生する場合があります。
※金額はあくまでも目安であり、税理士事務所や契約内容によって費用は異なります。

顧問税理士と契約する際の注意点
税理士と顧問契約を結ぶ場合、以下に挙げる3つのポイントに注意する必要があります。
- 契約内容を確認する
- 税務申告以外の相談が可能かを確認する
- 信頼のおける税理士と契約をする
契約内容を確認する
税理士と顧問契約を締結する際は、サービスの適用範囲や料金体系の詳細を書面で確認しなくてはなりません。契約に関してトラブルが発生した場合、口頭のやり取りだけでは証拠能力が弱く、法的保護を受けられない可能性があります。顧問料はもちろん、記帳代行や決算書の作成費用、税務調査への対応費用、さらには顧問契約の期間や解約条件など、契約書の細部にまで目を通して内容と費用を確認することが大切です。
税務申告以外の相談が可能かを確認する
税理士と顧問契約を結ぶ前に、税務会計以外の分野にも対応できるかを確認することも重要なポイントです。例としては相続税対策や事業承継、M&A、業界特有の会計処理や税制など、複雑で専門的な相談に対応できるかを確認しましょう。事業者が直面する経営課題は税務管理や会計業務にとどまらないため、将来的な事業展開を見据え、多様なビジネスニーズに対応できるサポート体制があるかを事前に確かめておきましょう。
信頼のおける税理士と契約をする
顧問税理士は企業の機密情報や財務状況を長期的に共有するパートナーとなるため、信頼関係の構築が極めて重要です。税理士の実績や経験、専門分野を確認するのはもちろん、初回面談などの機会を通じて人柄や相性を確かめ、質問や相談に迅速かつ丁寧に回答してくれる人物であるかを見極める必要があります。信頼できる第三者の紹介や税理士紹介サービスの利用なども有効であり、可能であれば複数の候補から比較検討することが望ましいです。
相続・事業承継についてのお悩みはレガシィまで
税理士と顧問契約を結ぶことで、税務管理や会計業務に関連するさまざまな業務を専門家に一任でき、事業者は本業に集中できる環境を整備できます。日常的な記帳や申告業務、節税対策、税務調査への対応に加え、経営相談や資金繰りといった経営全般に関わるサポートを受けられるのは大きなメリットです。
税理士法人レガシィは、相続・事業承継専門の税理士法人として、顧問税理士の先生との協働が可能です。相続・事業承継のセカンドオピニオンとして顧問税理士以外の意見も聞きたいという方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













