株式保有特定会社とは?評価方法やメリット・デメリット、株特外しについて解説
Tweet株式保有特定会社とは、一定の条件を満たすと株式の評価が厳しくなる会社を指します。企業オーナーにとっては、株価評価の方法や課税額に直結するため、正しく理解することが重要です。本記事では、株式保有特定会社の定義や特徴、株価の評価方法、メリット・デメリットを整理したうえで、「株特外し」を詳しく解説します。
目次
株式保有特定会社とは?

株式保有特定会社とは、総資産に占める株式などの割合が高い会社を指し、相続税評価の場面で特別な扱いを受ける法人形態です。以下では、まず「定義」と「特徴」を整理して解説します。
定義
株式保有特定会社とは、会社が保有する総資産のうち、株式などの金融資産が50%を超える場合に該当する会社です。「特定株式等」には上場株式や非上場株式、外国株式、投資信託の受益権などが含まれ、評価時点での相続税評価額で判定されます。
相続税法上の特別な分類であり、非上場株式の評価方法に大きな影響を与えるため、事業承継や相続対策を考える経営者にとって重要なポイントです。以下は、株式保有特定会社を定義する際の計算式です。
株式などの価格の合計 ÷ 総資産価格 ≧ 50%
ただし、すべての会社がこの基準で判定されるわけではありません。例えば開業から3年未満の会社や、休業中・清算中の会社は、株式保有特定会社ではなく別区分で評価されます。理由としては、「事業の実態がまだ確立していない、あるいはすでに事業活動を停止している会社を一律に評価対象とすることが適切ではない」と考えられているためです。
特徴
株式保有特定会社の大きな特徴は、事業承継時の相続税や贈与税の課税額が高くなる可能性がある点です。なぜなら自社株の評価額がそのまま課税額に直結するためであり、保有資産の大半を株式が占めていると、評価額が上がりやすくなります。結果として、オーナーや後継者にとって想定以上の税負担が発生するリスクがあるため注意が必要です。
株式保有特定会社の評価にあたっては、一般的な会社と異なる特別なルールが設けられており、次の章で解説する「純資産価額方式」「S1+S2方式」などが適用されます。評価方法が課税額にどのように影響するのかを理解できれば、より具体的な相続対策をしやすくなります。
株式保有特定会社における株価の評価方法
評価の方法はいくつかあり、それぞれの算定基準や、適用シーンによって税額に大きな差が生じます。まずは、基本的な仕組みを理解するのが重要です。主な評価方法は以下の3つです。
- 純資産価額方式
- S1+S2方式
- 配当還元方式
それぞれの評価方法の仕組みや特徴を詳しく解説します。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社が保有するすべての資産を相続税評価額で評価し、そこから負債を差し引いて株価を算定する方法です。株式保有特定会社の評価では、原則として純資産価額方式が採用されます。
この方式では、帳簿に記載された簿価ではなく、不動産や有価証券などの実際の相続税評価額で算定する必要があります。そのため、市場価格の変動が評価額に影響する点が大きな特徴です。
会社の収益性や将来性といった事業活動の見通しは評価額に反映されにくいため、あくまで「現時点での資産価値」を正確に把握するのに適しています。相続や贈与の際は、評価が課税額に直結するため、保有資産の内容を常に意識することが重要です。
S1+S2方式
S1+S2方式は、株式保有特定会社に適用できる特例的な評価方法で、1株当たりの取得価額を算定する際に用いられます。評価の際は、会社の資産を以下のように区分します。
- S1(株式などの特定資産以外の資産 ):本業に直接必要となる資産
- S2(株式などの特定資産):上場株式や非上場株式、投資信託などの金融資産
それぞれを評価したうえで一定の計算式を使い、最終的に1株当たりの価額を算定します。
配当還元方式
配当還元方式とは、過去の配当金額を基準に株価を評価する方法です。株式保有特定会社に該当する場合でも、同族株主以外の株主等がその株式を取得したときは、特例としてこちらの評価方法の適用が可能です。
純資産価額方式やS1+S2方式では、資産の時価から評価するため、株価が高くなる傾向にあります。一方で、配当還元方式は「株式が生み出す収益(配当)」から計算されるため、一般的に評価額が低くなる傾向があります。
結果として、相続税や贈与税の課税額を抑える効果が期待できるため、相続税の負担を軽減したい場合に積極的に検討される方法です。
株式保有特定会社のメリット
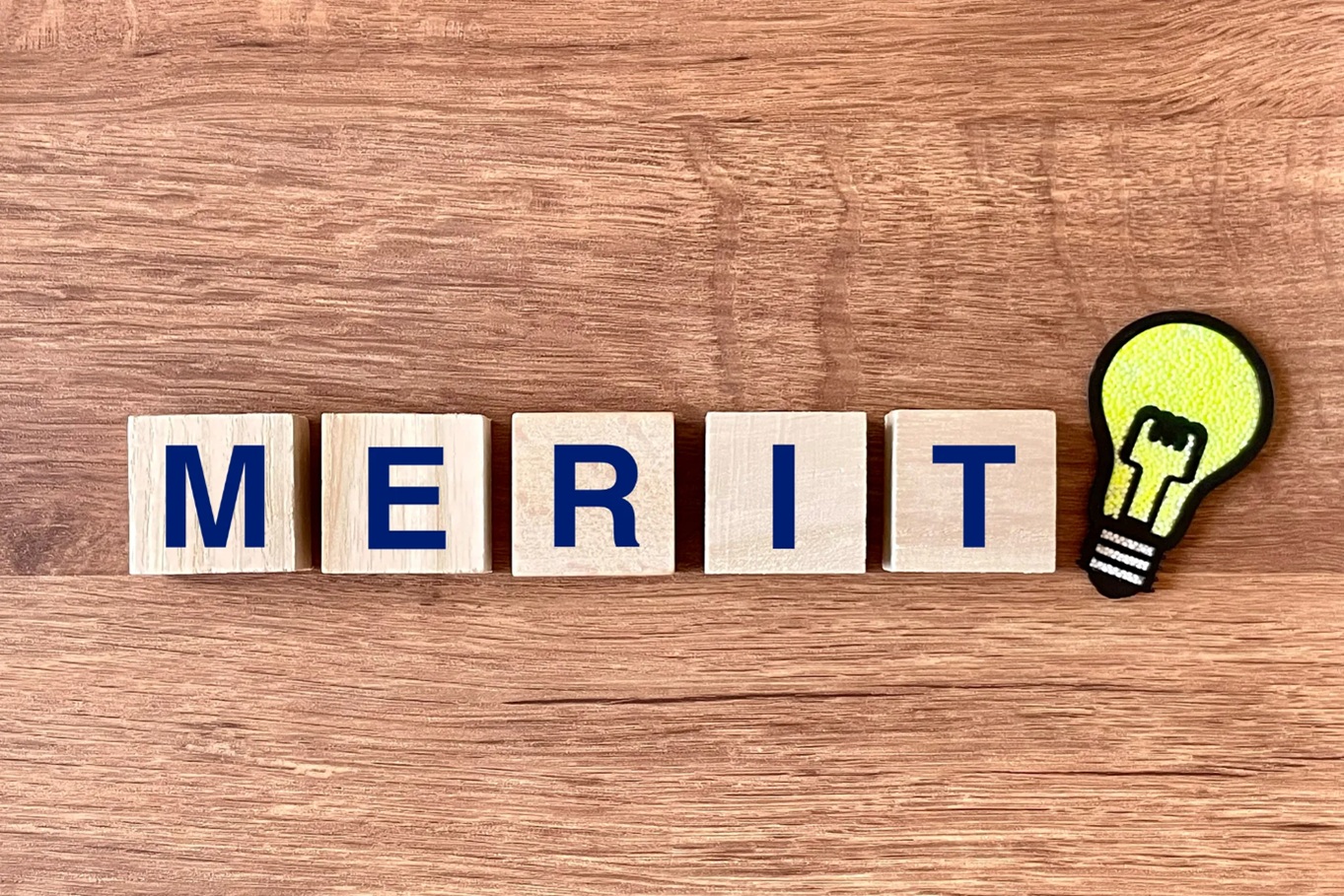
株式保有特定会社には、経営や資産管理の面でいくつかのメリットがあります。
- 経営の効率化を実現できる
- レピュテーションリスクを回避できる
- 節税対策・相続対策になる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
経営の効率化を実現できる
株式保有特定会社を活用すると、事業会社と資産管理会社の役割を分けられるため、経営資源を本業に集中させられます。また、事業リスクと資産運用リスクを切り離すため、一方の事業が不調に陥っても他方に影響が及びにくくなり、グループ全体のリスクを抑えられるのも大きなメリットです。さらに、M&Aや事業譲渡の際には、事業会社のみの売却が可能です。事業承継や組織再編の選択肢を広げられるため、柔軟な経営戦略を実現しやすくなります。
レピュテーションリスクを回避できる
株式保有特定会社を設立すれば資産管理と本業を切り分けられるため、企業全体の評判を守りやすくなります。例えば事業会社が投資活動を直接行っている場合、投資の失敗や不祥事が発生すると、その責任が本業の会社に直結するかもしれません。しかし資産管理会社を通じて投資を行えば、こうした影響が本業に及ぶのを防げます。
さらに企業が保有する株式・不動産といった資産の詳細が、外部から直接見えにくくなる点もメリットです。
財務状況に対する不必要な憶測や、風評被害によるブランドイメージの低下を防げます。結果として、経営の透明性を保ちつつ、不要なリスクから会社を守れます。
節税対策・相続対策になる
株式保有特定会社は原則として純資産価額方式で評価されるため、株価が高く算定されやすく、相続税の負担は大きくなりがちです。
一方で、事業会社の株式を資産管理会社などを通じて保有し、後述する株特外しを行えば、評価額を抑えて相続税対策に活用できる場合があります。
株式保有特定会社のデメリット

株式保有特定会社には多くのメリットがありますが、組織運営や税務上の負担が増える恐れがあるため、導入にあたっては慎重な判断が求められます。主なデメリットは以下の通りです。
- 組織構造が複雑化する
- 組織の運営コストが上がる
- 法規制が強化される
以下、それぞれのデメリットを詳しく解説します。
組織構造が複雑化する
株式保有特定会社を活用すると、事業会社と資産管理会社という2つの法人が並立します。経営の自由度や資産管理の柔軟性は高まる一方で、組織全体の構造が複雑になりやすい点は大きなデメリットです。
例えば事業会社と資産管理会社の間で適切に情報を共有できなければ、経営判断のスピードが落ちる恐れがあります。また、株式や資産の管理に関する意思決定が複数の会社をまたぐ形になるため、意思決定プロセスが長期化するリスクもあります。
さらに、各社の役員や従業員が自分の役割を十分に理解していなければ、業務の重複や責任の所在があいまいになるかもしれません。結果、無駄なコストや非効率な作業が発生し、経営全体のパフォーマンスを下げる恐れも考えられます。
組織の運営コストが上がる
株式保有特定会社を設立すると、事業会社に加えて資産管理会社も運営する必要があるため、必然的にコストが増加します。税務申告や決算処理は、それぞれの会社ごとに行わなければならず、顧問税理士や会計士、弁護士など専門家への依頼費用が重複します。
加えて、グループ全体の管理業務や内部統制、監査対応の負担も大きくなるのも大きな問題点です。財務諸表の作成や報告手続きが複雑化するほか、グループ内取引の整理やコンプライアンス対応にも追加のリソースが必要です。
株式保有特定会社を維持するには、設立コストだけでなく、毎年継続的に発生する運営コストが高くなる点をあらかじめ考慮しましょう。
法規制が強化される
株式保有特定会社は、節税や相続対策のために活用される一方で、過去には租税回避や脱税目的で設立されるケースも見られました。そのため、税務当局はこうした会社に対して特に厳格な監視を行う傾向があります。
また、相続税や法人税をめぐる制度改正の影響を強く受けやすいため、最新の税制や評価ルールを常に把握し、適切に対応することが重要です。対応を怠ると、想定外の課税やペナルティを課される恐れがあります。
株式保有特定会社ではなくする「株特外し」とは

「株特外し」とは、会社が株式保有特定会社に該当しないように資産構成を調整する行為です。前述のように、株式保有特定会社は総資産に占める株式などの割合が50%を超える場合に該当します。
そのため、株特外しを行う際には、割合を49%以下に引き下げます。自社株の評価方法や相続税の課税額に大きな影響を与えられるため、事業承継や資産管理を考えるうえで重要な手段です。
株特外しの主な方法
株特外しを実現するには、会社の資産構成を調整し、総資産に占める株式割合を50%未満にする必要があります。そのためには、株式を減らすか、株式以外の資産を増やすという2つの方向性があります。具体的な方法は、以下の通りです。
- 株式を売却する
- 現金や預金を増やす
- 不動産を購入する
- 事業用資産を増やす
以下、それぞれの方法を詳しく解説します。
株式を売却する
株特外しの方法は、株式の一部を売却し、資産全体に占める株式の割合を下げることです。売却によって得た現金を事業資金に充てたり、他の資産に再投資したりして、資産構成を見直します。
ただし、どの株式を売却するかは慎重に検討する必要があります。将来性や収益性、流動性といった観点から、会社の事業戦略に合った銘柄を選ぶのが重要です。安易に売却を進めると、長期的な収益基盤を失うリスクもあるため、専門家のアドバイスを受けながら計画的に進めましょう。
現金や預金を増やす
現金・預金を増加させるのも、株特外しを実現する方法のひとつです。具体的には、株主からの増資や銀行からの借入を行って資金を調達し、資産構成を調整します。
また、事業活動を通じて得た利益を内部留保として積み立てれば、純資産を増やしながら株式保有特定会社の要件を外れるようにコントロールできます。
さらに、現預金が増えると会社の流動性も高まり、新規事業への投資や不測のリスクへの備えとしても役立ちます。株特外しだけでなく、経営の安定性を高める点でも効果的な方法です。
不動産を購入する
株特外しの方法として、借入金を活用して不動産を購入する手段もあります。不動産を新たに取得すれば、会社の資産全体に占める株式等の割合を引き下げられ、株式保有特定会社の判定から外れる可能性が高まります。
不動産は、相続税評価額が取得価額より低く算定されるケースがほとんどです。そのため、会社の資産総額を増やしつつも、相続税の評価額を抑える効果が期待できます。資産構成の調整と相続対策を同時に進められる点が大きなメリットです。
事業用資産を増やす
事業用の不動産や設備を新たに購入し、資産全体に占める株式の割合を下げるのも、株特外しを行う方法です。他の方法と同じように資産構成を見直すと、株式保有特定会社の判定から外れる可能性が高まります。
不動産や設備は、取得価額と相続税評価額の間に差が出やすく、会社の資産総額を増やしながらも評価額を抑えられる場合があります。結果として、相続税対策としても有効に働くのが特徴です。
さらに事業用資産の増加は、会社の事業基盤を強化し、収益性の向上にもつながります。したがって、単なる株特外しの手段としてだけでなく、中長期的な経営戦略と組み合わせて検討することが重要です。
株特外しを行う際の注意点

株特外しは有効な相続・事業承継対策となり得ますが、実行にあたってはいくつかの注意点があります。
まずは、専門家との連携が必須である点です。税務リスクを避けるため、税理士やM&Aアドバイザーなどと協力し、最適な方法を選択しましょう。
また、無理な対策は、逆効果になるため注意が必要です。例えば、過度な資産移動や不自然な取引は事業活動に支障をきたすだけでなく、税務上の問題を引き起こす恐れがあります。
最後に、株特外しを行う際は、合理性の説明が必要です。税務当局が恣意的な株特外しと判断した場合、否認されるリスクがあるため、対策の目的や合理性を説明できることが必要です。
株式保有特定会社の株特外しを行う前に専門家までご相談ください
株式保有特定会社は、総資産に占める株式の割合が50%を超える場合に該当し、相続税評価において厳格な扱いを受ける会社です。自社が株式保有特定会社に該当しないよう回避する方法として「株特外し」があるものの、税務上のリスクもあります。
相続や事業承継において株式保有特定会社や株特外しへの対応に不安を感じている方は、相続専門の税理士法人レガシィへぜひご相談ください。レガシィは創業60年、相続専門としては30年以上の歴史を持ち、相続案件の実績は累計3.1万件を超えます。非上場株式の評価を含む複雑な相続にも、経験豊富な税理士が的確なアドバイスをいたします。安心して事業承継を進めるために、どうぞお気軽にご相談ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













