組織再編とは?メリット・M&Aとの違いをわかりやすく解説
Tweet企業の成長や経営課題の解決手段として注目される「組織再編」。合併や分割などの法的手続きを通じて企業体制を見直すことで、競争力の強化や事業承継対策など、多面的な効果が期待できます。本記事では、組織再編の基本的な仕組みやメリット、M&Aとの違いについて、わかりやすく解説します。
目次
組織再編とは
企業の成長や経営課題への対応を目的に、事業の再編や統合を行う「組織再編」。ここでは、その基本的な仕組みや種類、進め方についてわかりやすく解説します。
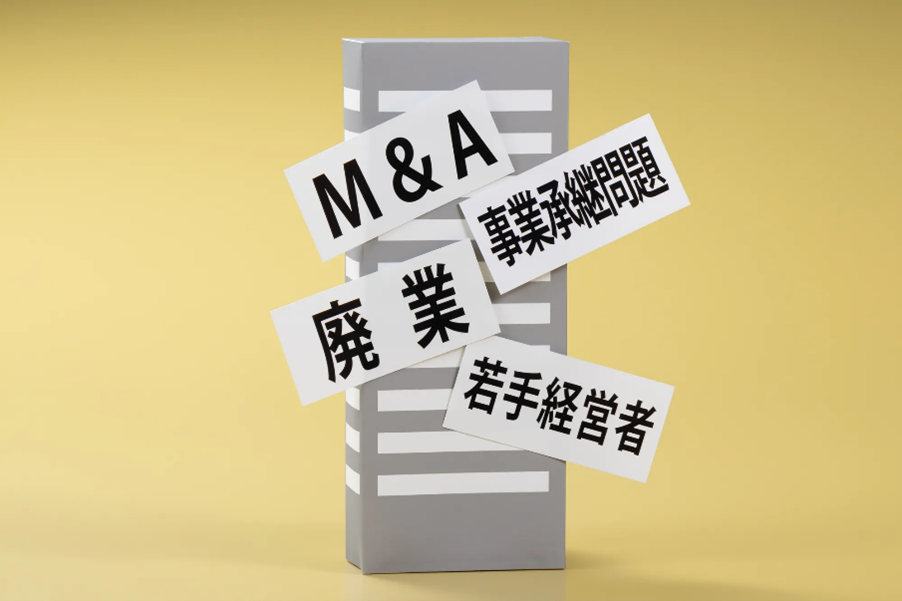
組織再編の概要
企業が合併や会社分割、株式交換など、さまざまな方法を使って組織の仕組みを根本から見直すことを「組織再編」といいます。
組織再編は、経営資源をより効果的に活用したり、事業経営を効率よく進めたり、市場の変化に柔軟に対応したりすることを目的として行われます。例えば、部門の統合や業務の流れを新しく設計し直すことなどが挙げられます。
組織再編は、会社法でも定められています。第743条では、「会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない」とあり、法的な根拠に基づいて計画的に再編を進める必要があります。
組織再編と組織改編の違い
企業の組織再編とは、会社法に基づいて合併や分割、株式交換などを行い、法人格や資本構造を大きく作り直す取り組みです。一方で、組織改編は、部署の新設や統合、役職の配置換えなど、社内の体制をより効率的にするための内部構造の見直しを指します。
例えば、部門をまとめて業務を効率化するのは組織改編にあたりますが、複数の企業が合併して新しい法人を作る場合は組織再編です。このように、両者の違いを正しく理解することは、経営判断のうえで非常に大切です。
組織再編とM&Aの違い
上述したとおり、「組織再編」とは、企業の内部構造を見直すことです。一方で、「M&A(合併・買収)」は、所有権の移転を伴う幅広い概念です。M&Aには、資本参加や外部資産の取得などを通じて、企業の成長を加速させる目的があります。
組織再編はM&Aの一部と考えられることもありますが、両者には目的や手続きに明確な違いがあるため、混同しないよう注意が必要です。例えば、組織再編は主に競争力の強化や経営の効率化を目指します。一方、M&Aはシナジー効果の創出や新しい市場への進出など、成長戦略の一環として行われます。
組織再編の目的

ここでは、組織再編が行われる主な目的について、経営上の視点から詳しく解説します。
事業の最適化による競争力強化
企業は不採算部門を切り離したり、収益性の高い分野に経営資源を集中させたりすることで、効率的で機動力のある事業体制を構築できます。また、法改正や市場環境の変化などの外部要因にも柔軟に対応しながら、組織全体の最適化を行えます。このような戦略的な再編は、企業が安定的かつ持続的に競争優位を確立するうえで重要な役割を果たします。
グループ全体の経営管理効率化
事業の成長にともないグループ企業が増加すると、管理業務の重複やコストの増大が課題となります。これを解消するための組織再編も重要な目的のひとつです。同一事業の集約や間接部門の統合などを行うことで、運営体制のスリム化と業務効率化が可能です。
また、持株会社の設置によってグループ全体の経営を一元的に管理し、資本構成の最適化やガバナンスの強化、KPIの導入などにより意思決定の迅速化を実現することも、組織再編によって達成される重要な成果のひとつです。これらの施策は、限られたリソースを重点事業へ集中させるための戦略的手段であり、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献します。
事業承継・後継者問題への対応
事業承継や後継者問題への対応は、組織再編の重要な目的のひとつです。会社分割や株式交換といった手法を用いることで、法人格を維持しながら事業や株式をスムーズに後継者へ引き継ぐことが可能です。
また、承継と同時に経営体制の見直しや資産整理を行えるため、再構築の機会としても有効です。後継者不在のケースでは、他企業への事業売却により売却益を得つつ、従業員の雇用維持にもつながります。例えば、株式取得に高額な資金が必要となる場合でも、会社分割などの再編スキームを活用すれば、株価のコントロールによって取得負担を軽減することが可能です。
組織再編の5つの手法・メリット
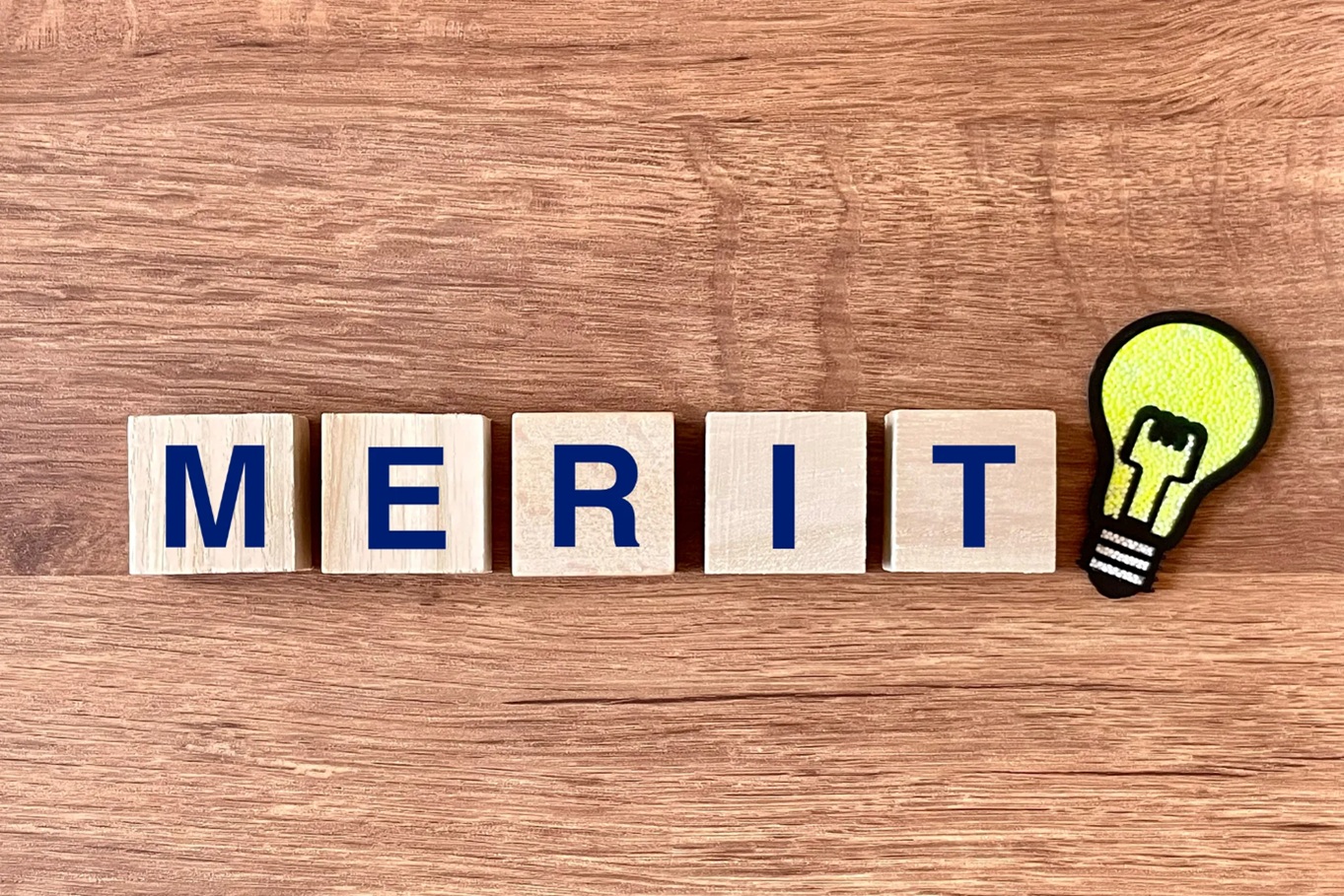
企業の持続的成長には、目的に応じた組織再編が不可欠です。ここでは代表的な5つの手法と、それぞれのメリットについて解説します。
合併
企業の合併とは、複数の企業が一体化してひとつの法人を形成する組織再編の手法です。手法は大きく分けて二つあります。ひとつは既存企業の一社が存続し他社を吸収する「吸収合併」、もうひとつは、関係する全企業が消滅し新たに法人を設立する「新設合併」です。新設合併は、手続きが複雑でコストもかかりますが、対等な関係での再編として前向きな印象を与えられる点が魅力です。
いずれの手法も、人的・物的資源の統合により競争力が高まり、経営管理の効率化が期待できます。例えば、重複する部門の整理やノウハウの共有を通じて、スピード感ある意思決定やコスト削減が実現しやすくなります。
会社分割
会社分割とは、企業が自社の事業を選択的に切り出し、ほかの企業へ承継させることで経営体制を再編する手法です。既存企業に事業を移す「吸収分割」と、新たに設立される法人に事業を継承させる「新設分割」の二つの形式があり、それぞれの目的や組織戦略によって使い分けられます。
会社分割は、不採算部門の切り離しや成長分野の独立によって収益性を高めることができるほか、承継側の企業にとっては、取得した事業を既存の体制に統合することで競争力の強化や業務効率の向上が期待できます。迅速な意思決定を促進し、グループ経営の柔軟性を高められる点も大きなメリットです。
株式交換
株式交換とは、企業が自社の株式を対価として他社の株式を取得し、完全な親子会社関係を構築する組織再編の手法です。グループ内での機動的な組織編成や管理体制の最適化を図る場面において、柔軟な統合手段として活用されます。株式交換は、自社株式と引き換えに他社の全株式を取得して完全子会社化を実現する組織再編手法で、経営の独立性が保たれるのが特徴です。また、少数株主の影響を排除しやすく、意思決定の迅速化や事業運営の一体化を促す効果が期待できます。
株式移転
株式移転とは、複数の既存企業が新設する持株会社の傘下に入り、完全な親子関係を構築する組織再編の手法です。買収側となる持株会社は、自社の株式を対価として既存企業の株式を取得し、各社を子会社化します。
株式交換と仕組みは類似していますが、親会社を新たに設立する点が異なります。ホールディングス化により、グループ全体の戦略を一本化でき、経営資源の集約や管理体制の効率化が図れるのが特徴です。例えば、子会社の法人格を維持しながら意思決定を迅速に行える体制を築くことで、競争力や組織の柔軟性を高めることが可能になります。
株式交付
株式交付は、自社の株式を対価として他社の株式を取得し、過半数の持分を獲得することで子会社化を図る新しい組織再編手法です。柔軟な支配体制が構築でき、取引先や少数株主との摩擦も抑えられるのが特徴です。
会社法改正により2021年に導入されたこの制度では、従来の株式交換よりも税制優遇の適用条件が緩やかで、子会社の法人格と経営の独立性を保ちつつ、企業グループ全体の効率的な戦略展開を可能にする点でも注目されています。
組織再編のポイント

組織再編を成功させるには、法的手続きや社内調整など、押さえるべき重要なポイントがあります。以下では、実施時に特に注意すべき点を紹介します。
従業員とのコミュニケーション
組織再編に伴って多くの人が関与するため、価値観や働き方の違いから摩擦が生じやすくなります。特に企業文化が異なる場合は、従業員との丁寧なコミュニケーションが不可欠です。改革の目的や意義を明確に共有し、研修の実施や社内報の活用、相談窓口の設置などを通じて従業員の理解と安心感を得ることが求められます。
例えば、現場リーダーが率先して前向きな雰囲気づくりを行い、評価制度の整備によって改革の方向性を定着させると効果的です。信頼関係が築かれないまま再編を進めると、生産性の低下や離職リスク、外部ステークホルダーとの関係悪化につながる恐れがあるため、継続的な情報提供と意識醸成が重要です。
組織再編税制の活用
組織再編を進める際には、不要な税負担の回避や資金活用の最適化も重要です。
例えば、組織再編には人件費やシステム改修費をはじめとする多額のコストが発生するため、事前の費用対効果分析と計画的な予算立案が欠かせません。特に退職金支払いや新体制への移行に伴う研修・教育費など、見落とされがちな間接費用にも注意が必要です。
組織再編税制を活用することで、企業の成長戦略を維持しつつ財務的な柔軟性を確保する道が開かれます。例えば、譲渡損益が発生する場合は法人税等の課税対象となりますが、組織再編税制を活用して一定の条件を満たす「適格組織再編」として組織再編を実施すれば、資産の移転が簿価で認識されるため、課税の繰り延べが可能です。
資金活用の最適化をしながら組織再編を計画的に進めるには、法務・税務の専門家に相談しながら、手続きや制度適用の判断を委ね、迅速・的確に処理を進めていくことが求められます。
組織再編には様々な手法がある!最適な選択のために専門家に相談しよう
組織再編には、合併・分割・株式交換など多様な手法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。事業承継や経営効率化を目的とした場合でも、税制面を含めて最適なスキーム選定には専門的判断が求められます。最適な再編スキームを選択するためにも、「事業承継スタートパック」などの実務支援サービスの活用が有効です。
組織再編に関してご不安があれば、相続専門の税理士法人レガシィへぜひご相談ください。60年以上の歴史と累計3万件を超える相続案件の実績をもとに、的確なアドバイスを提供いたします。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













