自社株の評価方法は? 評価額を下げる方法をわかりやすく解説
Tweet経営者にとって、自社株を評価することには大きな意味があります。自社株の評価は満足のいく事業承継や株式譲渡を行うために、また、相続税や贈与税を抑えるためにも重要です。本記事では、経営者層に向けて、自社株の評価方法、簡易計算方法、評価を行う目的、評価額を下げる大切さ、評価額を下げる方法などを解説します。
目次
自社株(非上場株式)の評価方法とは
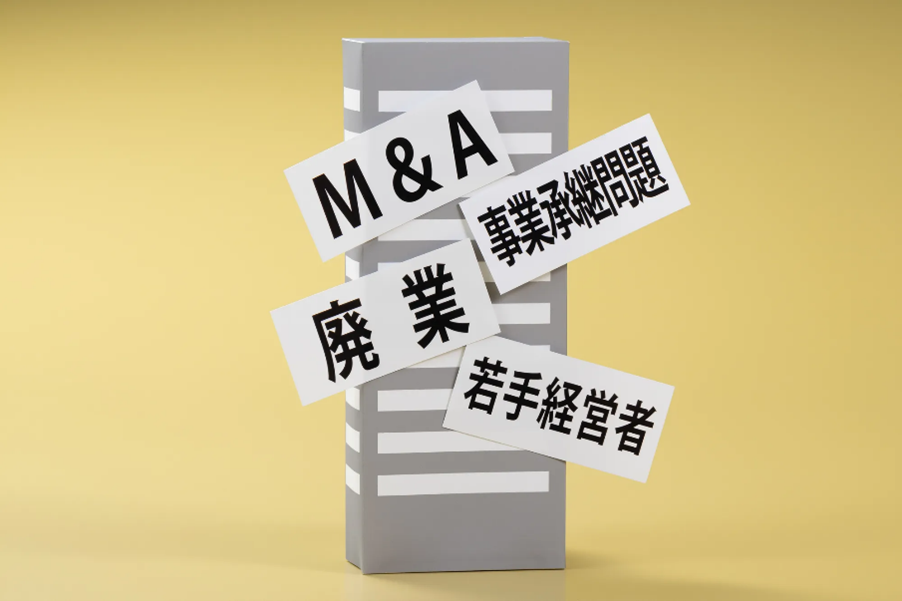
自社株評価とは、企業の株式価値を国税庁の定めた基準に基づいて算定することをいいます。上場企業の株式の場合、証券取引所での市場価格が存在しますが、非上場企業の株式には市場価格が存在しません。そのため、客観的に株式価値を評価するには、国税庁が作成する「財産評価基本通達」に則った計算が必要です。
自社株評価と企業価値評価は異なる
「自社株評価」と似たような言葉に、「企業価値評価」があります。両者は会社の価値を評価するという意味では共通していますが、評価の目的や評価方法が全く異なります。
一般的に、自社株評価は相続税や贈与税などの税務申告のために行われる評価です。相続税や贈与税は、財産の価値に応じて課税されるため、自社株の価値を評価して税額を算定しなければなりません。自社株評価は、自社株の買い取りや事業承継の際、「自社株をいくらで譲渡するか」を決めるために必要とされます。評価は、国税庁によって決められた基準を用いて行います。
一方、企業価値評価はM&A、資金調達、経営判断などの経済的価値を客観的に把握するために行われる評価です。第三者から見て適正とされる企業の価値を査定するために実施されます。自社株評価とは異なり、企業価値評価には決められた評価方法がありません。代表的な評価方法にはDCF法、マルチプル法、年買法などがあり、自社に合った評価方法を選べます。
自社株の3つの評価方法
自社株の評価方法には、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式の3種類があります。それぞれどのような方法でどのような場合に用いられるのか、解説します。
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、事業内容が類似している上場企業の株価や財務指標をベースに株式価値を評価する方法です。類似業種の配当金額・利益金額・純資産価額と比較し、非上場株式の価値を算定します。計算に必要となる類似業種の株価や配当・利益・純資産額などは国税庁によって定められています。
類似業種比準方式は、原則として会社の支配権を有する同族株主等が株式を取得する場合に使用します。また、従業員数が70名以上の大規模な会社の評価に用いられるのが特徴です。
ただし、会社の規模に関係なく、「特定会社」に該当する場合、類似業種比準方式ではなく純資産価額方式を使用するのが原則です。例えば、土地保有特定会社(相続税評価額のうち土地の占める割合が高い会社)や開業から3年が経過していない会社、比準要素数0の会社(直前期末における配当金額、利益金額、純資産価額のいずれもが0の会社)などは類似業種比準方式を使用できません。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社の資産と負債を時価で評価し、資産から負債を差し引いた「純資産」をもとに株式価値を評価する方法です。仮に会社が解散した場合に、株主に分配される財産価値を、相続税評価額をもとに評価します。
純資産価額方式は、利益ではなく財産に着目した評価方法であるため、評価額は資産の多い会社ほど高まる傾向があります。同族株主等が株式を取得する場合に、主に小規模の会社の評価に用いられます。中規模の会社の評価には、類似業種比準方式と純資産価額方式をミックスした併用方式が用いられるのが一般的です。
配当還元方式
配当還元方式とは、過去の配当金をもとに株式価値を評価する方法です。株式の所有によって受け取った過去2年間の配当金額を平均し、10%の利率で還元し、元本の株式価額を評価します。
類似業種比準方式や純資産価額方式とは異なり、配当還元方式は同族株主等に該当しない少数株主が株式を取得した場合に用いられる方法です。少数株主は会社の経営に与える影響が小さく、基本的に配当金を目的として株式を保有しているため、配当金を基準としたこの評価方法を使用します。支配権のない株主の立場を考慮し、評価額は低くなるのが一般的です。
自社株の評価の簡易計算方法

自社株の評価は、株主の判定(同族か否か)、会社規模の判定(規模はどれくらいか)、特定会社の該当判定(一般的な会社と業態が異なるかどうか)を経て、適切な評価方法を決定します。評価方法ごとに決められた計算式があるものの複雑であるため、正確に評価するには、国税庁の定める「財産評価基本通達」に基づいた計算と、専門家の関与が不可欠です。
ここでは簡易計算方法として、他の評価方法に比べて計算しやすい純資産価額方式を取り上げます。「資産-負債=純資産」であるため、純資産価額方式の計算式は
「(総資産評価額-総負債評価額-評価差額に対する法人税等相当額)÷発行済株式数」
となります。ただし、これはあくまで簡易計算であり、税務評価とは異なるため、実際の相続・贈与時には使えません。
自社株評価を行う目的
自社株評価は、相続時の財産評価、自社株の買い取り、円滑な事業承継を行うために不可欠です。それぞれについて解説します。
相続時の財産評価
事業承継の際、経営者の資産状況を把握するために、自社株の評価額が必要です。自社株の評価額がわからないと、相続税額の試算や遺産分割協議ができません。株式を相続すると財産の価値に応じて相続税が発生し、後継者には納税の義務が課されます。非上場企業は経営者が株式を保有しているケースが多く、業績が好調な会社は利益や純資産が高く、自社株の評価額が高くなりやすいです。相続税は財産の価値が高いほど高額になるため、相続税が発生した際に資金が足りず納税できないという状況に陥るリスクを防ぐためにも、生前に自社株評価をして対策することが重要です。
自社株の買い取り
自社株評価は、会社が自社株を買い戻して金庫株(自己株式)とする際、公平な価格を算定するためにも必要とされます。相続人や少数株主から株式を買い取る際に、納得感のある価格を提示することは、今後良好な関係を維持するためにも重要です。また、評価額がわからないと、買取資金の有無を判断できません。このように自社株の買い取りの際にも、自社株評価による正確な評価額の算出が求められます。
円滑な事業承継
円滑な事業承継を実現するために、自社株評価が不可欠です。評価額が曖昧では経営者の資産状況の把握が難しく、事業承継がスムーズに進みません。相続税額の試算や遺産分割協議で問題が生じる可能性もあります。自社株評価を行い、正確な評価額を提示することは、税務以外に経営上の価値としても重要です。自社株の評価が高いと後継者の負担になる可能性があるため、資産や負債の見直しを視野に入れ、自社株評価の準備を早めに、そして定期的にしておくことが大切です。
自社株の評価額を下げることが重要な理由
自社株の評価額は高ければ良いわけではありません。自社株を相続もしくは生前贈与した場合、相続税評価額が高いほど相続税額や贈与税額も高くなってしまいます。後継者が必ずしも納税資金を準備しているとは限らないため、想定外の税額だと払えないケースもあり得ます。後継者の税負担を軽くするためには、自社株の評価額を下げることが重要となります。相続税や贈与税を軽減できれば、円滑な事業承継にもつながります。自社株は、創業時からの利益の積み重ね、土地価格の高騰、保有資産の高さなどによって評価額が上がってしまうケースが少なくありません。自社株の相続・贈与においては、評価額を下げる「自社株対策」が必須です。
自社株の評価を下げるための4つの方法

自社株の評価は、役員の報酬を引き上げたり役員に退職金を支給したりすることによって、下げられます。自社株の評価を下げるのに有効な方法を4つ紹介します。
役員報酬の引き上げ
役員報酬は法人税の所得金額を計算する上で費用として認められるため、定款に基づいて多く支給すればその分会社の利益は圧縮されます。結果的に純資産が減り、自社株評価の低下につながります。
ただし、事業年度途中の増額や高額すぎる役員報酬は損金算入が認められません。事前に計画的に対応し、報酬はあくまでも適正な範囲内で設定しましょう。役員個人の給与所得が増えることによって、所得税や社会保険料が増える点にも注意が必要です。
役員退職金の支給
先代の経営者や役員が退職するタイミングで、役員退職金を支給するのも方法のひとつです。役員退職金には大きな所得控除が認められており、役員退職金の支給時は自社株の株価が大幅に下がるタイミングでもあります。事業承継のタイミングで役員退職金を支給して損金計上すれば、会社の利益が圧縮されて純資産が減り、自社株評価を下げられます。
ただし、役員退職金の額が会社の規模や業績に見合わない場合、損金不算入とみなされたり税務調査のリスクがあったりするため注意が必要です。役員報酬の引き上げと併せて適正額を専門家に相談しましょう。
株式配当金を低く設定
自社株の配当金を低く設定して、配当還元方式による株式評価を下げる方法も効果的です。配当還元方式は配当金額に基づいて株式を評価するため、配当金が少ないと評価額も低くなる傾向があります。記念配当や特別配当は株式評価の対象外であるため、普段の配当金を低く設定しておき、記念配当や特別配当を利用すれば、配当金の総額を変更せずに済みます。配当率は株主総会で引き下げることが可能であり、オーナー企業の場合は容易に変更できます。
この方法は、株式配当金が高い場合にはメリットがありますが、低い場合はメリットが見込めないため、自社の状況に応じて行いましょう。
組織再編の活用
合併・会社分割・株式交換・株式移転など組織再編を活用して、自社株評価を下げることも可能です。会社分割によって資産や負債を分散させたり、株式移転によって持株比率を変えたりすることで、自社株の価値は相対的に低く算定されやすくなります。
株式交換や株式移転に関しては基本的に株主が移動するだけであるため、口座変更などは必要なく、影響が少ないのがメリットです。なお、組織再編による株価対策は、「租税回避行為」と認定され、課税対象となるリスクがあるため、税理士などの専門家に相談した上で検討しましょう。
自社株評価の際の注意点

自社株を評価する際には、以下の3つに注意しましょう。
- 類似業種比準価額が適用できない場合がある
- 大会社の場合には類似業種比準価額のみで評価できる場合がある
- 配当還元方式は無配当でも0円にならない
開業から3年が経過していない会社、比準要素数0の会社、債務超過のある会社、土地などの比率が高い会社、同族関係者以外の株主が多い会社などは、類似業種比準価額を適用できません。適用できない場合は、株価が高く出やすい純資産価額や純資産額や特例の評価方式によって算出する必要があります。
規模の大きな会社は、原則として類似業種比準価額方式を使用しますが、場合によっては類似業種比準価額が適用されず、純資産価額方式になるケースがあります。一般的に、純資産価額方式よりも類似業種比準価額方式の方が評価額を抑えられるため注意しましょう。中小規模の会社は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用しますが、純資産価額方式のみの評価額の方が低い場合はその評価額を採用できます。
配当還元方式では、配当を行っていない場合でも評価額は発生します。無配当の場合は1株当たりの平均配当金を2円50銭に設定し、評価額を算出します。
自社株の評価は複雑な点が多いため、相続や事業承継などに精通した専門家に依頼するのがおすすめです。
自社株の適切な評価方法は、専門家に相談しよう
自社株評価には複雑な点が多く、自社で行うのは難易度が高いです。相続専門の「税理士法人レガシィ」に相談いただければ、的確なアドバイスはもちろん、株式の評価額の算出にもしっかりと対応いたします。
税理士法人レガシィには、60年以上の運営実績・累計2万件以上の相続税申告実績数があり、経験豊富な税理士が多数在籍しております。お気軽にご相談ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













