事業承継に強い税理士の探し方|依頼できることや報酬の相場も解説
Tweet近年、経営者の高齢化や後継者不足を背景に、事業承継の準備を急ぐ企業が増えています。一方で、複雑な手続きを前にして税理士への依頼を迷う経営者も少なくありません。本記事では、税理士に依頼できる具体的な支援内容をはじめ、依頼によって得られるメリット、報酬の相場、信頼できる税理士の見つけ方まで、わかりやすく解説します。
目次
事業承継で税理士に依頼できること

事業承継において税理士が担う役割は多岐にわたります。主に依頼できる業務は次のとおりです。
- 承継方法や実施時期に関する助言
- 承継に必要な資金調達方法の助言
- 自社株評価の算出とその根拠の説明
- 株式の分散を防ぐための対策提案
- 贈与税や相続税に関する制度活用の支援
事業承継の方法に関するアドバイス
事業承継の方法は、親族内承継や親族外承継、M&Aなど複数あり、企業の状況や後継者の有無によって適切な選択肢は異なります。税理士は、事業の現状や後継者の意向を踏まえ、状況に合った最適な承継方法を提案可能です。例えば親族内承継では、資産の移転に伴う相続税や贈与税の影響を考慮する必要があり、承継時期や手法の選定のサポートが可能です。
親族外承継では、役員や従業員への承継に関する契約や資金調達の課題にも対応し、実行可能性の高い計画づくりに貢献できます。また、M&Aによる第三者承継を検討する際は、株式評価や税務上の取り扱いについて専門的なアドバイスが求められるため、税理士の知見が重要です。
資金調達の支援
事業承継を進めるうえで、後継者への株式移転や相続税の納税などに必要な資金をどのように確保するかは重要な課題です。その点税理士は、承継に必要な資金の見積もりや、実現可能な資金計画の策定の面でもサポートできます。
資金調達の手段は、日本政策金融公庫などによる制度融資や、事業承継に関連する補助金の活用があり、それぞれの制度の特徴や申請要件についても適切なアドバイスが可能です。特に補助金の活用には、タイミングや書類の整備が求められるため、専門家の支援が有効です。税理士によっては、金融機関との面談に同席するなど、融資交渉の場面で支援を行う場合もあります。
自社株の評価計算
事業承継においては、自社株の適正な評価額の把握が重要です。株式の評価額は相続税や贈与税の課税額に直接影響するため、税務上のリスクを軽減するには正確に算出しなければなりません。特に非上場企業の場合、株価が市場で明示されていないため、専門的な知識を持つ税理士による評価が助けとなります。
評価には類似業種比準価額方式や純資産価額方式などがあり、企業の現状に応じた方法の選択が重要です。税理士に依頼すると、評価の根拠を整理したうえで税務署への説明にも対応できる水準の計算ができるようになります。申告手続きや税務調査への備えとしても有効です。
株式分散対策の助言
株式の分散は、事業承継において経営権の安定を損なう要因となるため、早期の対策が欠かせません。税理士は、後継者に株式を集約するための具体的な方法について助言を行います。例えば、複数の相続人に株式が分散するリスクを踏まえて事前に贈与の計画を立てると、スムーズな承継を実現しやすくなります。必要に応じて、持株会社化や自己株式取得株式の一部を会社に移す方法 や、他の相続人に対する代償措置の検討も可能です。
贈与・相続税対策のアドバイス
事業承継では、贈与税や相続税の負担が経営の継続に大きな影響を及ぼすため、税理士による的確な対策が不可欠です。税理士は事業や資産の状況に応じて節税案を提案し、計画的に承継を進めるための支援を行います。
対策としては「生前贈与」の活用や、一定の要件を満たすことで贈与税・相続税の納税が猶予される「事業承継税制」の利用が挙げられます。税理士はこれらの制度の適用条件や手続きについて適切な助言が可能です。現状2026年3月31日までに計画の提出、2027年12月31日までに贈与・相続することが要件に含まれます。
事業承継に強い税理士に依頼するメリット
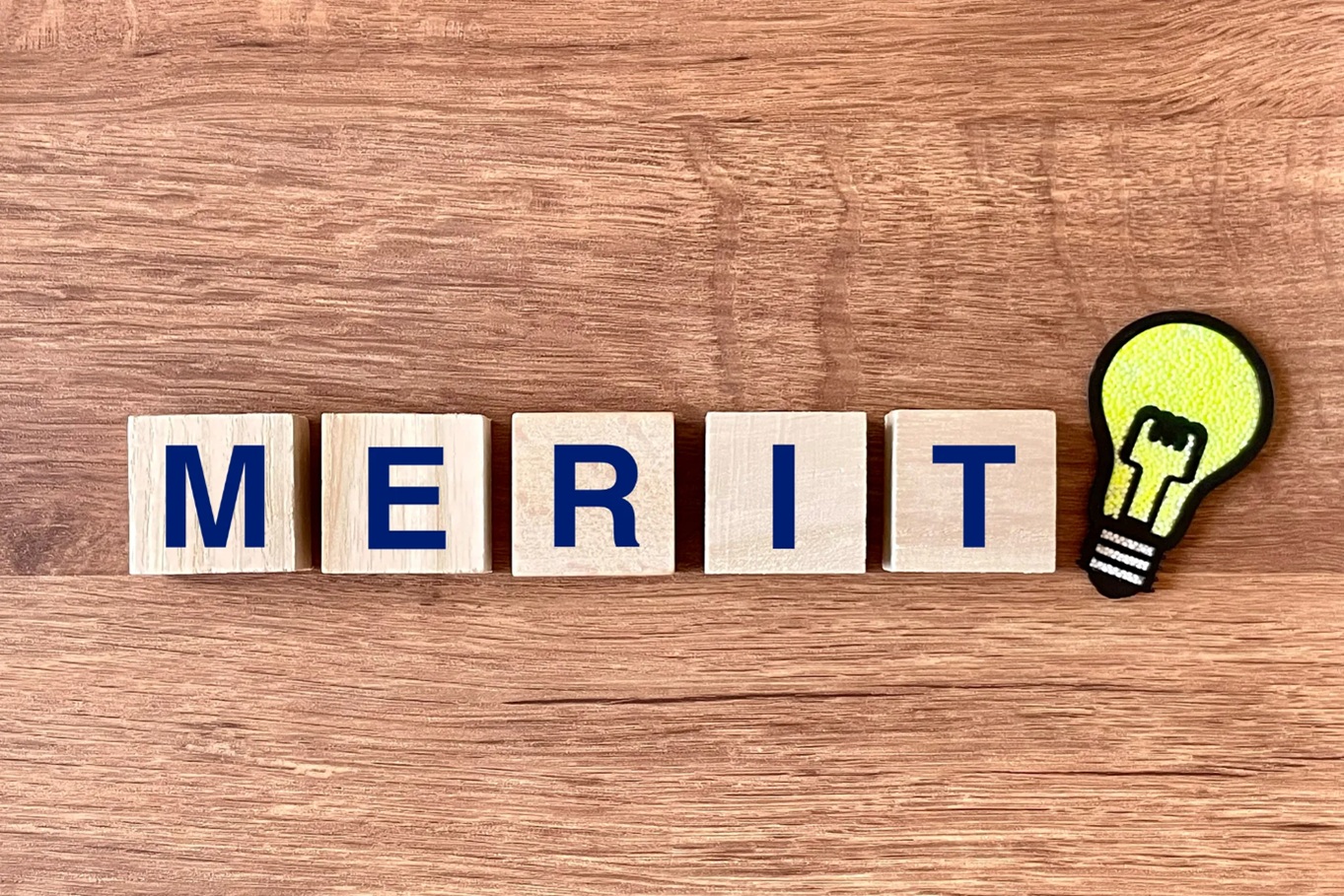
事業承継に精通した税理士に依頼すると、主に以下のメリットが得られます。
- 節税を意識した事業承継の提案が受けられる
- M&Aなどの多様な手法による支援を受けられる
- 他士業との連携による一貫したサポート体制を活用できる
税理士は経営状況や資産構成に応じた柔軟な提案が可能であり、計画的な承継を進めやすくなります。
節税などを意識した事業承継を行える
事業承継では、贈与税や相続税の負担が大きくなる可能性があるため、税理士による節税対策が重要です。税理士は、税制の仕組みや特例制度を正確に理解しており、企業の状況に応じた適切な対策を提案します。例えば、生前贈与を活用したり、事業承継税制の適用を受けたりすれば、税負担を抑えながら承継できるようになります。これらの制度は条件や手続きが複雑なため、専門家の助言を受けながら進めることが効果的です。
M&Aといった他の手法での支援も受けられる
事業承継は親族内への引き継ぎだけでなく、M&Aによる第三者承継という選択肢も注目されています。この場合、M&Aに関する専門知識と実務経験を持つ税理士に相談することで、税務面をはじめとする総合的な支援を受けられます。
税理士の中には、企業価値の算定(バリュエーション)や税務デューデリジェンスなど、M&Aの各ステップに対応できる専門家もいます。さらに、M&Aの相手企業を探す段階では、税理士が業界ネットワークや提携する仲介会社を通じて、候補企業の紹介や交渉支援を行うケースもあります。
税理士の持つ士業ネットワークを活用できる
多くの税理士は、弁護士や司法書士など他士業と連携したネットワークを保有しており、事業承継に必要な多様な手続きをワンストップで相談できる体制を整えています。例えば、相続や贈与に伴う法的手続きや不動産登記など、税理士だけでは対応が難しい領域でも、適切な専門家を紹介してもらえれば経営者の負担を軽減できます。
こうしたネットワークを活用することで、税務・法務・登記といった各分野の手続きを効率よく進められ、事業承継全体がスムーズに進行します。また、相談窓口が一本化されることで、手続きの流れを把握しやすくなり、対応の抜け漏れや手戻りのリスクも抑えられます。
事業承継における税理士の報酬相場
事業承継を税理士に依頼する場合の報酬は、業務内容の複雑さや事業の規模によって大きく異なります。例えば、相続税の試算や申告書の作成など、比較的単純な手続きにとどまるケースであれば、報酬は数十万円程度が一般的です。
一方で、株式評価や事業承継税制の活用、さらにはM&Aを含む総合的な支援を依頼する場合には、100万円以上の報酬が発生することもあります。これらの業務は、税務に加えて法律や財務、経営全体の知識が求められるため、高度な専門性に見合った費用が必要となるのが一般的です。また、事業承継は一度きりの手続きではなく、数年にわたって支援を受ける長期的なプロジェクトになることもあるため、顧問契約として継続報酬が発生するケースもあります。
なお、税理士報酬には公的な基準がないため、料金は各事務所が自由に設定しています。そのため、依頼前に料金体系や支援内容の範囲を確認することが重要です。複数の税理士から見積もりを取り、業務内容と費用のバランスを比較検討することで、納得のいく形で事業承継を進められます。
事業承継に強い税理士の探し方
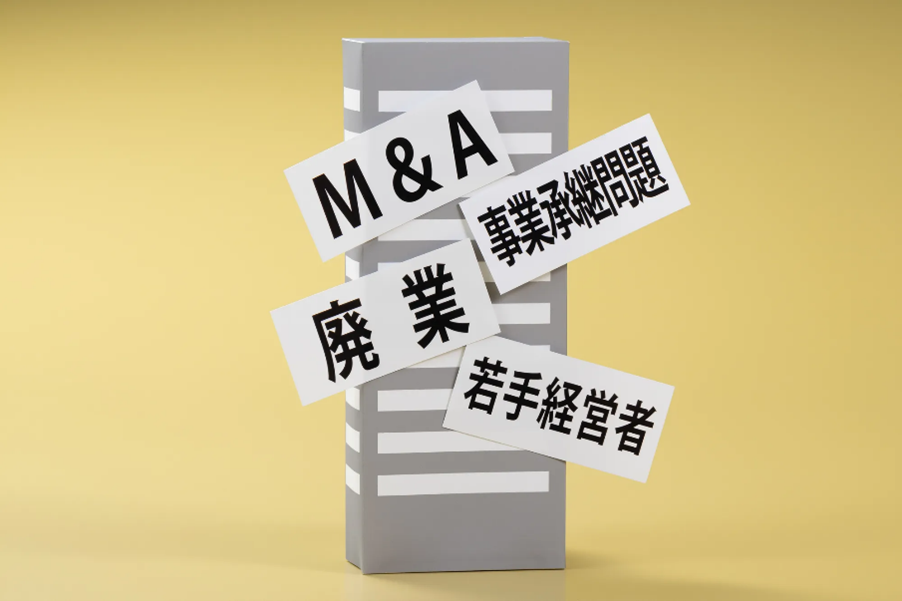
事業承継に強い税理士を選ぶ際は、税務知識だけでなく、事業承継の実績やM&Aへの対応力や他士業との連携体制の有無なども重要な判断材料です。
- 事業承継やM&Aに関する支援実績がある
- コンサルティング業務に対応している
- 弁護士や司法書士など他士業とのネットワークがある
こうした視点を踏まえて選ぶことで、自社に合った税理士から、より実践的で総合的な支援を受けやすくなります。
事業承継・M&Aの実績・スキルを確認する
事業承継やM&Aに関する過去の対応事例が豊富な税理士であれば、複雑な手続きにも柔軟に対応できる可能性が高くなります。まずは、税理士事務所のウェブサイトなどで、事業承継やM&Aに関する支援実績や顧客の声が掲載されているかを確認しましょう。
具体的な事例があれば、専門性や経験の深さを判断する材料になります。加えて、セミナーや無料相談会などに参加し、実際に税理士と対話することで、説明のわかりやすさや相談のしやすさを実感として確かめられます。
事業承継・M&Aのコンサルティングを行っている
税理士を選ぶ際は、税務申告だけでなく、事業承継の計画策定から実行まで一貫して対応できるかが重要なポイントです。企業の現状や将来像を踏まえた計画立案には、総合的な視点と専門的な知識が求められます。現状分析や課題の洗い出し、承継手法の選定、財務・税務のシミュレーションなど、きめ細やかなコンサルティングが提供されているかも見極めのポイントです。
さらに、提案内容が実行可能であるか、具体的な手続きなど実施段階までサポートしてもらえるかも確認します。こうした対応が整っていれば、事業承継に向けて一貫した支援を受けられ、安心して任せられる体制があると判断できます。
他の士業との連携力がある
事業承継では相続や登記、不動産の手続きなど、税務以外の分野も関わるため、他の専門家と連携できる体制が整っている税理士に依頼すると安心です。
例えば、税理士法人レガシィでは、税理士を中心に司法書士や行政書士、不動産会社などと連携した「360°サポート」を提供しており、各分野の専門家が連携して手続きを進める仕組みが整えられています。このような連携体制があれば、複数の専門家に個別で相談する手間が省け、事業承継に関する手続きをワンストップで進められます。
事業承継の支援を税理士に依頼する場合の注意点

事業承継を税理士に依頼する際は、できるだけ早めに相談を始めることと、料金体系が明確な税理士であるかを確認することが大切です。事業承継は早めに相談することで選択肢が広がり、計画的に進められます。また、費用が不明確なまま依頼すると、後々トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。
早い段階で相談する
事業承継には、後継者の育成、株式の移転、相続・贈与税の対策など、多くの準備が必要です。短期間で完了できるものではなく、時間的な余裕がないまま進めると、必要な対策が不十分になり、思わぬ問題に直面する可能性があります。
早期に税理士へ相談することで、自社の状況を丁寧に整理しながら複数の選択肢を検討でき、将来を見据えた計画的な事業承継を実現しやすくなります。特に相続税や贈与税対策には準備期間が必要です。早めに動けば、後継者への引き継ぎだけでなく、税務・財務・法務の各面でのリスクを抑えながら、スムーズに承継を進められます。
料金体系などが明確な税理士に相談する
税理士に事業承継の支援を依頼する際は、相談料・着手金・成功報酬などの費用項目が明確に提示されているかを確認し、見積もりの内容に納得できるかを判断することが大切です。また、提示された金額に含まれるサービス内容をしっかり確認しておくことで、契約後の認識違いや予期せぬ追加費用の発生を防げます。
さらに、業務の途中で追加費用がかかる可能性があるかどうかについても事前に説明を受けておけば、予算面での不安を軽減でき、安心して事業承継の準備を進められます。
事業承継でのお悩みは専門家までお寄せください
事業承継は企業の将来に深く関わる重要な節目であり、早い段階で信頼できる専門家に相談することが大切です。税理士に依頼すれば、税務対策を含む多面的なサポートが受けられ、後継者へのスムーズな引き継ぎが実現しやすくなります。
税理士法人レガシィでは、親族内承継やM&Aを含めた多様な選択肢の中から、企業の実情に応じた最適な支援を提供しています。事業承継の進め方にお悩みの方は、まずは「レガシィの事業承継・M&Aコンサルティングサービス」をご覧いただき、ぜひご検討ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













