MBOとは? メリットや実施の流れについて解説
Tweet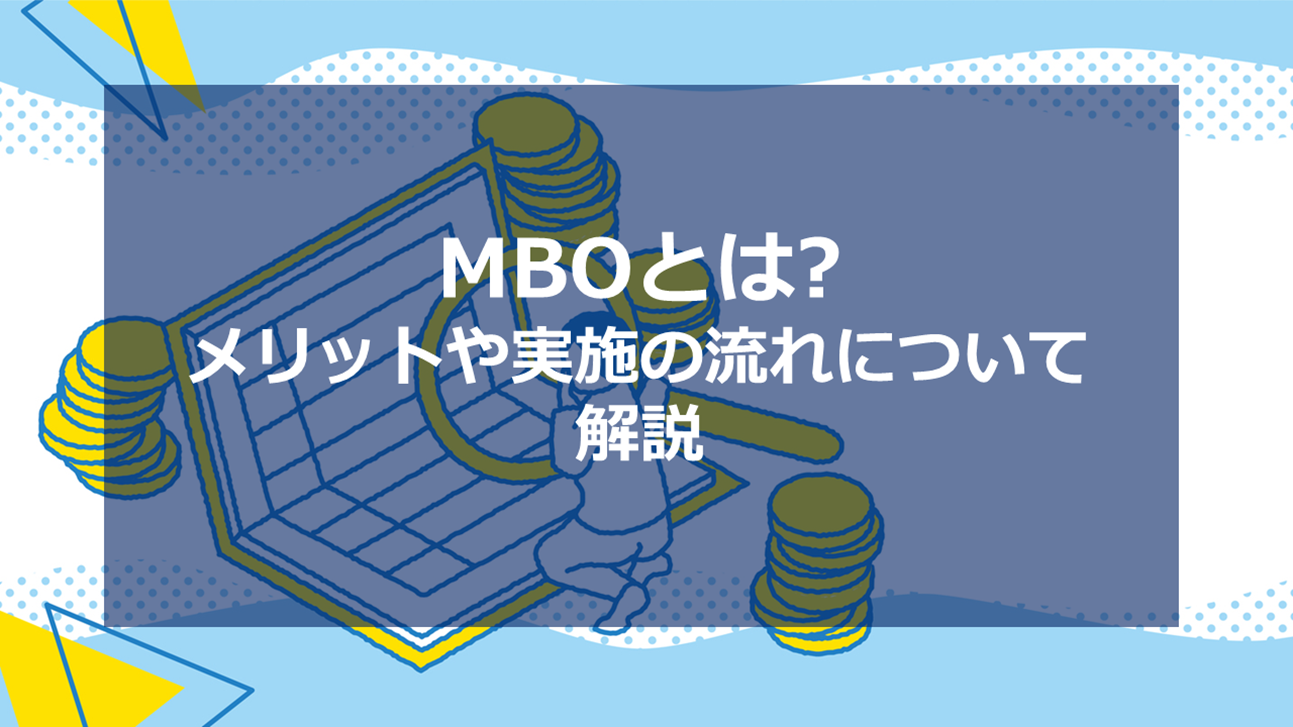
MBO(経営陣による買収)は、企業の経営層が自社の株式を取得し、経営権を掌握する手法です。
中堅企業の経営者にとって、事業承継や経営判断の迅速化を実現する手段として注目されています。本記事では、MBOの概要やメリット、実行の流れについて解説し、MBOを検討している経営者がスムーズに理解を深め、実行に向けた一歩を踏み出せるようサポートします。
MBOとはM&Aの手段のひとつ
MBOはM&A(Mergers and Acquisitions)の一形態で、他のM&A手法とは異なる特徴を持っています。
概要
MBO(Management Buyout)とは、企業の経営層が自社を経営する権利を得るために、自社株を買い取ることを意味します。経営層である企業役員はこれにより、株主の意向をうかがわなくとも、迅速でフレキシブルな意思決定が可能で、中長期的な視点での経営に集中できます。MBOはM&Aの一環として行われることが多く、類似手段としてEBO(Employee Buyout)があります。
MBOは上場・非上場企業問わず実行され、企業役員が株式を購入して経営権を得る手段として確立しています。企業役員独自で実行するほか、投資機関や金融機関と連携して行われるケースもあります。
TOBとの違い
MBOとよく比較される手段に同じくM&AのひとつであるTOB(Takeover Bid)があります。
MBOは上場企業、非上場企業のどちらでも実行されていますが、TOBは上場企業のみを対象に取引所外で株式を入手する手段で、外部の第三者が買い手となる場合もあります。
TOBは、企業役員の同意を得ずに第三者が株式買収を進める「敵対的TOB」として用いられることもありますが、企業役員が合意して行う「友好的TOB」もあります。一方、MBOは企業役員が自社の株式を取得し、オーナー経営者を目指す方法であり、基本的に友好的な買収として行われます。つまり、MBOは買収を行う主体に着目した用語で、TOBは買収方法に着目した用語です。
MBOを行うメリット

MBOを実行するメリットは、多岐にわたります。主なものは下記のとおりです。
- 経営判断・意思決定の迅速化
- 中長期的な視点での経営
- TOBの回避
- 事業承継での後継者問題解決
経営判断・意思決定の迅速化につながる
現代社会においてはIT技術の進展や世界情勢による為替や株価の急変動など大きな変化が常に訪れています。そのため、企業の経営者には迅速かつ柔軟な対応が求められています。しかし、企業役員以外に多くの株主が存在する場合、経営判断には株主総会での決議が必要となり、意思決定に時間がかかります。
こうした事態を避けるためにMBOは有効です。企業役員が株式を保有できれば、経営判断の自由度が高まり、意思決定が迅速に行えるためです。MBOにより経営権が集中し、承認が不要となれば、中核事業への資源の集中や効率化による業績向上をスムーズに実現できる可能性があり、企業にとっては大きなメリットとなります。
中長期的な視点での経営を実現できる
多くの株主は投資による利益を重視し、短期的な要求をすることがあります。そのため、株主が多い企業では中長期的な視点での経営が難しくなるケースがあります。企業役員が長期的な経営を志向すると、株主との考え方に齟齬が生じ、対立を招く可能性もあります。
このようなケースでMBOを実行すれば、短期的な業績向上にこだわらずに、中長期的な視点で経営戦略を策定することが可能となり、企業の成長につなげやすくなります。
TOB回避策として利用できる
敵対的TOBにより、企業にとって望ましくない第三者に大量の株式を入手されることで、その第三者へ経営権が移転してしまう危険があります。
このような状況を回避するために、MBOは重要な役割を果たします。MBOを実施することで、企業役員が株主となり、経営権を掌握するための株式を保有できます。それにより、第三者への株式の流出が制限され、TOBの実行を防ぐことができます。
また、非上場企業の場合、MBOによって企業役員が株式を取得し、定款で譲渡制限を設定することで、株式の譲渡に企業の同意を必要とすることが可能です。これにより、非上場企業でも敵対的買収を防止することができます。
事業承継での後継者問題を解決できる
MBOによって現経営陣が株式を買い取ることで、後継者を外部から探す必要がなくなります。これにより、企業は内部の信頼できる経営陣から後継者を選び、円滑な事業承継を実現できる可能性があります。
また、事業承継には多額の資金が必要ですが、特別目的会社(SPC)を活用したMBOを行うことで、資金調達の負担を軽減し、承継をスムーズに進めることが可能です。SPCは株式の買い取りを目的とした法人であり、金融機関からの資金調達を行うことで、個人資金とは切り離して財源を確保できます。
特別目的会社(SPC)については下記をご参考ください。
MBOのデメリット

MBOにはデメリットもあります。
- 株主との対立リスク
- 財務状況の悪化
- 企業体質の変化を阻害する
などです。
株主との対立リスクが生じる
MBOは、既存の株主との対立を引き起こす可能性があります。特に、株式の売却価格をめぐって意見が対立することもあり、調整が難航するとMBOの成功が危ぶまれることもあります。
そのため、MBOを円滑に進めるためには、既存の株主との十分なコミュニケーションを取り、理解と信頼を得ることが重要です。株価の算定にはさまざまな方法があり、公正な評価を行うために専門家の意見を参考にしながら適正な価格を決定することが求められます。
財務状況の悪化リスクがある
MBOを行うためには多額の資金調達が必要となり、財務状況が悪化してしまうのもMBOを実行するデメリットです。
SPCを設立する場合、金融機関や投資ファンドから融資を受けて株式の入手を進めることになり、MBO成功後も企業の負債は残ります。利息返済も考慮して検討する必要がある点に注意が必要です。
企業体質の変化を阻害するリスクがある
企業役員だけが経営権を持つため、外部からの意見を聞く機会が少なくなり、企業体質の変化を阻害するという点にも注意が必要です。
世界情勢や経済動向の変化により、企業活動も柔軟な変化に対応していくことが重要となっているため、従来のやり方に固執した社風では対応しきれず、経営が悪化するリスクがあります。長期的な視点を持ちながらも、短期的な変化に柔軟に適応するためには、外部の意見を取り入れることも重要です。
MBO実行の流れ
ここからはMBOを実行する際によく用いられる、SPC(特別目的会社)を設立した手法による具体的な流れを紹介します。
- 対象企業の価値を算定
- 「SPC」の設立
- 資金の調達
- 株式の買い取り
- SPCと対象企業の合併
1.対象企業の価値を算定する
最初にやるべきことは、対象となる企業の価値を算定することです。これを基に株式の買い取り価格を決定しますので、のちの資金調達などに影響する非常に重要なプロセスになります。
MBOの場合には、過半数以上の株式を取得し経営権を入手することが目的になるため、通常の株式価格にプレミアムを上乗せした価格になるのが一般的です。
企業の価値を算定する方法には、さまざまな方法があります。代表的なものは以下のとおりです。
- DCF法:将来のキャッシュフローに基づいて算定する
- 修正純資産法:企業の純資産により算定する
- 類似会社比準法:類似する上場企業の財務内容や株価を基に算定する
ただし、企業の算定方法は専門的な知識が必要となるため、専門家と相談するなどの対応が必要となります。
非上場企業の算定方法は下記を参考にしてください。
2.株式の受け皿「SPC」を設立する
次の準備としてはSPC(特別目的会社)の設立です。SPCは特定の目的を果たすために設立される法人で、MBOにおいては買収資金の調達手段として活用されます。
株式の買い取りには多額の資金が必要となりますが、企業役員や後継者個人の信用力だけでは十分な資金調達が難しい場合、SPCを設立します。SPCを利用することで、経営陣個人が負債を負うことを避け、買収対象会社の返済能力を活用することが可能です。
また、ひとつ注意しておきたいのが社名です。上場企業の場合「その新会社の名称が当該上場会社との関連を容易に推測させるものであったり、所在地、代表者・役員の一部が当該上場会社と同一であったりするなどの事例」については、MBO実行が類推できてしまうとして注意喚起がされています。
3.株式取得のための資金を調達する
上記で解説しているように、株式の買い取り資金はSPCが準備をします。調達先は、対象企業の取引銀行が有力な候補となりますが、そのほかにも日本政策金融公庫なども考慮すべき調達先となります。また、ノンバンクや投資ファンドを利用するケースもあります。しかし、どこを選ぶにしても対象企業の価値や返済能力が審査されることになります。損益やキャッシュフローなどをチェックして、専門家のサポートも受けながら進めることが必要です。
4.SPCが株主から株式を買い取る
資金調達ができたら、株式の買い取りを開始します。非上場株式の場合には、株主名簿などにより、株主と直接交渉をして株価を買い取ります。上場企業の場合には、公開買付けによって株式を入手することもあります。
5.SPCと対象企業とで合併させる
最後にSPCと対象企業を合併させることが必要です。SPCは買収を目的として設立されるため、事業実体がなく、金融機関からの融資を受けるための信用力がありません。そこで、対象企業とSPCを合併させることで、対象企業の信用力をSPCに付与し、金融機関からの融資を可能にします。この仕組みにより、金融機関は実質的には対象企業に融資していることとなり、より多くの資金調達が可能になります。
また、SPCを用いた合併は適格合併となることが多いです。これにより、税務面でのメリットが期待できます。ただし、SPCが多額の繰越欠損金を計上している場合には、適用されない可能性があります。繰越欠損金の引き継ぎを前提とする場合には、事前に専門家への相談が必要になります。
MBOを円滑に進めるためのポイント
MBOを円滑に進めるためには、以下のように押さえるべきポイントがあります。
- 入念な計画
- 既存株主との対立を避ける
- 専門家に相談する
入念に計画を立てる
MBOを成功させるためには、入念な計画が必要です。MBOでは、それ自体を成功させることに注力しがちですが、MBOは経営改革のスタートであり、ゴールではないことを忘れないでください。
MBOは手段であり、目的は経営を改革して、企業を成長させることにあります。
そのため、MBOへ着手する前から経営へのビジョンを明確化しておくことが必要です。例えば、MBO後の具体的な施策や株式の買い取りで調達した資金返済の問題などです。上場企業の場合には、上場廃止になるので、その後の資金調達や信用力の低下などに関する問題も考えておく必要があります。
既存株主との対立を避ける
MBOで注意したいことのひとつに「利益相反」があります。これは、MBOを行う際なるべく安価で株式を買おうとする企業役員と、なるべく高く売りたい株主の間の対立により発生します。
本来は株主の利益を優先すべき企業役員が株主の利益を損ねる行為になるため、株式の価格などを巡って、大きな対立になる恐れもあります。結果的にMBOが失敗してしまう可能性も排除できませんので、株式価格の適正化やMBOの目的・プロセスの開示を通して、既存株主との綿密なコミュニケーションを取ることが重要です。
専門家に相談する
MBOでは、企業価値の算定による株式の価格設定やSPCの設立・合併、既存株主との交渉など、専門知識が必要なプロセスが多くあります。そのうち一つでも問題が生じると、MBOが成立しない可能性があります。そのため、MBOを成功させるには、専門家のアドバイスが不可欠です。さまざまな専門知識を持つ専門家ならば、トラブルにも対応でき、スムーズに目標を達成できる可能性が高まります。
MBOや事業承継のお悩みは専門家までご相談ください
ご紹介してきたようにMBOは企業の役員が経営権を得て、中長期的な視点での経営を実現するためなどに適しています。特に事業承継を考えている場合には、非常に有効な手法です。
しかし、一方で実施にはさまざまな専門知識が必要となり、知見を持った専門家のサポートは欠かせません。
レガシィマネジメントグループでは、事業承継を相談から承継までサポートするサービスを実施しています。相続専門60年以上の実績を活かしてサポートいたします。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













