シニアの健康管理はスマートウォッチで|メリットや選び方、機能を解説
Tweet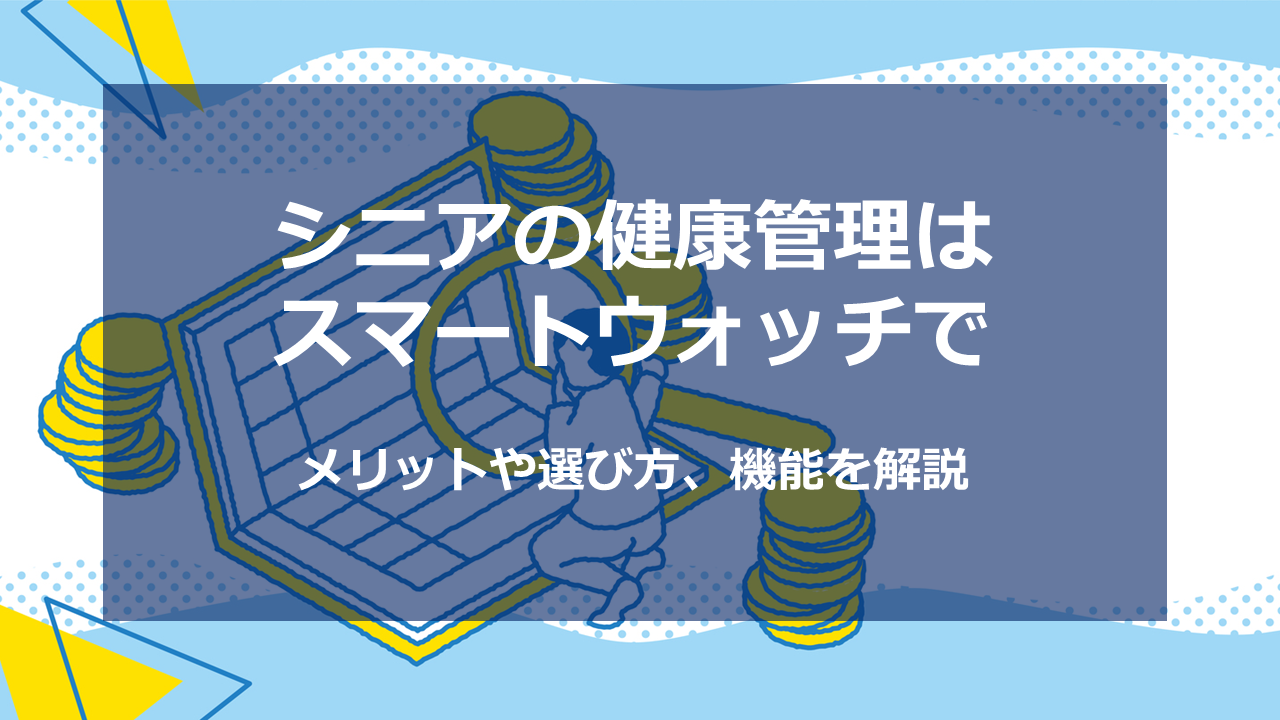
健康管理にスマートウォッチを活用する方が増えています。特にシニア世代にとって、スマートウォッチは単なるガジェットではなく、健康を守る頼もしいパートナーになります。歩数や心拍数、睡眠の質など多様なデータを自動で記録・分析してくれるため、日々の健康状態を手軽に把握できるようになります。
また、緊急SOS機能や転倒検知など、シニアの安全を守る機能も充実しています。この記事では、シニアの健康管理におけるスマートウォッチのメリットや選び方、主要な機能について詳しく解説していきます。健康寿命を延ばすための強い味方となるスマートウォッチの魅力を、ぜひ知っていきましょう。
目次
スマートウォッチとは?シニアの健康管理における役割
スマートウォッチは腕時計型のウェアラブルデバイスで、時計機能だけでなく健康管理や通知機能など多機能なデジタル機器です。スマートフォンと連携して使用するタイプが主流ですが、最近ではスマートフォンがなくても単独で使える製品も増えています。
スマートウォッチの基本的な仕組み
スマートウォッチは内蔵されたセンサーによって、心拍数や動きなどを検出し、健康データを収集します。収集したデータはBluetooth通信などを通じてスマートフォンのアプリと連携し、詳細な分析や長期的な傾向を確認することができます。
多くのモデルではタッチスクリーンやボタン操作で簡単に各種機能にアクセスできるよう設計されており、シニアの方でも直感的に使いこなせる工夫がされています。一般社団法人電子出版アクセシビリティ推進協議会(AEBS)によると、最新のモデルでは大きな文字表示や音声操作機能を搭載し、視力や指先の動きに不安のある方でも使いやすくなっています。
従来の健康管理との違い
従来の健康管理では、血圧計や体温計など個別の機器を使って測定し、手帳などに記録する方法が一般的でした。しかし、この方法では測定と記録に手間がかかり、継続することが難しいという課題がありました。
スマートウォッチは着けているだけで常時測定・自動記録されるため、手間なく健康データを蓄積できます。さらに測定結果をグラフ化して表示したり、異常値を検知して警告したりする機能も備えているため、健康状態の変化に早く気づくことができます。厚生労働省でも記録したデータを医師に見せることで、より適切な診断や治療にも役立てられるのも大きなメリットと述べています。
シニアにおすすめのスマートウォッチ健康管理機能
 スマートウォッチには様々な健康管理機能が搭載されています。シニアの方々が日常的に活用できる主要な機能について詳しく解説します。
スマートウォッチには様々な健康管理機能が搭載されています。シニアの方々が日常的に活用できる主要な機能について詳しく解説します。
身体活動のモニタリング
歩数計は最も基本的な機能で、日々の活動量を数値で確認できます。多くのスマートウォッチでは歩数だけでなく、距離や消費カロリーも自動計算してくれます。これにより、適度な運動習慣を維持するための目安になります。
また、階段の上り下りや速歩きなどの活動も認識し、「アクティブな時間」として記録するモデルもあります。厚生労働省が推奨する「1日8,000歩」や「週150分の中強度の運動」といった健康目標の達成状況も簡単にチェックできるため、モチベーション維持にも役立ちます。
心臓と循環器系の健康管理
心拍数測定は安静時と運動時の心拍変動を記録することで、心臓の健康状態を把握するのに役立ちます。通常より高い/低い心拍数が続く場合はアラートで知らせてくれる機能を持つモデルもあります。
さらに高機能なモデルでは、心電図機能を搭載し、不整脈の一種である心房細動(AF)などの早期発見に貢献しているものもございます。また、血圧測定機能を備えたスマートウォッチもあり、高血圧の管理に活用できます。日本循環器学会によるとこれらの機能は特に循環器系疾患リスクの高いシニア世代にとって、日常的な健康管理の強い味方となるとのことです。
睡眠の質のモニタリング
睡眠時の体の動きや心拍変動から、睡眠の質を分析する機能を搭載したスマートウォッチが増えています。浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠などの睡眠サイクルを記録し、睡眠の質をスコア化して表示します。
睡眠中の血中酸素濃度を測定できるモデルでは、睡眠時無呼吸症候群の兆候を検知することも可能です。参考の数値となりますが、日本睡眠学会によると良質な睡眠は認知機能や免疫力維持に重要であり、シニアの健康維持には欠かせない要素です。自分の睡眠パターンを知ることで、生活習慣の改善にもつなげられます。
その他の健康指標の測定
血中酸素濃度(SpO2)を測定できる機能は、肺や心臓の健康状態を反映する重要な指標です。特に呼吸器系の持病がある方にとって、日々の状態管理に役立ちます。
また、ストレスレベルを心拍変動から推定する機能や、女性の方向けの月経周期管理機能なども搭載されたモデルがあります。最新のモデルでは皮膚温の変化を検知して体温変化を推測する機能も登場しており、健康管理の幅がさらに広がっています。自分にとって必要な健康指標を把握できるモデルを選ぶことで、効果的な健康管理が実現できると日本医師会でも述べられています。
シニアの安全を守るスマートウォッチの特別機能
スマートウォッチは健康管理だけでなく、シニアの方の安全を守る機能も充実しています。一人暮らしのシニアや外出が多い方に特におすすめの機能を紹介します。
緊急通報と転倒検知機能
転倒検知機能は、内蔵の加速度センサーが急激な動きと衝撃を検知し、転倒したと判断すると自動的に緊急連絡先に通知する機能です。高齢者の事故で最も多い「転倒」による危険から身を守るための重要な機能といえます。
また、緊急SOSボタンを搭載したモデルでは、体調が悪くなったときや危険を感じたときにボタンを長押しするだけで、あらかじめ登録しておいた家族や救急サービスに通報できます。日本高齢者生活支援学会によると、これらの機能は特に一人暮らしのシニアにとって、「もしも」の時の命綱となる可能性があるとのことです。
位置情報共有と見守り機能
GPS機能を搭載したスマートウォッチでは、着用者の現在地を家族と共有することができます。認知症などで道に迷う可能性がある方の見守りに役立つほか、外出先で体調不良になった場合も、正確な位置を伝えられるため迅速な援助が期待できます。
一部のモデルでは、あらかじめ設定したエリアから出た場合に自動通知する「ジオフェンス機能」も備えており、より安心感のある見守りが可能です。位置情報の共有は、プライバシーとの兼ね合いもありますが、家族との信頼関係の中で活用すれば、シニアの自立した生活を支える強力なツールになると総務省でも述べられています。
服薬リマインダーと健康管理アラート
定時に薬を服用する必要のある方にとって、スマートウォッチの服薬リマインダー機能は非常に便利です。設定した時間になると振動や音でお知らせしてくれるため、うっかり忘れを防止できます。
また、長時間の座りっぱなしを検知して体を動かすよう促す「活動リマインダー」や、水分摂取を促す「水分補給リマインダー」機能も健康維持に役立ちます。これらの機能は単なる「思い出させる」だけでなく、健康的な生活習慣の形成を支援する役割も果たしています。
シニアに最適なスマートウォッチの選び方
数多くあるスマートウォッチの中から、シニアの方に適したものを選ぶためのポイントを解説します。使いやすさや必要な機能を重視した選び方を知っておきましょう。
使いやすさと操作性を重視する
スマートウォッチを選ぶ際、最も重要なのは使いやすさです。画面が大きく、文字が読みやすいモデルを選びましょう。また、タッチパネルの感度が良く、操作がしやすいものが理想的です。
ボタン操作が併用できるタイプは、タッチ操作が苦手な方にもおすすめです。さらに、音声操作に対応したモデルであれば、手が塞がっているときや細かい操作が難しい場合でも便利に使えます。実際に店頭で触ってみるか、オンラインの場合は返品ポリシーを確認してから購入すると安心です。自分に合った操作性を持つモデルを選ぶことが継続使用の鍵となります。
バッテリー寿命と充電のしやすさ
毎日充電するのが負担になるシニアの方には、バッテリー寿命の長いモデルがおすすめです。一般的なスマートウォッチは1〜2日の連続使用が多いですが、最長で2週間持続するモデルもあります。機能をある程度絞れば、より長く使えるものもあります。
充電方法も重要なポイントです。磁気式の充電ケーブルやワイヤレス充電に対応したモデルは、小さな端子を差し込む必要がなく、手先の器用さに自信がない方でも簡単に充電できます。充電忘れを防ぐためには、就寝時など決まった時間に充電する習慣をつけると良いでしょう。バッテリー残量が少なくなると通知してくれる機能も便利です。
価格と機能のバランス
スマートウォッチの価格帯は非常に幅広く、5,000円程度の入門モデルから10万円を超える高機能モデルまであります。自分に本当に必要な機能は何かを考え、過剰な機能が付いていないものを選びましょう。
例えば、基本的な健康管理機能(歩数、心拍数、睡眠)だけで十分なら、中価格帯(1〜3万円)のモデルでも十分かもしれません。一方、医療グレードの精度を求めるなら、やや高価なモデルの方が満足度は高いでしょう。初めてスマートウォッチを使う方は、まずはリーズナブルなモデルから始めて、使用感を確かめてから次のステップに進むのも賢明な選択です。
スマートフォンとの互換性
多くのスマートウォッチはスマートフォンとペアリングして使用します。お使いのスマートフォン(iPhoneやAndroid)と互換性があるかどうかを事前に確認することが重要です。例えば、Apple Watchは基本的にiPhoneとしか連携できません。
また、スマートフォンを持っていない方や操作が苦手な方には、SIMカードを内蔵して単独で通信できるモデルもあります。こうしたモデルなら、スマートフォンがなくても緊急通報や位置情報共有などの機能が使えます。家族が遠方に住んでいる場合でも、このタイプのスマートウォッチがあれば安心して見守りができるでしょう。
シニアの健康管理におけるスマートウォッチ活用術
スマートウォッチを購入しただけでは健康は改善しません。効果的に活用するための具体的な方法を見ていきましょう。日常生活にどう取り入れるかがポイントです。
日常的な健康データの記録と活用
スマートウォッチで記録された健康データは、定期的に確認する習慣をつけましょう。多くのスマートウォッチは専用アプリで日々のデータをグラフ化して表示するため、変化の傾向が視覚的に分かりやすくなっています。
例えば、歩数や活動量のデータから、自分の活動パターンや運動不足の日をチェックし、生活習慣の改善につなげることができます。また、心拍数や血圧の変動パターンから、ストレスや体調変化に早めに気づくことも可能です。特に慢性疾患を持つ方は、これらのデータを医師の診察時に見せることで、より適切な治療やアドバイスを受けられる可能性があります。
家族や医療関係者との情報共有
多くのスマートウォッチの健康管理アプリには、データを家族や医師と共有する機能があります。離れて暮らす家族とデータを共有すれば、遠隔でも健康状態を見守ることができるようになります。
特に、通院中の方は診察前にデータをまとめておくと、医師との相談がスムーズになります。日々の血圧変動や心拍数の変化、睡眠の質などのデータは、医師の診断に役立つ重要な情報となります。ただし、プライバシーの観点からデータ共有の範囲は自分で適切に設定し、信頼できる相手とのみ共有するようにしましょう。
目標設定と継続使用のコツ
スマートウォッチを効果的に活用するには、適切な目標設定と継続使用が鍵となります。まずは自分の現状に合わせた無理のない目標を設定しましょう。例えば、現在の歩数が平均3,000歩なら、まずは5,000歩を目指すなど段階的に設定すると達成感を得やすくなります。
継続して使用するコツは、スマートウォッチを身につけることを日課にすることです。朝起きたら着ける、充電は就寝時にするなど、生活のルーティンに組み込むと習慣化しやすくなります。また、家族や友人と一緒に使って互いに励まし合うのも継続のモチベーションになります。多くのスマートウォッチアプリには達成バッジや友人とのチャレンジ機能があり、これらを活用すると楽しみながら健康管理を続けられるでしょう。
シニアの健康管理スマートウォッチ導入時の注意点
スマートウォッチを健康管理に活用する際には、いくつかの注意点や限界も理解しておく必要があります。期待しすぎず、適切に活用するためのポイントを紹介します。
測定精度と医療機器との違い
スマートウォッチは便利な健康管理ツールですが、医療機器としての認証を受けていないモデルがほとんどです。そのため、測定値はあくまで参考値と考え、絶対的な数値として捉えないことが重要です。特に血圧や心電図などの重要な指標は、医療用の機器で定期的に確認することをお勧めします。
また、測定方法や着用位置によって精度が変わることも理解しておきましょう。例えば、心拍数は腕の動きや時計の装着具合によって誤差が生じることがあります。健康管理に活用する際は、絶対値よりも「変化の傾向」を見ることが大切です。急激な変化や継続的な異常値が見られた場合は、必ず医療機関で相談するようにしましょう。
プライバシーとデータセキュリティ
スマートウォッチで収集される健康データは非常に個人的な情報です。これらのデータがどのように保存され、誰とどのように共有されるのかを理解しておくことが重要です。多くのメーカーのプライバシーポリシーを確認し、自分が安心できる範囲で設定を行いましょう。
また、アプリのアカウント設定時には強固なパスワードを設定し、可能であれば二段階認証を有効にすることをお勧めします。家族と共有する設定にする場合も、どのデータをどこまで共有するかを自分で決定できることを確認しておきましょう。健康データは非常に重要な個人情報であり、その取り扱いには十分な注意が必要です。信頼できるメーカーの製品を選び、データ保護に関する設定を適切に行うことが安心して利用するための基本となります。
過度な依存とストレスの回避
健康管理ツールとしてスマートウォッチは便利ですが、数値やデータに過度にとらわれると、かえってストレスの原因になることもあります。例えば、歩数目標を達成できなかった日に必要以上に落ち込んだり、睡眠スコアの低さに不安を感じたりすることは避けるべきです。
スマートウォッチはあくまでも健康管理を「サポート」するツールであり、数値だけで健康状態のすべてが判断できるわけではありません。自分の体調や感覚も大切にしながら、バランスよく活用することが重要です。「測れること」だけが健康ではなく、心の健康や生活の質も含めた総合的な視点を持ちながら活用することで、スマートウォッチは真の意味で健康的な生活の良きパートナーとなるでしょう。
まとめ
スマートウォッチはただ身につけるだけでなく、データを定期的に確認し、家族や医療関係者と共有しながら活用することで、その効果を最大限に引き出せます。あなたの健康を守るパートナーとして、ぜひスマートウォッチを毎日の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。健康寿命を延ばし、いきいきとした生活を送るための強い味方になってくれるはずです。
レガシィマネジメントグループが提供する「ワクデジ」はデジタル技術を活用の支援を通して日常的な“ワクワク”を提供し、人生100年時代にウェルビーイングな人生を送ることができるように支援するものです。スマートウォッチをつかった健康管理を始めてみませんか?
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表














