高齢の親の見守りサービス 種類や選ぶポイントは?
Tweet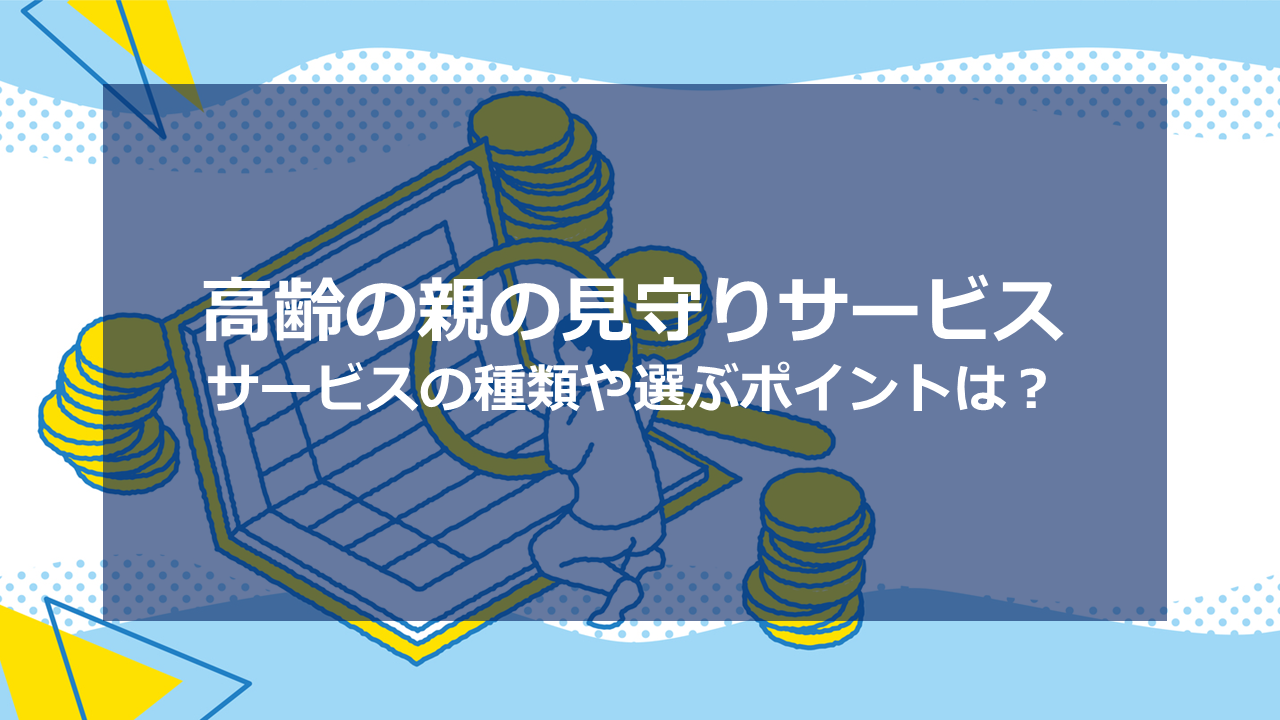
高齢の親が離れて暮らしていると、日々の安否や健康状態が気になるものです。特に一人暮らしの場合、「何かあったらどうしよう」という不安は大きくなります。そんな悩みを解決するのが「見守りサービス」です。センサーやカメラ、定期訪問など様々なタイプがあり、自治体の無料サービスから民間企業の有料サービスまで選択肢は多岐にわたります。この記事では、高齢者見守りサービスの種類や特徴、選び方のポイントを詳しく解説します。離れていても親の安全を確保し、お互いが安心して暮らすための方法を見つけていきましょう。
目次
高齢者向け見守りサービスとは
見守りサービスとは、離れて暮らす高齢者の安否や健康状態を定期的に確認し、緊急時には適切な対応を行うサポートシステムです。近年の核家族化や高齢化社会の進行により、一人暮らしの高齢者や老々世帯が増加する中、こうしたサービスの需要は年々高まっています。
見守りサービスの基本的な役割
見守りサービスの主な役割は、日常的な安否確認と緊急時の対応です。センサーや通信機器を使った遠隔監視から、人による直接訪問まで、様々な方法で高齢者の生活をサポートします。多くの場合、異変があれば家族や緊急連絡先に通知される仕組みになっています。
また、見守りサービスは単なる安全確保だけでなく、定期的な人との交流による孤独感の軽減や、健康状態の変化の早期発見にも役立ちます。介護が必要になる前の段階で利用することで、自立した生活をより長く続けられるという予防的な効果も期待できます。
見守りサービスの対象と利用者
主な対象は、要介護度が高くなく、ある程度自立した生活ができる高齢者です。完全に介護が必要な状態であれば、介護保険サービスなどの別の支援が適しています。利用者の多くは、日常生活は自分でできるものの、急な体調変化などに備えたい方や、遠方に住む家族が安心のために導入するケースが一般的です。
利用者の生活状況や健康状態、家族の状況によって最適なサービスは異なるため、個々のニーズに合わせた選択が重要となります。要介護認定を受けていない高齢者でも利用できる民間サービスや自治体独自の支援が多いのも特徴です。
見守りサービスの主な種類と特徴
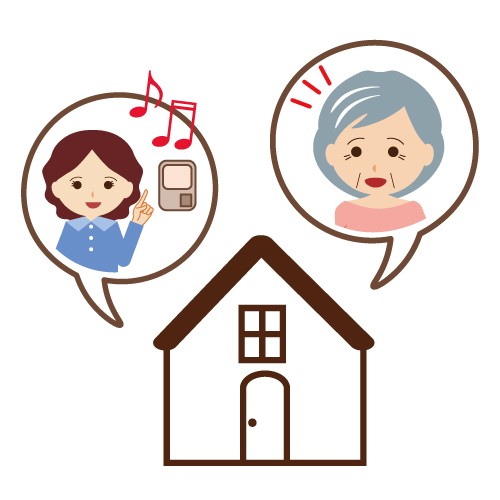
見守りサービスは大きく分けると、人による見守りと機器による見守りの2種類があります。それぞれに特徴や利点があるため、高齢者の状況に合わせて選んでいきましょう。
訪問型見守りサービス
訪問型見守りサービスは、スタッフが定期的に高齢者宅を訪問し、直接対面で安否確認や健康状態の確認を行うサービスです。主に郵便局員や地域のボランティア、民間サービスの専門スタッフなどが担当します。訪問頻度は週1回から月1回程度と様々で、訪問時には簡単な会話をしたり、生活状況を確認したりします。
このサービスの最大のメリットは、実際に人が訪問するため、高齢者の表情や部屋の様子など、機械では捉えられない細かな変化に気づける点です。また、定期的な人との交流は孤独感の軽減にも効果的です。
センサー型見守りサービス
センサー型見守りサービスは、高齢者の自宅内に各種センサーを設置し、動きや生活パターンを検知するシステムです。主に玄関、トイレ、寝室などに人感センサーを設置し、一定時間動きがない場合や通常と異なる行動パターンが検知された場合に、家族やサービス提供者に通知が届く仕組みになっています。
このタイプの最大の特徴は、高齢者に負担をかけることなく24時間見守りができる点です。操作が不要で、日常生活をそのまま送れるため、高齢者の抵抗感が少ないことも利点です。ただし、長期的に見ると人による訪問型よりコストパフォーマンスが良い場合もあります。
オート電話・メール型見守りサービス
オート電話・メール型見守りサービスは、あらかじめ設定した時間に自動で電話やメールが高齢者に送信され、応答があるかどうかで安否を確認するシステムです。多くの場合、高齢者は電話に出るだけ、またはボタンを押すだけという簡単な操作で応答できます。応答がない場合は、家族や緊急連絡先に通知が届きます。
このサービスの特徴は、シンプルかつ低コストである点です。高齢者がテクノロジーに不慣れでも、電話に出るという日常的な動作だけで利用できます。ただし、緊急時の対応や詳細な生活状況の把握には限界があります。
カメラ型見守りサービス
カメラ型見守りサービスは、高齢者の自宅内にカメラを設置し、映像を通じて遠隔から様子を確認できるシステムです。スマートフォンやパソコンから映像をリアルタイムで確認でき、中には通話機能付きのものもあります。最近のモデルでは、AIが異常を検知して通知する機能や、プライバシーに配慮して普段は画像を暗号化し、緊急時のみ解除される機能などもあります。
直接目で確認できる安心感がある一方で、常に見られているという抵抗感を高齢者が感じる可能性もあります。このため導入時には十分な説明と同意が必要です。複数のカメラで家全体をカバーできるなど、高い安心感を得られます。
宅配型見守りサービス(配食サービス)
宅配型見守りサービスは、食事の配達を通じて高齢者の安否確認を行うサービスです。定期的に食事を届けるスタッフが、配達時に高齢者の様子を確認し、異常があれば家族や緊急連絡先に連絡します。食事の栄養バランスが整っているため、高齢者の健康維持にも役立ちます。
メリットは、食事という生活に欠かせないものと見守りが一体化している点です。買い物や調理が困難な高齢者にとっては特に有用です。また、定期的に配達員と対面するため、コミュニケーションの機会にもなります。ただし、緊急対応には不向きで、配達時間帯以外は見守りができないというデメリットもあります。
地域や自治体が提供する無料・低コストの見守りサービス
民間企業の有料サービスだけでなく、自治体や地域団体が提供する無料または低コストの見守りサービスも多数存在します。経済的な負担を抑えながら安心を得たい方におすすめです。
自治体による見守り配食サービス
多くの自治体では、高齢者向けの配食サービスと見守りを組み合わせたプログラムを提供しています。例えば墨田区の「高齢者配食みまもりサービス」や練馬区の「見守り配食事業」などがあります。これらは栄養バランスの取れた食事を定期的に届けながら、配達員が高齢者の安否を確認するサービスです。
自治体のサービスは民間と比べて低価格で、所得に応じて無料や割引になる場合もあります。ただし、対象者の条件(年齢や世帯状況など)が設けられていることが多いため、利用前に各自治体の窓口に確認する必要があります。
民生委員や地域ボランティアによる見守り
民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉の相談員で、担当地域の高齢者宅を定期的に訪問し、安否確認や生活相談を行います。この活動は無料で利用できる大切な地域福祉資源です。また、社会福祉協議会などが運営する地域ボランティアによる見守り活動も各地で実施されています。
例えば新宿区では「地域見守り協力員事業」を実施しており、研修を受けたボランティアが定期的に高齢者宅を訪問しています。こうした地域に根ざした見守りは、高齢者にとって顔見知りによる安心感があり、地域コミュニティとのつながりを維持する効果もあります。利用を希望する場合は、市区町村の福祉課や地域包括支援センターに問い合わせると良いでしょう。
地域交流による非制度的見守り
公的なサービスではありませんが、地域のイベントやサークル、趣味活動などへの参加を通じた「非制度的見守り」も効果的です。こうした活動に定期的に参加することで、地域の人々が自然と高齢者の様子に気を配る関係性が構築されます。
例えば、いつも参加している方が突然来なくなれば、参加者が心配して連絡を取るなど、自然な見守りの輪が生まれます。費用がかからず、高齢者自身の生きがいや社会参加にもつながるメリットがあります。特に人との交流が好きな方や、制度的な見守りに抵抗がある方に適しています。地域の公民館や社会福祉協議会などで行われている活動に参加してみることをおすすめします。
郵便局など公共サービスと連携した見守り
郵便局では「みまもりサービス」として、郵便局員による定期訪問や電話確認を行うサービスを提供しています。民間サービスでありながら、全国に拠点を持つ郵便局ならではの地域密着型のサポートが特徴です。特に地方の過疎地域でも利用しやすいのが強みです。
訪問時の様子は家族にレポートとして報告されるため、遠方に住む家族にとって安心材料となります。こうした公共性の高いサービスは、信頼性が高く、高齢者にも受け入れられやすいという特徴があります。
見守りサービスを選ぶ際のポイント
様々な種類がある見守りサービスですが、どのように選べば良いのでしょうか?高齢者本人の状況や家族のニーズを踏まえた選定ポイントを解説します。
高齢者本人と家族の意向バランス
見守りサービスを導入する際、最も重要なのは高齢者本人の意向を尊重することです。「見守られている」という感覚に抵抗を感じる方も少なくありません。そのため、本人が納得して受け入れられるサービスを選ぶことが長続きの秘訣です。一方で、家族側の安心感も重要な要素です。
例えば、本人は「人が来てくれる訪問型」を希望しているのに対し、家族は「24時間監視できるカメラ型」を望むなど、意見が食い違うケースもあります。こうした場合は、双方の折り合いがつく範囲でサービスを選定したり、段階的に導入したりするなどの工夫が必要です。高齢者のプライバシーや尊厳を尊重しながら、家族も安心できるバランスポイントを見つけることが大切です。
緊急時の対応体制と信頼性
見守りサービスの最も重要な機能の一つが、緊急時の対応です。異変を検知した後、どのような対応がなされるのかは、サービスによって大きく異なります。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 24時間365日の対応が可能か
- 緊急時の連絡先設定(複数設定可能か、順番は変更できるか)
- 専門スタッフの駆けつけ対応があるか(対応エリアや到着目安時間)
- 救急通報との連携体制(必要に応じて救急車を手配してくれるか)
- 過去の対応実績や利用者評価
特にセキュリティ会社が提供するサービスでは、緊急時に専門スタッフが駆けつける体制が整っている場合が多いです。一方、単純な通知サービスでは、異変を家族に知らせるだけで、その後の対応は家族に委ねられることもあります。高齢者の状態や家族の状況に応じて、必要な対応レベルを見極めることが重要です。
家族と高齢者のコミュニケーション強化
見守りサービスは便利な道具ですが、家族とのコミュニケーションの代わりにはなりません。むしろ、見守りサービスを活用しながら、より質の高いコミュニケーションを図ることが理想的です。
たとえば、見守りサービスから得られる情報をきっかけに会話を広げることができます。たとえば「今日はよく歩いたみたいだね、どこへ行ったの?」といった自然な問いかけが、日常的な会話の糸口になります。
また、定期的に電話や訪問を習慣化することも大切です。テクノロジーに頼りすぎず、直接声を聞き、顔を見て話す時間を意識的に持ちましょう。ビデオ通話などのオンラインツールも活用すれば、離れていても顔を見ながら話せる機会が増えます。
さらに、見守りサービスの使用感についても率直に意見交換を行い、高齢者本人の意向を尊重しながら使い方を調整していくことが重要です。加えて、緊急時だけでなく、日常的な情報も家族間で共有できるような仕組みを整えることで、安心感と信頼関係を深めることができるでしょう。
特に遠方に住む家族の場合、見守りサービスに安心感を求めるあまり、直接のコミュニケーションが減ってしまうケースもあります。テクノロジーはあくまでコミュニケーションを補完するものであり、人と人との関わりの大切さを忘れないようにしましょう。高齢者にとって、家族との会話や交流は心の支えになり、認知機能の維持にも効果があります。
まとめ
高齢の親の安全と安心を確保するためには、適切な見守りサービスの選択が重要です。 レガシィマネジメントグループが提供する「ワクデジ」は、「ワクワクをデジタルで!」をコンセプトに、高齢者のデジタルサービスの支援をし、暮らしを豊かにする訪問型専属デジタルサービスです。
メールやチャット、ビデオ通話といったコミュニケーションの支援から、日々のお困りごとやお買い物などを、デジタルを通してサポートします。付添い外出や、親族様あてへ報告をすることもできますので、見守りサービスとしてもご活用いただけます。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表














