相続税で税務調査が入るのはいくら以上?時期や対策も解説
Tweet相続税の税務調査は、財産の総額が大きいほど対象となる可能性が高まります。両親など被相続人になるであろう方が多額の財産を遺す可能性が高い場合、相続人になると想定される人にとって、その基準や実施時期、さらに有効な対策は事前に知っておきたい重要なポイントです。
目次
相続税で税務調査が入るのはいくら以上か
相続税の税務調査には、法律上「いくら以上で必ず実施される」という明確な基準はありませんが、実務では相続財産の規模が大きいほど対象となる可能性が高まります。特に、財産総額が2億円から3億円を超える場合、税務署による調査の優先度が上がる傾向があると指摘されています。
また、調査の判断基準は金額だけでなく、申告内容の一貫性や整合性も重要視されます。資産の種類や評価方法に不自然さがある、または申告内容と税務署が把握している金融機関や不動産に関するデータと食い違いがある場合は、資産規模にかかわらず調査対象となる懸念が生じます。
つまり、資産額が比較的少なくても、記載の誤りや評価の不備、説明が難しい資産の移動があると税務署の関心を引く傾向にあります。税務調査を回避するには、正確な財産把握と適切な申告書の作成が不可欠です。
相続税の税務調査が入られやすい人の特徴

相続税の税務調査は、申告内容や資産状況によって対象になりやすい人がいます。代表的な特徴としては以下のようなケースが挙げられます。
- 税理士に依頼せず自分で申告する
- 申告内容に不備や整合性の欠如がある
- 財産総額が多く富裕層に該当する
- 現金をタンス預金している
- 名義預金や過去の贈与が疑われる
税理士に依頼せず、自身で申告している
専門的な知識を持たずに自身で申告を行うと、財産評価や控除の適用に誤りが生じやすく、過少申告を疑われるケースがあります。実際、相続税の申告では一部の財産が申告されていなかったり、評価額が過小に見積もられていたりする事例が少なくありません。
一方、税理士が申告に関与すれば、専門家による適切な判断のもとで申告が行われるため、正確性と信頼性の高い内容となります。統計上も、相続税申告における税理士関与率は85%を超えており、所得税の約20%と比べても高い水準にあります。この点からも、税理士の関与がない申告は税務署から注目されやすく、調査対象となる可能性が高いと考えられます。
また、法令の適用の誤りや計算のミスといった単純な不備からも、税務調査へ発展することがあります。こうしたリスクを踏まえると、税務申告は専門家に依頼すると安心です。
申告漏れや申告内容に整合性がない
相続税の申告において必要な財産や取引を記載していなかったり、相続人ごとの申告内容に差異があったりする場合は、不自然と判断されやすくなります。こうした不一致は、税務署が申告の信頼性を疑う大きな要因です。
税務署は、金融機関や法務局などから得た情報と申告書の内容を突き合わせ、資産の漏れや評価額の差異を重点的に確認します。その際、齟齬や矛盾が見つかると、事実関係を確認するために税務調査が行われる可能性が高まります。
特に、取引履歴や財産の分配状況に違いがあると、意図的な申告漏れや評価の過少申告を疑われやすくなります。正確な申告内容を作成し、相続人間で整合性を保つことが、調査リスクを減らすうえで重要です。
財産総額が多く、富裕層に該当する
相続財産の総額が大きい場合、その分、課税額も高額になるため、税務署の関心が強まります。特に多額の財産を保有する人の相続では、申告内容の正確性や漏れの有無が厳しく確認されます。
税務署は高額相続の中でも、特に3億円を超える財産を有するケースを重点的に調査対象とする傾向があります。これは金額が大きいほど税率が高いことから、同じ金額の申告漏れや評価誤りによる追徴税額が税率が低い規模よりも増えるため、調査効率が高いと判断されるからです。
加えて、富裕層の相続には不動産、非上場株式、美術品など評価の難しい資産が含まれることが多く、適正な評価や申告がされているか入念にチェックされます。
タンス預金などの現金保有が多い
生活費などの予備として、現金を自宅に保有することは一般的です。しかし、100万円単位のまとまった現金を保管していた場合は、調査で注視されることが多いとされています。税務当局は「国税総合管理システム」を用いて、亡くなった被相続人の生前の納税状況に加え、報酬や支払いの法定調書などを総合的に管理しており、おおよその現金のストックを把握しています。「現金隠し」を疑われるのは、その金額と申告された預貯金の額があまりに乖離しているケースです。発覚した場合は、追徴課税などペナルティの対象となります。
名義預金と疑われる過去の贈与がある
名義預金とは、資金提供者と名義人が異なり、名義人が預金の引き出しや管理を実質的に行えない状態の預金を指します。たとえば親が子ども名義の口座に資金を入れても、子どもが通帳や印鑑を管理せず、本人の自由な使用ができない場合、その預金は贈与とは認められず、相続税申告時には被相続人の財産として申告しなくてはなりません。
被相続人が主に利用していた金融機関に当人以外の口座があり、多額の預金がされているものの引き出された形跡がない場合などは、税務調査の対象になるおそれがあります。
調査においては、相続人がその口座を認識していたか、贈与の意図があったか、または相続人自身が口座管理を行っていたかなどが詳細に調査されます。名義預金と認定されると、相続税の申告漏れとして追徴課税や罰則が科されるリスクが高まります。
そもそも税務調査とは

税務調査は、納税者の申告内容が正確かどうかを、税務署や国税局が確認する手続きです。法人税や所得税においては、確定申告をしている法人や個人事業主などが対象となります。対象者は、過去の申告状況や業種、取引内容など、一定の基準や疑義に基づいて選定されます。相続税の場合は、被相続人に基礎控除を超える資産があるのに無申告である場合や、過少申告が疑われる場合に実施されます。申告納税制度のもとでは、納税者の自主申告の信頼性を確保するうえで欠かせない制度です。
調査には任意調査と強制調査があり、ほとんどは納税者の協力のもとで行われる任意調査です。事前に電話や通知書で日程調整が行われ、帳簿や関係資料の確認が実施されますが、不正の疑いが強い場合には事前通知なしで行われることもあります。
一方、強制調査は国税局査察部が裁判所の令状を得て実施し、巨額脱税など重大な違反が疑われるケースに限られます。いずれの場合も調査には受忍義務があり、正当な理由なく拒否すれば罰則の対象となるため、適切な準備と対応が不可欠です。
相続税の税務調査への対応
任意調査では多くの場合、事前に通知があるため、その時点で指定された帳簿や契約書、通帳などを整理し、申告内容と突き合わせて事実関係を明確にしておくことが重要です。顧問税理士などがいる場合は事前に打ち合わせを行い、想定される質問への回答を準備しておくことで、当日の対応が円滑になります。
調査当日は、調査官の質問に対して事実に基づき簡潔かつ正確に答えます。調査官との会話はすべて公式なやり取りとして慎重に対応し、不確かな事項については確認後に回答する姿勢を維持することが重要です。資料の持ち帰りを求められた場合には、必ず控えを残し、預かり証を受け取っておくと後日のトラブル防止につながります。
不安がある場合や、専門知識を必要とするやり取りが想定される場合は、税理士の立ち会いを依頼すると安心です。税理士は税務調査の流れや対応に精通しており、調査官とのやり取りや交渉を適切にサポートしてくれるため、結果的に調査期間や負担の軽減にもつながります。
相続税における税務調査の特徴
相続税の税務調査では、被相続人が遺した財産全体を確認するため、現金や預金、不動産、動産など多様な資産が調査対象となります。特に預金の動きや申告書に記載されていない財産の有無など、細部まで精査される点が特徴です。
税務調査の連絡は相続人代表者に行われますが、当日は可能な限り相続人全員の立ち会いが望まれます。生前に被相続人とかかわりの深かった相続人が参加することで、資産の由来や利用状況について正確な説明が可能となります。
また、調査は被相続人が生前に暮らしていた居宅で実施されることが多く、残された書類や遺品からも情報が収集されます。調査の目的は申告内容の正確性を確認し、税の公平性を保つことであり、申告漏れや評価の誤りが判明した場合には修正申告を求められることがあります。
相続税における税務調査の状況
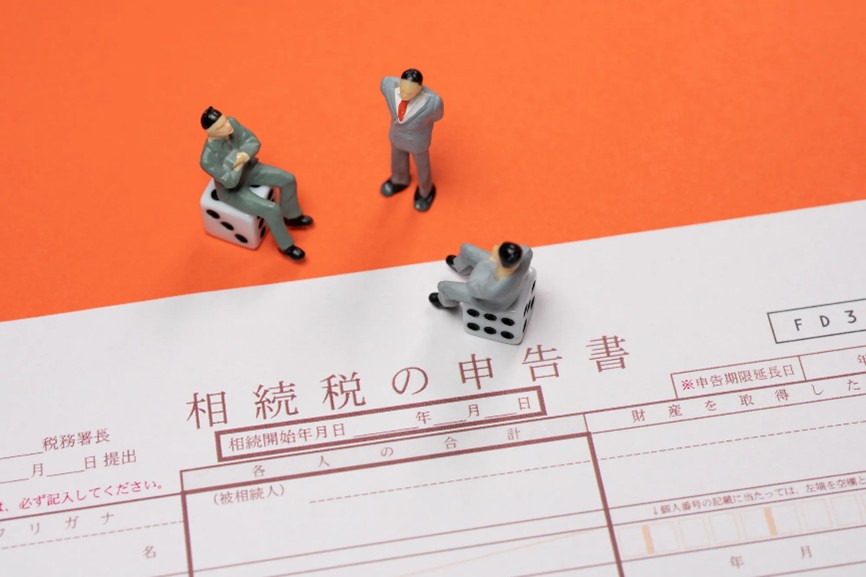
相続税の税務調査は他の税目に比べて実施率が高く、申告全体の約20%が調査対象になるとも言われています。令和5事務年度の国税庁統計によれば、実地調査件数は前年から増加し前年比104.4%、追徴税額も前年比109.8%と伸びており、近年は特に調査強化の傾向が鮮明です。
国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況 」1ページ
また、相続税の調査では無申告事案や海外資産を含む案件への注力度が高まっています。海外に多くの資産を保有する富裕層は、その所在や移動履歴を明確にし、適正な申告を行うことが不可欠です。
このように、相続税の税務調査は対象者の規模や申告内容、資産の特性に応じて厳格化が進んでおり、事前準備と専門的なサポートの活用が調査リスクを軽減する鍵となります。
相続税の税務調査が入りやすい時期
相続税の税務調査は、申告期限から1~2年後に行われることが多いとされますが、必ずしもその時期に限られるわけではありません。実際の調査時期は、事前の書類審査や内部資料の確認を経て決定されるため、申告直後に訪問を受けるケースはまれです。
また、税務署の年間スケジュールから見ると、実地調査が集中しやすい時期があります。確定申告業務で多忙な2~5月や、人事異動直後の7月は調査件数が少ない一方、8~11月は比較的余裕があり、調査が行われやすい傾向があります。
相続税で混同しやすい3年・5年・7年の意味
相続税における「3年」「5年」「7年」という期間は、それぞれ異なる制度や期限を指すため、混同しやすい点に注意が必要です。制度理解を深めるために、次のポイントを押さえておきましょう。
- 生前贈与加算の対象期間は3年から7年に延長される
- 相続税の時効には5年と7年の2つのケースがある
生前贈与加算は3年から7年へ
生前贈与加算とは、被相続人が死亡する前の一定期間に行われた贈与財産を相続財産に合算して課税する制度です。
従来は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から段階的に加算期間が延長され、2031年1月1日以降に開始する相続では7年以内の贈与が対象となります。
この制度は、死亡直前の贈与による課税回避を防ぎ、税負担の公平性を保つことを目的としています。また、相続開始前4年から7年以内の贈与については、その総額から100万円を差し引いた額が加算対象となります。なお、贈与税をすでに納付している場合は、その税額が相続税から控除されるため、二重課税にはなりません。
相続税の時効は5年または7年
相続税の時効は、原則として法定申告期限の翌日から5年と定められています。法定申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月後であり、その翌日から起算して5年が経過すると国の課税権は消滅します。
ただし、財産の隠匿や書類の改ざんなど悪質な行為があった場合は、時効期間が7年に延長されます。この延長は脱税や隠ぺい行為を防ぐために設けられています。
時効を狙って放置するのは極めてリスクが高く、税務署は不動産や金融機関の情報を把握しているため、無申告や申告漏れは高い確率で発見されます。時効成立前に申告漏れが判明した場合は、速やかに期限後申告を行い、延滞税や加算税といった負担を最小限に抑えることが可能です。
相続税の税務調査を避けるためにできる対策

相続税の税務調査を回避するためには、正確な申告と情報の透明性を確保することが不可欠です。特に、次の3点を意識すると効果的です。
- 正確な相続税申告を行う
- 贈与や財産整理の経緯を証明できる記録を残す
- 相続税申告に精通した税理士へ早期に相談する
正しい相続税申告を心がける
正確な相続税申告を行うには、被相続人が保有していたすべての資産を漏れなく把握し、財産評価や各種控除の適用を適切に行うことが欠かせません。評価額や控除額の計算に誤りがあると、税務署のチェック対象となる可能性が高まります。特に未成年者控除など基礎控除以外の控除や小規模宅地等の特例を活用する場合には、制度や法令に対する正確な知識が必要です。
相続前の贈与・財産整理は記録を残すことが重要
相続開始前から計画的に贈与や財産整理を行うことは、課税額の軽減だけでなく申告内容の透明性確保にも有効です。適切な資産移転は、将来の申告負担を減らし、税務署からの不必要な疑念を避ける助けとなります。
また、生前贈与を行った場合は、契約書や贈与日を明記した振込記録などを必ず保管しておくことが重要です。これらは税務調査時に贈与の正当性を証明する裏付け資料として不可欠です。
さらに、資産の変動や贈与履歴を一覧で整理しておけば、相続時の申告が円滑になり、計算や記載ミスによる余計な調査リスクを大幅に減らせます。日常的な記録管理は、適正な相続税申告を行い、調査リスクを軽減するための基盤となります。
相続税申告専門の税理士に相談する
相続税申告に強い税理士へ依頼すれば、法令や通達に基づいた正確な評価・計算が行われ、申告書にも税理士の署名が加わることで税務署からの信用が高まります。特に経験豊富な税理士であれば、複雑な財産構成や海外資産、不動産評価などにも的確に対応可能です。
また、税理士のみが利用できる書面添付制度を活用すれば、申告書が専門家によって検証・評価されたことが明示され、調査対象となる懸念をかなり払拭できます。
さらに、適切な専門家の関与は、財産評価の誤りや控除の適用ミスを防ぎ、追徴課税や延滞税のリスクを大幅に減らします。相続税申告に不安がある場合は、早めに専門税理士へ相談し、状況に応じた最適な申告体制を整えることが重要です。
相続税の税務調査に関するよくある疑問

相続税の税務調査において、特に質問の多い以下の点について順に解説します。
- 少額の申告でも税務調査が行われる可能性はあるのか
- 税務調査では具体的にどのような点が確認されるのか
- 申告内容に誤りが見つかった場合、どのような対応や処分があるのか
少額でも税務調査されることはあるのか
相続税の税務調査は、財産額だけで判断されるものではなく、相続財産が比較的少額であっても対象となる場合があります。
特に、名義預金の疑いや、不自然な資金移動、死亡直前の高額出金などがある場合は、総額にかかわらず調査対象となる可能性が高まります。ただし、実務上は財産総額が2億円以上の高額案件が優先的に調査される傾向が強く見られます。
税務調査では何が見られているか
税務調査では、申告内容の正確性を確認するため、被相続人や相続人の金融取引や財産状況が詳細に調べられます。
特に、被相続人や親族名義の預貯金口座については、入出金履歴を5〜10年分さかのぼって確認され、大きな資金移動や不明な出金があれば使途を問われることがあります。
さらに、生前贈与の有無や現金、貴金属などの動産の保有状況も調査対象となり、名義預金や未申告資産が判明した場合は相続財産に加算されます。
相続税申告内容が間違っていたらどうなるか
相続税申告に誤りがあると、追徴課税の対象となり、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。
税務調査で過少申告が発覚した場合は加算税率が高くなるため、早めに自主的な修正申告を行うことが重要です。
また、申告自体をしていなかった場合には無申告加算税が、偽装や隠ぺいなど悪質な行為があった場合には重加算税が課されます。誤りに気づいた場合は、速やかに正しい税額を算定し、修正申告と納付を行うことが適切です。
富裕層は相続税の税務調査に要注意!専門税理士への相談がおすすめ
資産を多く保有する富裕層にとっては、相続税額が高額になる傾向があり、税務調査の対象となる可能性も高まります。そのため、生前から節税や納税資金の確保、円滑な遺産分割を見据えた対策を講じることが重要です。土地や自社株式など評価の難しい資産をお持ちの場合は、専門家による正確な評価と戦略的な対応が不可欠です。
相続専門の税理士法人レガシィでは、60年の歴史と累計3万件超の申告実績を活かし、富裕層向けの生前対策サービスやコンサルティングを提供しています。
税務調査のリスクを軽減しながら安心して相続を行うためにも、ぜひ一度ご相談ください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













