祭祀財産とは?相続税対策として活用する方法や注意点を解説
Tweet祭祀財産とは、墓地や仏壇、位牌など、祖先を祭るために用いられる特別な財産のことを指します。
この記事では、祭祀財産の具体的な種類や、誰が受け継ぐかの決め方を解説するとともに、相続税対策としての活用方法や注意すべき点についてもご紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
祭祀財産(さいしざいさん)とは
祭祀財産(さいしざいさん)とは、先祖供養を目的として保有・使用される特別な財産のことです。具体的には、仏壇や位牌、墓地、墓石、家系図などが該当します。これらの財産は民法上、通常の相続財産とは異なる扱いを受けるため、相続放棄の対象にはなりません。なお、祭祀財産そのものを放棄することはできませんが、墓じまいなどを通じて供養の方法を見直すことは可能です。
祭祀財産の承継者は原則として1人に限られ、相続とは異なるルールで選定されます。また、祭祀財産の承継者は必ずしも相続人に限られるものではなく、親族以外の人であっても、その資質や事情に応じて承継者として認められることがあります。
相続税対策を考える際には、祭祀財産の特徴や扱いについて正しく理解しておくことが大切です。
祭祀財産の種類
祭祀財産として扱われるものには以下のような種類があります。それぞれ詳しく解説します。
- 墳墓(ふんぼ)
- 祭具(さいぐ)
- 系譜(けいふ)
墳墓(ふんぼ)
墳墓とは、故人の遺体や遺骨を納めるための施設全体を指します。具体的には、墓碑(墓石)や霊屋、埋棺だけでなく、それらを設置するための敷地である墓地も含まれます。ただし、墓地は単なる土地ではなく、「墳墓と社会通念上一体と認められる範囲」に限られるため、あまりに広い土地は墓地には該当しません。
また、墓地は土地の所有権を取得するものではなく、一般的には使用権として代々引き継がれます。さらに、寺院や霊園の敷地内に設けられた永代供養墓なども、場合によっては墳墓に含まれることがあります。
祭具(さいぐ)
祭具とは、仏壇や位牌、神棚、仏像など、故人や先祖を供養する際に使われる礼拝用具の総称です。これらは、特定の宗教や宗派に限らず、広く一般的に使われる供養具も含まれます。祭具は単なる飾りではなく、亡くなった方への敬意や感謝の気持ちを表すという、精神的な意味合いが強いことが特徴です。例えば、盆提灯や十字架なども供養の場で使われるため、祭具に含まれます。
一方で、仏間のように建物の一部として作られた空間は、たとえ仏壇や神棚が置かれていても祭具とはみなされません。
系譜(けいふ)
系譜とは、先祖から子孫へと受け継がれてきた血縁関係や家族の歴史を記録した文書や図表のことです。例えば、家系図や過去帳などの形で保存されており、家族の祭祀や伝統を守るうえで欠かせません。これらの資料は、所有者が加筆や修正をしながら、代々受け継がれてきた貴重な財産です。そのため、終活や相続の準備を進める際には、系譜の記録を正確に保つことが大切です。
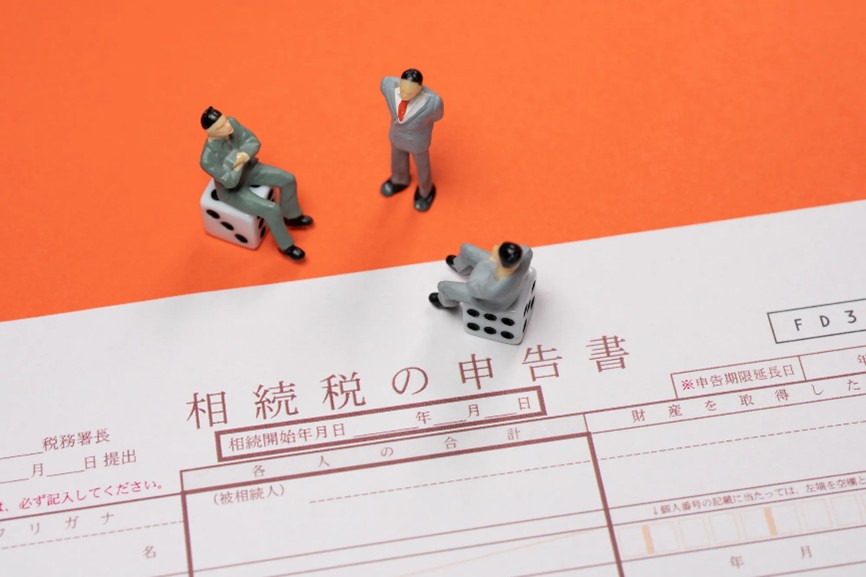
祭祀財産での相続税対策の仕組み
相続税法第12条第1項第2号に基づき、祭祀財産の相続は非課税とされています。そのため、生前に祭祀財産を取得すれば、相続時に課税対象となる現金や預貯金などの財産を減らすことができます。その結果、相続税の負担軽減につなげることが可能です。例えば、あらかじめ墓地や仏壇を用意しておけば、その取得費用に相当する額に対しては、相続税は課税されません。
ただし、内容や金額によっては非課税対象と認められない場合もあります(詳しくは後述します)。また、祭祀財産の購入のために借りたお金(借入金)は、相続税の計算で債務控除の対象にならない点にも注意が必要です。節税のために祭祀財産の活用を考える場合は、専門家に相談することをおすすめします。
祭祀財産の承継者
承継者の選定には法律だけでなく、慣習や被相続人の意思も影響します。ここでは、承継者の決まり方について、以下の3つの観点から解説します。
- 被相続人指定の祭祀主催者
- 慣習に倣った祭祀主催者
- 家庭裁判所による承継者の指定
被相続人指定の祭祀主催者
被相続人が生前に特定の人物を祭祀主催者として指定していた場合、その意思が最も優先されます。指定された人は、祖先の供養を行うだけでなく、仏壇や墓地などの祭祀財産を管理する責任も負います。なお、祭祀主催者の指定方法には法律上の決まりはなく、口頭で伝えるだけでも有効です。
例えば、被相続人である父が生前に長男を祭祀の主催者として明示していた場合、その意思に基づき長男が承継者となります。こしかし、被相続人の意思をはっきりさせ、後々の争いを防ぐためには、遺言書に記載しておくことが望ましいでしょう。
慣習に倣った祭祀主催者
被相続人が誰に祭祀を主催してほしいかを明確に指定していない場合、地域や家系に伝わる慣習に従って、祭祀を引き継ぐ人が決まることがあります。例えば、長男が祭祀主催者とされる地域もありますが、一般的には、故人の子や配偶者など、近い親族が祭祀主催者となるケースが多く見受けられます。
ただし、現在の法律では、こうした慣習が法的な効力を持つことはほとんどありません。実際の手続きでは、慣習はあくまで参考程度に扱われるのが現状です。そのため、祭祀財産やその承継について考えるときは、慣習だけに頼るのではなく、遺言の作成や生前の意思表示などによって被相続人の希望を明確にしておくことが大切です。
家庭裁判所による承継者の指定
被相続人による指定や慣習が明確でなく、かつ祭祀財産の承継者をめぐり相続人間で争いが発生することもあります。このような場合、家庭裁判所は申立てを受けて、故人との関係性や祭祀への関心、経済的状況などを総合的に考慮したうえで、適任者を判断・指定します。このような裁判所の関与は、相続人間の協議が整わない場合の最終的な手続きと位置づけられます。

祭祀財産での相続税対策の注意点
祭祀財産は相続税の非課税対象となりますが、著しく高額なものを購入する際には注意が必要です。例えば、純金製の仏具や骨董的な価値を持つ仏像など、資産価値や換金性が高いと判断されうるものについては、宗教的儀礼のためではなく投資や資産保全を目的とした取得とみなされ、非課税の適用対象外となる可能性があります。
そもそも祭祀財産が非課税とされているのは、先祖供養のために日常的に使われるという性質があるからです。そのため、本来の目的や実際の使用がともなわず、不自然に高価なものを購入した場合には、税務署から課税逃れと指摘されるリスクがあります。
したがって、相続税対策のひとつとして祭祀財産を検討する場合は、「本当に祭祀に必要なものかどうか」という視点を忘れずに持つことが重要です。また、購入前には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
祭祀財産を活用した相続税対策は専門家に相談しよう
祭祀財産とは、墓地や仏壇など先祖供養のための特別な財産で、相続税法上は非課税財産として取り扱われます。そのため、生前に墓地や仏壇を取得することで、相続の際に課税対象となる財産を減らし、相続税の軽減につなげることが可能です。
ただし、取得する仏壇等が著しく高額である場合には、宗教的・儀礼的な目的を逸脱していると判断され、課税対象とみなされる可能性があります。したがって、祭祀財産の取得にあたっては、その実質的な必要性や用途を慎重に検討することが重要です。祭祀財産を活用した相続税対策をお考えの際は、30年以上にわたり相続専門で歩んできた税理士法人レガシィにぜひお任せください。
創業60年を超えるレガシィにお任せください。
-
累計相続案件実績
32,000件超
2025年10月末時点
-
資産5億円以上の方の
複雑な相続相談件数年間1,096件
2023年11月~2024年10月
-
生前対策・不動産活用・
税務調査対策までワンストップ対応
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表













