コラム
第11回ゴリゴリの相続
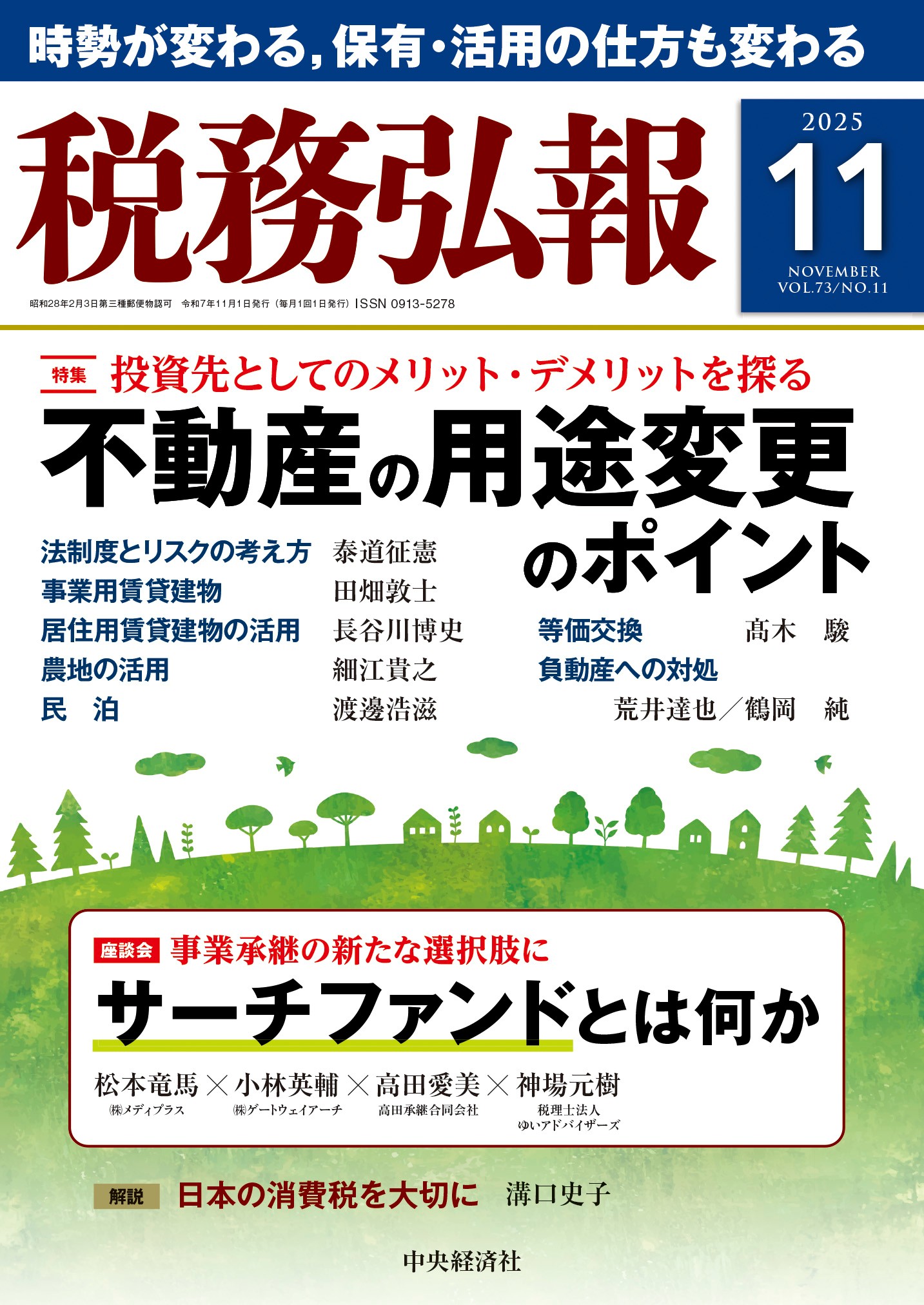
皆様こんにちは。文学研究と相続実務をクロ スオーバーさせる本連載、第11回はバルザッ クの『ゴリオ爺さん』を取り上げます。
この本は19世紀人気小説家のバルザックの 代表作であり、イギリスの文芸評論家サマセッ ト・モームによって世界10大文学にも選ばれ るほど有名な歴史的傑作です。
バルザックは写実主義の系譜に連なり、人間 社会やお金の泥臭さや猥雑さから逃げずに丹念 に描く作家。家族関係を描くことも多く、相続 あるあるがたくさん出てきますが、中でも本作 はその真骨頂。バルザックだけにザックり、い や反対でした、写実主義に敬意を表して丹念に 読み解きます。
ザックりなあらすじ
⑴ 裕福だった元麺製造業者ゴリオは、2人の 娘を溺愛し、娘の結婚後も財産を惜しみなく 与え続けるが、やがて無一文となり安下宿で 余生を送る。
⑵ 娘たちは父を疎んじつつも金を無心し、社 交界で虚栄を追い、同宿の野心家ラスティニャ ックや謎の脱獄囚ヴォートランは金と愛と権 力の相克に巻き込まれる。
⑶ 結局孤独のうちに死んだゴリオの葬儀に娘 は現れない。一方で、墓地に立ったラスティ ニャックはパリを見下ろし「さあ、これから はお前と俺との勝負だ」と社会への挑戦を誓 う。
贈与と教育
生前贈与は相続対策において有効な手段で す。贈与税には暦年贈与や相続時精算課税にお いて非課税枠があり、長期的に行えば相続財産 を減らし節税できます。シミュレーションをき ちんと行えば強力な相続対策になります。
ただし、数字だけで判断すると危ういことも。 贈与する側は感謝を期待し、受ける側はいつし か「当たり前」になりがちです。例えば、仕送 りや住宅資金援助を受け続けた子が自立心を失 うケースは現代でも珍しくありません。
ゴリオも事業家として金銭の功罪を熟知して いたはずですが、娘の表面的な言葉に惑わされ、 「教育的効果」より「今この瞬間の要求に応え ること」を優先してしまった。結果、バランス を欠き、与えすぎてしまったのです。
『リア王』と似ている?
父と娘の表面的な関係が描かれる『ゴリオ爺 さん』は、第1回で取り上げた『リア王』を想 起させます。
リア王は国を3人の娘に分け与える際、口先 だけ美しい長女・次女を信じ、心から愛する三 女を勘当してしまいます。後に真実に気づきま すが、すでに手遅れで発狂し、娘とともに悲劇 的な死を迎えます。
『ゴリオ爺さん』も同じ構図。ただし違うのは、 ゴリオは娘の利己心を薄々知りつつも「いや、 心の底では自分を愛しているはずだ」と信じ続 けたこと。リア王は「愛を疑い、絶望する父」、 ゴリオは「愛を信じ抜く父」と対比できます。
どちらが現代的で幸せか
現代の父親像に近いのはどちらでしょうか? リア王はオラオラ感漂う家父長的な父。「愛 の言葉がなければ贈与しない」という姿勢は現 代ではそぐわないでしょう。
一方ゴリオは娘にぞっこんで、時にバカにさ れながらも尽くし続ける。これは現代日本のお 父さんにも重なる姿です。
では幸せなのは?
リア王は悲劇ですが、最後に三女との誤解が 解け、わずかでも救いがあります。
ゴリオは客観的に見ると「ごめんだ」と思う 境遇です。しかし、それでも尽くせる相手がい ること自体が幸福なのでは? 実務でも、遺言 の付言事項に怒りや恨みがにじんでいても、そ の奥に「最後まで愛していた」気配を感じるこ とが少なくありません。ゴリオもまた、愛を生 き抜いた幸福な父だったのかもしれません。 結果、両者引き分けとしましょう。
母の不在
『ゴリオ爺さん』では様々な登場人物が出てき ます。謎の脱獄囚ヴォートランはとても魅力的 な人物で、他の有名作品にも登場してきます(バ ルザックは人物再登場という手法を発明し、作 品間にまたがって魅力的な人物を活躍させ、読 者を飽きさせませんでした)。ラスティニヤッ クもその一人。社交界での成功を夢見て時には 大博打を打つことも考える人物ですが、ゴリオ のことも心配してくれます。
しかし、この連載で毎回注目している「あの 人」が登場人物としていません。そう、「母」 です。
ゴリオ爺さんに配偶者、つまり二人の娘にと って母がいればどうだったでしょうか?父の暴 走的な愛情による贈与や、娘の表面的な言葉に 早く気づけたでしょう。調整役がいれば、安宿 での孤独死や葬儀の無関心といった悲劇は避け られたかもしれません。
『リア王』も『カラマーゾフの兄弟』も母が見 事に描かれていません。ちょっとした描写もな く完全に未亡人として完膚なきまでに描かれて いません。なぜなら相続でキーパーソンである 母がいてしまうと相続が円満に行われ小説とし ての悲劇が起こらないからです。
バルザックも母で悩む
作者のバルザック自身はというと、実の母に は苦しめられました。冷淡で厳しく、幼い彼を 寄宿舎に預けて愛情を与えませんでした。その 経験が「母性の不在」や「愛を求める父子関係」 として作品に反映されています。
現実の相続でも母が早くに亡くなっている家 庭は少なくありません。その場合にすることは 「母的な存在を作ること」です。実の母でなく ても、調整役・緩衝役となる人がいれば、相続 は円満化に近づきます。ラスティニャックがゴ リオを気遣ったように、専門家もまた「母的存 在」として支える役割を担えるのです。
ラスティニャックの野望とは?
ゴリオの葬儀に出たラスティニヤックが物語 のラストで「今度は、俺とお前の一騎打ちの勝 負だぞ!」と叫びます。これは文学史上有名な フレーズですが、なぜこう叫んだのでしょう?
一般的にはゴリオの悲劇を悼み、復讐も兼ね て社交界で成功することへの決意表明でしょ う。しかし相続的な観点でみると、自分こそは しっかり家庭を築き、配偶者と健やかに暮らし、 息子や娘を立派に育てたいという決意かもしれ ません。そういう意味でラスティニャックは、 父でありながら「母」の役割も担う存在になろ うとしていたのです。まさに調整役のお手伝い する士業の役割とも重なります。
※本内容は「税務弘報 2025年11月号」に掲載されています。








