コラム
第9回利己と利他の間~『源氏物語』が教える家督マネジメント
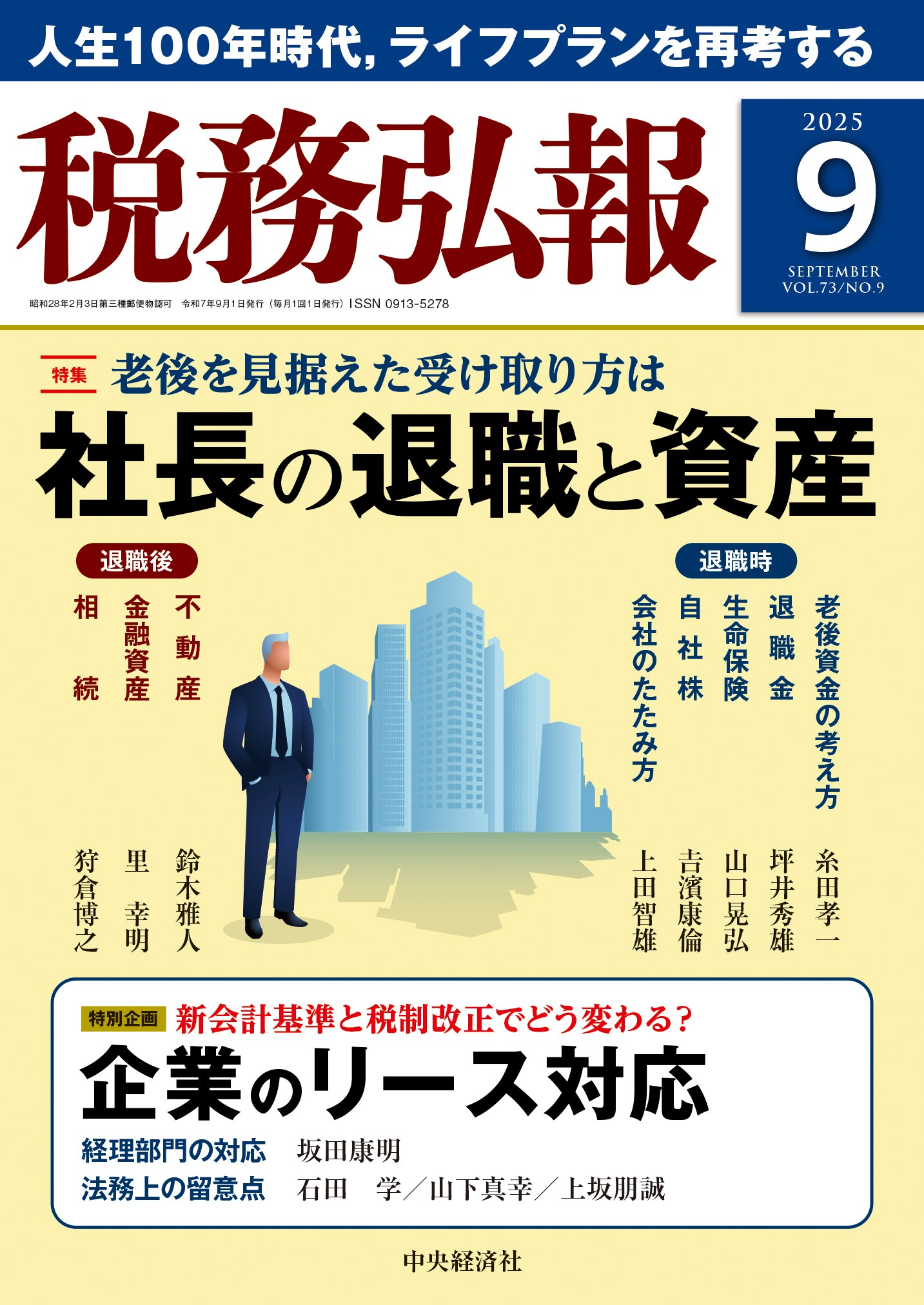
この連載は、私が大学・大学院時代に研究した「文学」を素材に、実務の現場で活かせる「相続の知恵」を掘り下げています。第9回は『源氏物語』。世界文学としても名高く、2024年には大河ドラマ『光る君へ』でもヒロインとして描かれた紫式部の大傑作ですが、“家を保つ”という相続的視点で読んでみると意外な示唆が詰まっています。以前YouTube「相続と文学」で光源氏編・紫の上編の2本動画を公開しました。今回は誌面向けに内容を深掘りし、「利己的利他」というキーワードで家督観を読み解きます。
家督小説として読む
物語は約1,000頁、男女合わせて300人以上が登場しますが、要は「貴族社会で家をどう残すか」が骨格です。第一部は光源氏の青年期と出世、第二部は中年期の栄華と翳り、第三部(宇治十帖)は子・孫世代へ舞台が移ります。平安貴族にとって家とは家屋敷だけでなく、位階・后妃としての縁・血脈、そして儀礼文化までも含んだ複合資産でした。
源氏の目線から物語を眺め直すと、藤壺中宮への傾倒も、紫の上の保護も、明石の君との縁組も、すべては「家督を伸ばす投資とリスクヘッジ」に読めます。ただしその手法は、父帝の后との密通、幼女の早期囲い込み、政略結婚の強行など、現代的倫理からみると危ういものばかり。だからこそ利己と利他が複雑に絡み合い、読者は千年後も「光源氏は善人か悪人か」で揺れ続けるように思います。
変えられない過去を変える罪
源氏の利己性を最も端的に表すのは、亡母・桐壺更衣の面影を藤壺に求めた禁断の恋です。父帝の后に手を出すことは、当時の感覚でも明確な禁忌。しかも生まれた皇子(冷泉帝)は公式には帝の御子として即位。血の真実を隠匿して王位を継がせる行為は、家の栄光と裏腹に「いずれ露見しかねない負債」を同時に抱き込みました。いわば相続実務でいう、未分割のまま帰属が曖昧な財産を外形上だけ誰かに帰してしまうようなもの。のちの宇治十帖で薫が「自分は誰の子なのか」と苦悩するのは、まさにこの負債の利息を払わされる世代交代ドラマです。
養育という長期投資・教育信託
ところが同じ人物が、子どもの教育になると驚くほど遠大な視野を持ちます。
紫の上を引き取り、躾・書道・和歌・管弦すべて直伝し、最終的に后妃並みの教養を授けた経緯は人的資本形成の典型。紫の上は、実子を持てなかったものの、後見人として多数の姫君を養育し、家を円で囲うクッション役になります。
例えば、明石の姫君は地方生まれゆえ身分が低いのですが、源氏はその潜在力を見抜き、「都で磨きを掛ければ皇太子妃に届く」と紫の上へ託します。結果、第三皇子の后となり、外戚・光源氏の政治基盤は磐石に。いわば相続した田畑を見かけだけで判断して売らずにしっかり育てて大きな穣を得るわけです。
また、夕霧には「世に出る前に学問を積め」と大学寮へ送り込みます。平安貴族の長男は家司任せで楽隠居も珍しくないなか、源氏は身分より能力を重んじる現代的な教育方針を導入し、夕霧は公卿の才媛たちから一目置かれる有能官僚に成長します。
このように養育を、家を長持ちさせる投資と捉える姿勢は、相続対策でよく出る教育資金一括贈与や後継者MBA派遣と発想が重なります。
紫の上は許して抱え込む緩衝材
紫の上は育てられる側から育てる側に回った 稀有なヒロインです。自分に子が無い宿命を嘆 くより、明石の姫君や女三の宮の皇子・王女た ちを受け入れ、母としての役を全うする。嫉妬 心が無いわけではありませんが、家益が個人感 情を上回る瞬間、彼女は許すことを選ぶ。この 「許す力」が、源氏家を内部崩壊から守るバッ ファーになります。
臨終の場面で紫の上は、涙ぐむ匂宮(明石中 宮の子)に「大きくなったらこの邸に住んで庭 の梅と桜を忘れずに見てね。仏様にもお供えし てね」と言い残します。これを現代の遺言でい えば、法的効力はないものの感情を受け継がせ る付言事項です。金額よりも思いを可視化する 効果は大きく、相続現場でも、付言事項のおか げで兄弟喧嘩が収まるケースはしばしばありま す。
家督のタネが光と陰を同時に結ぶ
源氏亡き後、舞台は子世代・孫世代に。
夕霧は父の理念どおり学識官僚として出世、 帝の外戚ラインを盤石に固め「光」を体現しま す。一方で薫は出生の秘密(実父は柏木)を背 負い心の平安を得られず、「自分は誰の子か」 というアイデンティティ不全に苦しむ「陰」。
匂宮は美貌と権勢を武器にプレイボーイぶり を発揮し、浮舟事件で薫と三角関係を繰り広げ ます。浮舟は入水未遂、薫は恋と信仰の板挟み で煩悶、匂宮は責任を取らぬまま。ここに源氏 特有の色好み遺伝子が再演されます。
家督戦略の成功(夕霧ライン)と、恋愛リス クの負債(薫・匂宮ライン)が併存する構造は、 事業承継で「本業は伸びたが、オーナー家の私 生活が倫理を逸脱して炎上」というケースに酷 似します。相続計画は数字の勘定だけでなく、 感情も並行して、いやそれ以上に処理せねばな らないと教えてくれるわけです。
現代実務への五つの示唆
1.欠損を完全に帳消しはできない
源氏が禁忌を犯しても母の不在は埋まらなか ったように、実務でも「相続争いをゼロに戻す 魔法」はないのです。過去は受け止め、次善策 に注力するほかないように思います。
2.教育は最大の相続財産
お金を生前贈与するより、後継者の人的資本 を底上げする投資のほうが、複利が効きます。
3.『母』を設置
母的な役割を担った紫の上が家内の潤滑油だ ったように、信頼できる第三者(士業)が親族 間のクッションになります。
4.付言事項で「言葉の遺産」を残す
漠然とした「感謝」「謝罪」「願い」を文章に 起こす作業は、残す側の内省にもなります。
5.利己と利他の二面性を自覚する
家を守る利他、自己実現の利己。双方を天秤 に掛け、「利己で動き、利他で補正」という源 氏的バランスを設計図に落とし込むことが、長 期的には最も合理的に思われます。
相続において狭義の個人主義が当たり前にな る昨今、『源氏物語』に表われる利他的な考え を鑑み、揉めない相続を目指していくのが現代 的なウェルビーイングに感じます。
※本内容は「税務弘報 2025年9月号」に掲載されています。








