コラム
第8回『こころ』の謎は「相続の赦し」で解ける
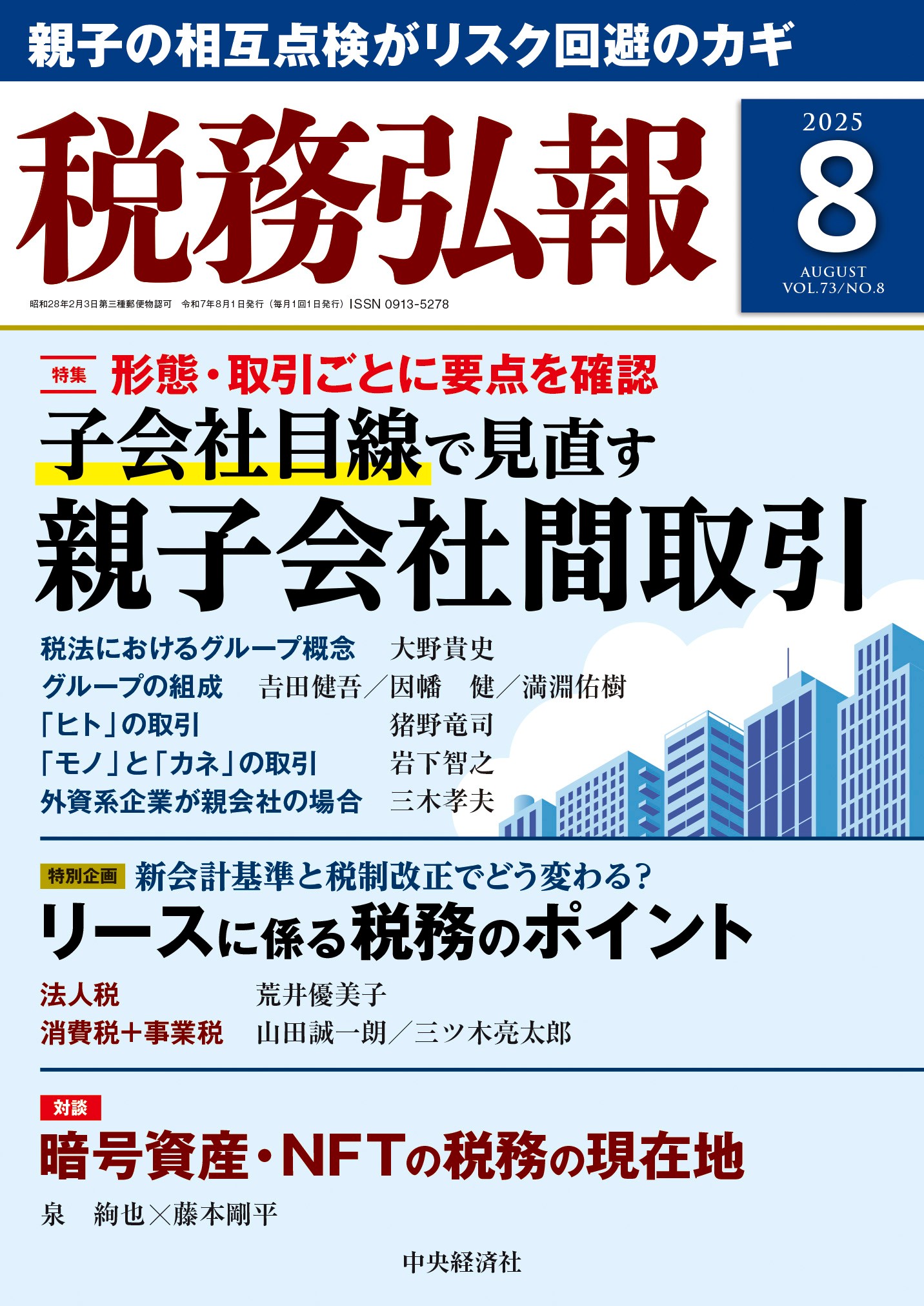
この連載は、私が大学・大学院時代に研究した「文学」を素材に、実務の現場で活かせる「相続の知恵」を掘り下げています。第8回目は『こころ』。高校生の頃国語の教科書に一部掲載されていて読んだ方も多いかと思います。本作には、遺産・遺言・赦しという“相続の三要素”が濃縮されており、明治の青春小説にとどまらない現代的示唆を放っています。私のYouTubeチャンネル「相続と文学」でも紹介しています。
心許ない『こころ』
まずは簡単なあらすじを紹介します。
⑴ 「先生」と呼ばれる謎めいた人物と大学生の「私」が鎌倉の海で出会う。親しくなるにつれ、先生は「私」に対し人間不信と厭世観を語りはじめる。
⑵ 先生が孤独になった発端には、大学生の頃に大地主の父と母を続けて亡くした際、叔父による財産横領があった。父の遺した遺産管理を頼んだ叔父が不当な手段で利得を得たことで、先生は“赦せぬ心”を抱え、人間不信に陥る。
⑶ 先生はその後親友Kと下宿先のお嬢さんをめぐり複雑な三角関係に。先生は叔父にだまされた体験を重ねたのか、恋愛で負けまいとKを出し抜き求婚する。Kは自殺する。
⑷ 明治天皇崩御、乃木将軍の殉死に触発され、先生は「私」に長い遺書を送り自死を選ぶ。
いかがでしょう? かなり暗い内容ですが、このあらすじだけでも相続がポイントのように思えますよね。ただいろんな研究書や論文を読んでも「明治の精神」論や同性愛的解説は多いものの、肝心の「相続」を切り口にした解読がないのが不思議なところです。
叔父を許せなかった先生
『こころ』の解読では、なぜ先生は自殺してしまったのか、が問われることが多いです。先述のとおり、その発端は叔父の財産横領ですが、さらにその原因にあるのは両親の相続です。先生の財産は本来、父から先生へとスムーズに承継されるはずでした。しかし遺産を管理する叔父が最初は優しく手を差し伸べながらも実質的に財産を自己の管理下に。自分の娘とも結婚させようと画策します。先生は法的手段より“絶 縁”を選び、感情の凍結を続けたまま青春を閉ざします。ここに相続トラブルがもたらす最悪の副作用である不信・孤立・自己嫌悪が凝縮されます。
許しを欠いた恋愛相続
財産の損失額そのものは訴訟で取り戻せたかもしれません。だが先生は悪い意味で“勘定”よりも“感情”を重視し、結果的に感情を抑圧したまま生き続けました。一見訴えなかったことで赦しているように見えて、その実本当に赦せなかったからこそ閉じこもってしまったわけです。その抑圧が友人Kと下宿人のお嬢さんである静との三角関係で再燃。恋愛において今度は自分が裏切りを実行し、皮肉にも叔父の裏切りを相続してしまう事態に陥ります。
遺書は赦しのシナリオだったか
先生が語り手の「私」に宛てた遺書は一見、告白と懺悔のモノローグのみで終わるかに見えます。しかし文末の「私の過去を善悪ともに他(ひと)の参考に供するつもりです」という言葉は、叔父を赦し切れなかった自分とは逆に、“許しの相続”を「私」に託したメッセージとも読めます。岩波文庫版にして分量144頁分ものこの遺書は一体何なのでしょうか? それを遺言の「付言事項」(遺言書にその意味や思いを付加できるもの。法律上効力はないが感情に訴えやすく伝わりやすい言葉)と捉えるとどうでしょう?そこには「数字を写す遺言」の補足ではなく、数字にもその説明にも表しきれない「心を写す遺言」の先駆けが見て取れます。
父の遺産を前に揺れる『私』
小説の構成としては中盤に(時系列的には最後)、語り手である「私」の田舎の父が危篤となり、きょうだい(兄、自分、妹)間の遺産配分の気配が漂います。以前先生が散歩中「君のうちに財産があるなら、今のうちに能く始末をつけてもらって置かないと不可いと思う」「君の御父さんが達者なうちに、貰うものはちゃんと貰って置くようにしたらどうですか」「万一の事があったあとで、一番面倒の起るのは財産 の問題だから」と言っていたのも思い出します。漱石はここで先生から私への“心の承継”と実家の“財産承継”を同時進行させ、読者に「勘定と感情の両立」を問います。先生の遺書を読んだ私が取るべき行動は、「赦せる相続」を実践することに他なりません。ただ、実際の小説ではどんな相続を「私」がしたかは描かれていません。読者の想像力に委ねられています。
赦しのキーパンソンである母
ここまで相続で必要なのは「赦し」であることを『こころ』を通して解説してきました。先生が両親からの相続で叔父に騙されたことを精神的な意味で「赦す」ことができれば、世間やKや自分を赦すことができ、その後の悲劇が起こらなかったのかもしれません。しかし起こってしまったものはしょうがなく、未来ある「私」に託したわけでした。
この連載でも「赦し」のテーマは何度か取り上げてきましたが、ポイントとしていつも「母」の存在を挙げていました。「母」がいる場合は、母が一喝するために、また母を守るために赦せたりするが、「母」がいないと相続でモメてトラブルになる、というものです。
さて、『こころ』ではどうでしょうか? 先生は実の父と母を両方同じ病気で同じタイミングで亡くしてしまいます。母不在です。Kも養家に見放され実家からも勘当を受けて母不在です。先生が恋する下宿のお嬢さんは逆に軍人未亡人の母しかいないが、その母を結婚後すぐに亡くします。語り手である「私」の母は、先生に就職口を見つけてもらったら? と促すような、かなり世間的なお母さんです。登場人物の中で唯一「母」として健在。ここに希望の光が見えます。つまりこの「私」の家の相続は、お互い譲り合って、そして赦し合ってモメずに着地する予感を感じさせます。
作者の夏目漱石はどうだったのでしょうか? 『こころ』の直後に書いた随筆集『硝子戸の中』でも書かれているとおり、両親が高齢の時に生まれた末っ子。すぐに養子に預けられるも養父母が良い人ではなくひどい扱いを受けて実家へ帰ってきます。しかし養父は大人になって成功した漱石を頼って財産をせびりに来ます。家の財産問題で大いに悩んだのでこのような相続をテーマとした傑作が生まれたのでしょう。
※本内容は「税務弘報 2025年8月号」に掲載されています。








