「朝5時、まだ家族は眠っている——今日も自分だけの勉強時間が始まる。」
これは、フルタイムで働きながら税理士試験に挑戦している社会人のある一日の始まりです。「毎日仕事が忙しくて勉強時間が確保できない」「何年かかるか分からない試験に、今から挑戦していいのか不安」——そんな悩みを抱えながらも、多くの方が税理士を目指して一歩を踏み出しています。
本記事では、働きながら税理士を目指す方に向けて、試験の全体像から効率的な勉強法、科目選びの戦略まで、現役税理士の視点でわかりやすく解説します。
受験資格の緩和や学習サービスの充実によって、社会人にとっても税理士資格は「現実的に目指せる選択肢」になりつつあります。
限られた時間の中でも合格を狙える学習プランや時間管理術、さらに科目別の攻略ポイントまで、実践的な内容を多数ご紹介。この記事が、あなたの新しいキャリアの第一歩となるきっかけになれば幸いです。
社会人が税理士試験に挑戦する際の基本知識
税理士試験に挑戦する前に、資格取得までの道のりや試験の全体像を把握しておくことが重要です。このセクションでは、税理士を目指す上で知っておきたい基本情報を解説します!
税理士資格取得の主なルート
税理士になるためには、主に以下のルートがあります。最も一般的なのは、税理士試験に合格し、実務経験を積むルートです。
オンライン資格学習サービスのスタディングによると、社会人が税理士になる方法としては、以下のものが考えられます。
- 税理士試験5科目合格+2年以上の実務経験
- 大学院修了+試験合格(一部免除)+2年以上の実務経験
- 弁護士・公認会計士資格保有
- 税務署で23年以上勤務
税理士試験の科目構成と特徴
税理士試験は複数の科目から構成されており、科目合格制を採用しています。つまり、一度合格した科目は生涯有効であり、残りの科目のみ合格すればよいという特徴があります。
科目は以下のように区分されています。
| 科目区分 | 科目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 必須科目 | 簿記論、財務諸表論 | 会計科目2科目必須 |
| 選択必須科目 | 法人税法、所得税法 | いずれか1科目以上 |
| 選択科目 | 相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税 | 残りの科目から選択し、合計5科目になることが必須 |
参考:国税庁┃税理士試験の概要
受験資格の緩和(令和5年度以降)
国税庁によると令和5年度から税理士試験の受験資格が緩和され、会計科目については誰でも受験可能になりました。この緩和によって、税理士試験挑戦へのハードルが下がっています。
社会人が働きながら税理士試験に合格できるのか
多くの社会人が「働きながら税理士試験に合格できるのか」という疑問を持っています。結論から言えば、働きながらでも合格は可能です。
合格者の実態と両立の可能性
実際に、多忙な仕事や育児をしながらも税理士試験に合格した方は数多くいます。重要なのは、効率的な時間確保と継続的な学習習慣の確立です。
働きながら合格を目指す場合、日々のスキマ時間をどれだけ有効活用できるかが鍵となります。通勤時間の活用、音声教材の利用、朝の2時間学習など、自分のライフスタイルに合わせた学習パターンを見つけることが重要です。
必要な勉強時間と科目別の目安
税理士試験に合格するためには、科目ごとに適切な勉強時間を確保する必要があります。各科目の勉強時間の目安は以下の通りです(合格率は年度によって異なるため参考として)。
科目によって必要な勉強時間は異なるため、自分の状況に合わせた計画を立てることが重要です。
| 科目 | 勉強時間(目安) | 理論・計算比率(例) | 合格率(令和6年度) |
|---|---|---|---|
| 簿記論 | 450時間 | 理論0%・計算100% | 17.4% |
| 財務諸表論 | 450時間 | 理論50%・計算50% | 8.0% |
| 所得税法 | 650時間 | 理論50%・計算50% | 12.6% |
| 法人税法 | 650時間 | 理論50%・計算50% | 16.4% |
| 相続税法 | 450時間 | 理論50%・計算50% | 18.7% |
| 消費税法 | 300時間 | 理論50%・計算50% | 10.3% |
| 酒税法 | 150時間 | 理論40%・計算60% | 12.1% |
| 国税徴収法 | 150時間 | 理論0%・計算100% | 13.0% |
| 住民税 | 200時間 | 理論50%・計算50% | 18.2% |
| 事業税 | 200時間 | 理論50%・計算50% | 13.7% |
| 固定資産税 | 250時間 | 理論50%・計算50% | 18.0% |
参考:スタディング|社会人が税理士になるには?働きながら短期合格を実現する勉強法
社会人が知るべき科目選択の戦略と注意点
税理士試験における科目選択は、合格への近道を左右する重要な戦略です。単に勉強時間の短さだけで選ぶのではなく、様々な要素を考慮することが大切です!
科目選択の基本的な考え方
科目選択は単純に勉強時間だけで決めるべきではありません。勉強時間が短い科目はライバルも多く、合格ラインが高くなる傾向があります。
科目選択では、将来の実務で役立つ分野を基準に選ぶことも重要です。特に法人税法、相続税法、消費税法は実務でよく活用される分野であり、将来的な仕事の幅を広げることにつながります。
将来のキャリアを考慮した科目選択
たとえば、将来独立開業を目指す場合、法人税法の選択がおすすめです。法人顧問が増えることで報酬が安定しやすく、長期的なキャリア形成に役立ちます。
また、相続税法も近年需要が高まっており、専門特化型の事務所を目指す場合に有利な選択肢の1つとなります。自分のキャリアビジョンに合わせて、戦略的に科目選択を行いましょう。
社会人のための効率的な学習方法と時間管理
社会人が税理士試験に合格するためには、限られた時間をいかに効率的に使うかが重要です!このセクションでは、社会人特有の制約を考慮した学習方法を紹介します。
効果的な勉強時間の確保方法
社会人にとって、まとまった勉強時間の確保は常に課題となります。効率的に時間を捻出するためのテクニックを身につけましょう。
通勤時間や昼休み、就寝前や起床後の30分など、「スキマ時間」を有効活用することが社会人の学習成功の鍵です。特に早朝学習は、習慣化することで、仕事の疲れが出る前の集中力の高い時間帯に効率よく学習することができるためおすすめです。
合格に必要な範囲への集中学習法
税理士試験の出題範囲は広いですが、合格に必要な範囲に絞り込むことで、効率的な学習が可能になります。過去問分析を通じて、優先して学ぶべき範囲を特定しましょう。
繰り返し復習で記憶を定着させることも重要です。特に理論科目では、単に暗記するだけでなく、理解して説明できるレベルまで学習することが求められます。
問題演習重視の学習アプローチ
税理士試験では、知識のインプットだけでなく、問題を解く力を養うことが重要です。早い段階からアウトプット練習を取り入れましょう。
本試験形式で時間を決めて問題を解く訓練を繰り返すことで、試験本番での時間管理能力が身につきます。特に計算問題では、素早く正確に解答するためのテクニックを磨くことが合格への近道となります。
科目別の効率的な勉強法と攻略ポイント
税理士試験の各科目には、それぞれ特徴があり、効率的な学習方法も異なります。このセクションでは、主要科目ごとの攻略ポイントを紹介します!
簿記論の効率的な学習法
簿記論は計算問題中心の科目であり、基本的な仕訳から財務諸表作成までの一連の流れを理解することが重要です。基礎をしっかり固めてから応用問題に進むことがポイントです。
学習のステップとしては、まず論点理解、次に簡単な例題演習、そして最後にまとまった問題の反復練習という流れが効果的です。特に合格するためには、素早く正確に計算する力を養うことが不可欠です。
財務諸表論の効率的な学習法
財務諸表論は計算問題と理論問題がバランスよく出題される科目です。まずは計算問題の学習から始め、その後理論の学習に移行するのが効率的です。
理論部分は暗記よりも理解が重要であり、自分の言葉で説明できるレベルまで学習することが合格への近道です。企業会計基準や会社法の変更にも常に注意を払い、最新の情報をキャッチアップすることも忘れないようにしましょう。
法人税法の効率的な学習法
法人税法は理論の正確な理解と素早い計算・集計スキルの両方が求められる科目です。法人税特有の考え方や計算構造をしっかり理解することが重要です。
学習の流れとしては、論点把握→例題演習→問題演習→復習のサイクルを繰り返すことが効果的です。特に計算問題では、制限時間内に解き切るための速さと正確性を両立させる訓練が必要になります。
相続税法の効率的な学習法
相続税法は理論の正確な理解と財産評価・税額計算の速さが求められる科目です。相続税特有の複雑な計算構造を理解することがポイントです。
相続税法では、様々な特例や非課税措置などの知識が問われるため、体系的な理解が重要になります。時間制限内での解答力を鍛えるために、制限時間を設けた問題演習を繰り返し行うことをおすすめします。
社会人税理士のキャリアパス
税理士資格取得後のキャリアについての情報は、試験に挑戦するモチベーションにつながります。
受験者の年齢層と長期キャリアの可能性
意外に思われるかもしれませんが、令和6年度の税理士試験結果によると、41歳以上の受験者が11,543人と最も多くなっています。税理士試験は20歳以下から40代以上まで幅広い年齢層が受験しており、幅広い年代に人気のある資格であることが伺えます。
また、税理士は長期的なキャリア形成が可能な職業であり、60代、70代になっても活躍できる点が魅力の一つです。専門知識を持つプロフェッショナルとして、長く社会に貢献できるキャリアを築くことができます。
まとめ
社会人が税理士試験に合格するには、効率的な学習計画と時間管理、そして適切な科目選択が重要です。働きながらでも、計画的に取り組むことで2〜3年での合格も十分に可能です。
- 社会人が税理士になる主流ルートは「5科目試験合格+実務経験」
- 受験資格の緩和により会計科目は誰でも受験可能に
- スキマ時間活用と問題演習重視の学習が効率的
- 科目選択は勉強時間だけでなく、将来の実務での有用性も考慮すべき
- 年収や受験年齢は幅広く、長期キャリア形成が可能な魅力的な職業
税理士試験への挑戦を検討されている方は、まずは1科目から始めてみることをおすすめします!一歩踏み出すことで、新たなキャリアの扉が開くかもしれません。
———————————————————–
レガシィでは、「Meet Legacy!!」と称した会社説明・座談会を定期的に開催しています。実際に職場環境を見学したり、メンバーとざっくばらんに話ができます。
まずは気軽に見学にお越しください!
▼申し込みはこちら▼
https://legacy.ne.jp/recruit/news/meet-legacy2505


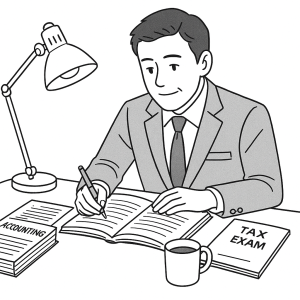
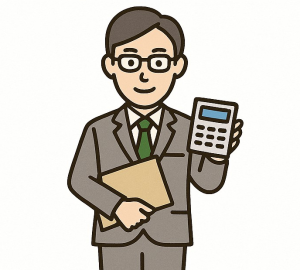
コメント