「税理士になりたい想いはあるけれど、何から始めればいいのかわからない…」そんな不安を抱えていませんか?
実は、税理士試験の準備で最初につまずきがちなのが「受験資格や日程の確認」だったりします。そのため、このポイントを事前に押さえておくことで、学習の計画もスムーズに立てられ、スタートダッシュに大きな差がつきます。しかも、税理士試験は「科目合格制」というユニークな制度があるため、戦略的な準備が合格への近道になるんです。
この記事では、令和7年度(2025年度)の税理士試験の日程や申込みスケジュールはもちろん、受験資格の整理、学習の進め方、そして実務家としてのリアルな視点まで、税理士を目指すすべての方に役立つ情報をたっぷり詰め込みました。
執筆しているのは、相続を中心とした税務を専門に扱う税理士法人レガシィ。現場で新人税理士を多数サポートしてきた実務家だからこそお伝えできる、リアルな声をお届けしていきます。
「まだ大丈夫」ではなく、「今から始める」あなたを応援します。税理士試験に挑む一歩を、この記事から踏み出してみませんか?
令和7年度(2025年度)税理士試験の日程と概要
税理士試験は毎年夏に実施される国家試験です。令和7年度の試験日程を確認し、余裕を持った準備を始めましょう。
令和7年度税理士試験の重要日程
令和7年度の税理士試験は、2025年8月5日(火)から8月7日(木)までの3日間で実施される予定です。この日程に向けて、以下の重要な日程もチェックしておきましょう!
試験の官報公告は2025年4月4日(金)に行われ、受験申込の受付期間は2025年4月21日(月)から5月9日(金)までとなっています。合格発表は2025年11月28日(金)の予定です。申込期間は約3週間と短いため、必要書類の準備は早めに行いましょう!。
試験科目と時間割
税理士試験は各科目120分の試験時間で実施されます。
1日目は簿記論、財務諸表論、消費税法/酒税法が、2日目は法人税法、相続税法、所得税法が、3日目は国税徴収法、固定資産税、住民税/事業税が実施ます。 受験科目に応じて、どの日に試験会場に行く必要があるかを確認しておきましょう。
税理士試験の受験資格と必要条件
税理士試験の受験資格は科目によって異なります。会計学科目は誰でも受験可能ですが、税法科目には一定の条件が必要です。条件を確認し、自分が満たしているかを確認していきましょう!
会計学科目と税法科目の受験資格の違い
税理士試験の科目は大きく会計学科目と税法科目に分かれています。会計学科目である簿記論と財務諸表論については、受験資格が撤廃されているため、誰でも受験することができます。
一方、税法科目(法人税法、所得税法、相続税法など)の受験には、学識(学歴)、資格、職歴のいずれかの条件を満たす必要があります。これらの条件を満たしていない場合は、税法科目を受験することができませんので注意が必要です。
学識(学歴)による受験資格
学歴による受験資格は、主に大学などの高等教育機関での学習経験に基づいています。以下のいずれかに該当する場合、税法科目の受験資格を得ることができます。
- 大学・短大・高専を卒業し、「社会科学に属する科目」を1科目以上履修している
- 大学3年次以上で「社会科学に属する科目」1科目以上を含む62単位以上取得している
- 専門学校で所定の課程を修了し、「社会科学に属する科目」を1科目以上履修している
- 司法試験合格者</li >
社会科学に属する科目には、経済学、商学、法学などが含まれます。成績証明書で該当科目の履修を証明できるようにしておきましょう!
資格による受験資格
特定の資格を取得していることでも、税法科目の受験資格を得ることができます。代表的な資格には以下のものがあります。
- 日商簿記検定1級
- 簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る) など
これらの資格は、一定の会計知識や能力を証明するものとして認められています。資格取得の証明書を保管しておくことが重要です。
職歴による受験資格
実務経験によっても受験資格を得ることができます。主に以下のような職歴が認められています。
- 税理士・公認会計士・弁護士等の事務所での補助業務に2年以上従事
- 企業などでの税務・会計関連業務に2年以上従事
職歴による受験資格を証明するためには、勤務先の証明が必要になります。職歴証明書には、業務内容や期間を具体的に記載してもらうことが重要です。
認定による受験資格の取得方法
上記の学歴・資格・職歴のいずれにも該当しない場合でも、国税審議会による個別認定申請を行うことで受験資格を得られる可能性があります。これは「認定による受験資格」と呼ばれるものです。
例えば、外国の大学を卒業(社会科学に属する科目を履修)した方 や、商工会での経理経験者なども、個別に審査を受けることで受験資格を認められることがあります。認定申請には通常よりも早めの準備が必要ですので、該当する方は余裕を持って手続きを進めましょう。
税理士試験の科目と合格要件
税理士資格を取得するためには、合計5科目に合格する必要があります。科目の選択と組み合わせを理解することで、効率的な対策を行なっていきましょう。
試験科目の構成と選択
税理士試験は、必修科目と選択必須科目から構成されています。税理士資格を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 会計学科目:2科目(簿記論、財務諸表論)
- 税法科目:3科目(法人税法、所得税法、相続税法など)
特に重要なのは、税法科目のうち「法人税法」または「所得税法」のいずれか1科目を必ず含める必要があるという点です。税法科目の選択肢としては、他に相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、事業税、固定資産税、住民税などがあります。
科目合格制度とその活用法
税理士試験の大きな特徴として、「科目合格制度」があります。これは、一度合格した科目については、その合格が生涯有効となる制度です。
1科目ずつ受験し、少しずつ合格科目を増やしていくという長期的な戦略も可能です。例えば、仕事をしながら試験勉強をする場合、毎年1科目ずつ受験するという方法も一般的です。自分のペースで計画的に進めていくことができるのが、この制度の大きなメリットです。
科目選択の戦略と優先順位
効率的に税理士資格を取得するためには、科目選択にも戦略が必要です。一般的には、以下のような優先順位で受験するケースが多いです。
- 税法科目の前に、受験資格がない会計学科目(簿記論・財務諸表論)から始める
- 必須科目である法人税法または所得税法を早めに受験する
- 自分の得意分野や興味のある科目、将来専門としたい分野の科目を選択する
また、実務経験がある場合は、その経験を活かせる科目から受験するのも効果的です。自分の強みと弱みを分析し、合格確率の高い科目から挑戦することで、モチベーションを維持しやすくなります。

税理士試験の申込み手続きと流れ
税理士試験の申込みには、いくつかの手続きと必要書類があります。申込期間が短いため、事前に準備を進めておきましょう!
申込書類の入手方法
税理士試験の申込用紙は、国税局等で交付を受けることができます 。また、郵送による請求も可能です。
申込用紙の配布は、通常、試験の官報公告日(令和7年度は2025年4月4日(金) )以降に開始されます。早めに申込用紙を入手し、必要事項を確認しておくことをおすすめします。国税庁のホームページでも申込みに関する情報が掲載されますので、定期的にチェックしておくとよいでしょう。
必要書類と準備のポイント
税理士試験の申込みには、以下の書類が必要となります。
- 税理士試験受験願書
- 受験票
- 受験資格を証明する書類(成績証明書、資格証明書、職歴証明書など)
- 税理士試験受験申込書(兼写真票)
特に受験資格を証明する書類は、取得に時間がかかる場合があります。例えば、成績証明書は大学等の発行に数週間かかることもあります。また、職歴証明書は勤務先の協力が必要です。これらの書類は、申込期間の前から準備を始めておくことが重要です。
また税法に属する科目受験者、一部科目合格(免除決定)者は別途証明する書類が必要となります。詳しくは「令和7年度(第75回)税理士試験受験案内」を確認してください。
参考:令和7年度(第75回)税理士試験受験案内<https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm>
申込書類の提出方法と注意点
申込書類は、指定された国税局等に提出します。令和7年度の場合、2025年4月21日(月)から5月9日(金)までの間に提出する必要があります。
提出方法には、主に郵送による方法があります。郵送の場合は、期間内の消印が有効となりますが、できるだけ余裕を持って発送することをおすすめします。また、書類の不備があると受理されない場合がありますので、提出前に記入漏れや添付書類の確認を十分に行いましょう。
受験資格がない場合の対策と取得方法
税法科目の受験資格がないと受験できないのか不安になりますよね。他にもいくつかの方法で資格を取得することができるので、自分に適した方法を見つけていきましょう!
簿記検定などの資格取得による対策
受験資格の中で比較的取得しやすいのが、簿記検定などの資格です。特に、日本商工会議所の簿記検定1級や全国経理教育協会の簿記能力検定上級は、税理士試験の受験資格として認められています。
参照:国税庁 受験資格について<https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm>
日商簿記1級 は、年2回実施されているため、計画的に受験することが可能です。簿記の知識は税理士試験の会計学科目にも直結するため、一石二鳥の効果があります。また、これらの資格は就職や転職にも有利に働くことが多いです。
実務経験を積む方法と職場選び
税理士事務所や会計事務所などで働くことで、実務経験による受験資格を得ることも可能です。通算2年以上の経験が必要となりますが、実務を通じて税務や会計の知識を深められるというメリットもあります。
参照:国税庁 受験資格について<https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm>
実務経験を積む際のポイントとしては、以下の点に注意しましょう。
- 税理士、公認会計士、弁護士の事務所など、認められる職場かどうかを確認する
- 業務内容が税務・会計関連業務に該当するかを確認する
- 後日証明を受けられるよう、業務内容や期間の記録を残しておく
実務経験は、試験勉強との両立が可能であり、実践的な知識も身につけられるため、効率的な準備方法といえます。
大学や専門学校での必要科目の履修
大学や専門学校で必要な科目を履修することも、受験資格を得る方法の一つです。特に、社会人向けの通信教育や夜間コースを活用することで、仕事をしながらでも学歴による受験資格を得ることができます。
大学では「社会科学に属する科目」を1科目以上履修することが条件となります。科目履修生として必要な科目だけを受講することも可能な大学もありますので、各教育機関の制度を調査してみるとよいでしょう。
税理士試験の合格率と難易度分析
税理士試験は国家資格の中でも難関とされています。だからこそ合格率や科目別の難易度を理解し、効果的な対策を立てることで、資格取得へと近づいていきましょう。
近年の合格率の推移と傾向
令和6年度の税理士試験全体の合格率は16.6%で、前年の21.7%から減少しています。長期的に見ても、税理士試験の合格率は10%~20%前後で推移しており、難関試験であることがわかります。
参考:令和6年度(第74回)税理士試験結果表<https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/74/kekka/pdf/kekka.pdf>
年度によって若干の変動はありますが、試験の難易度は毎年一定の水準が保たれています。合格率の低さから見ても、十分な準備と計画的な学習が不可欠です。特に、一度に全科目合格を目指すのではなく、科目合格制度を活用した長期的な取り組みが重要となります。
科目別の合格率と難易度比較
令和6年度の科目別合格率を見ると、科目によって難易度に差があることがわかります。なお、以下かっこ内は令和5年度の科目別合格率です。
| 科目名 | 合格率 |
|---|---|
| 簿記論 | 17.4%(23.0%) |
| 財務諸表論 | 8.0%(前年度:14.8%) |
| 相続税法 | 18.7%(前年度:14.2%) |
| 法人税法 | 16.4%(前年度:12.3%) |
科目の合格率は年度によっても異なります。合格率は参考にしつつ、それだけにとらわれない科目選択をしましょう。
年齢層別の合格率と特徴
税理士試験は、年齢によっても合格率に差があります。令和6年度のデータによると、20歳以下の合格率が38.8%と高い一方、41歳以上では8.4%と低くなっています。
若年層の合格率が高い理由としては、学習に専念できる環境や、最新の教育を受けて間もない状態であることなどが考えられます。一方、社会人受験者は仕事との両立が必要なため、効率的な学習方法がより重要になります。年齢が高くなるほど、時間の確保や集中力の維持に工夫が必要ですが、実務経験を活かせる面もありますので、自分の強みを生かした学習計画を立てましょう。
税理士試験合格のための効果的な学習戦略
税理士試験に合格するためには、体系的な学習計画と効果的な学習方法が不可欠です。ここでは具体的な学習戦略を紹介します。
科目別の効果的な学習方法
税理士試験の科目ごとに、効果的な学習アプローチは異なります。会計学科目と税法科目それぞれの特性に合わせた学習方法を採用しましょう。
会計学科目(簿記論・財務諸表論)は、基本概念の理解と計算問題の練習が重要です。特に簿記論は反復練習が効果的であり、毎日少しずつでも問題を解く習慣をつけることが大切です。財務諸表論は理論的な理解も必要となるため、テキストの読み込みと並行して問題演習を行いましょう。
税法科目は、法令の理解と適用が中心となります。法律の条文を単に暗記するのではなく、その背景や趣旨を理解することが重要です。また、税法は頻繁に改正されるため、最新の情報を常にチェックする習慣も必要です。特に法人税法や所得税法は範囲が広いため、体系的に整理しながら学習を進めましょう。
長期的な学習計画の立て方
税理士試験の合格には、通常、長期的な学習計画が必要です。科目合格制度を活用し、無理のないペースで着実に進めていくことが重要です。
長期計画の立て方のポイントは以下の通りです。
- まず受験する科目を決め、その科目に集中する
- 試験日から逆算して、学習のマイルストーンを設定する
- 基本学習、応用学習、問題演習、模擬試験といった段階を設ける
- 定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を調整する
例えば、1年間の学習計画では、最初の3ヶ月で基本的な知識の習得、次の3ヶ月で応用的な内容の学習、その後の3ヶ月で過去問演習、最後の3ヶ月で総復習と模擬試験という流れが一般的です。自分の生活リズムや仕事の忙しさに合わせて、無理のない計画を立てることが継続の秘訣です。
過去問と模擬試験の活用方法
税理士試験対策において、過去問題と模擬試験は非常に重要なツールです。これらを効果的に活用することで、出題傾向の把握や実力チェックが可能になります。
過去問題の活用方法としては、まず学習の初期段階で出題範囲や傾向を把握するために一通り目を通し、その後、各トピックの学習後に関連する過去問を解くという方法があります。直近10年程度の過去問を繰り返し解くことで、頻出論点を押さえることができます。
模擬試験は、本番と同じ時間配分で解くことで、時間管理能力を養うとともに、自分の弱点を発見するのに役立ちます。模擬試験を受けた後は、間違えた問題だけでなく、正解した問題の解法も見直し、より効率的な解き方がないか検討しましょう。多くの受験予備校では、本番前に複数回の模擬試験を実施していますので、積極的に活用するとよいでしょう。
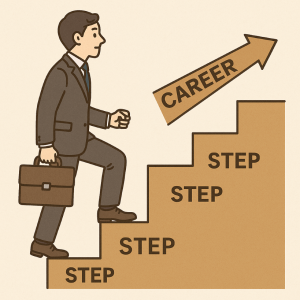
税理士資格取得後のキャリアパスと展望
税理士資格を取得した後には、様々なキャリアパスが広がっています。将来の展望も見据えながら、一緒に資格取得を目指しましょう!
税理士としての活躍の場と可能性
税理士資格は、税務・会計分野における専門家としての道を開きます。主な活躍の場としては、以下のようなものがあります。
- 税理士事務所・税理士法人や会計事務所での勤務
- 独立開業による自身の税理士事務所の経営
- 企業の経理部門や財務部門での専門職
- コンサルティング会社での税務アドバイザー
- 金融機関の資産税部門での相続・事業承継コンサルタント
特に近年は、単なる税務申告のサポートだけでなく、経営コンサルティングや資産運用アドバイス、事業承継対策など、活躍の幅が広がっています。企業の国際化に伴い、国際税務の専門家としてのニーズも高まっています。
税理士会への登録と継続教育
税理士試験に合格した後、実際に税理士として業務を行うためには、税理士会への登録が必要です。登録には、税理士試験合格証書のほか、一定の書類と登録手数料が必要となります。
税理士会に登録すると、継続的な研修や情報提供を受けることができます。税法は毎年改正されるため、最新の知識を常にアップデートすることが重要です。税理士会では定期的な研修が実施されており、これらに積極的に参加することで専門性を高めることができます。また、税理士会のネットワークは、業務上の相談や情報交換の場としても貴重です。
独立開業と就職の比較と選択肢
税理士資格取得後の大きな選択肢として、「独立開業」と「就職」があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分のライフスタイルや目標に合わせて選択することが重要です。
独立開業のメリットは、自分のペースで働ける自由度の高さや、成功すれば高い収入を得られる可能性があることです。一方、顧客開拓の難しさや経営リスク、不安定な収入などのデメリットもあります。
就職のメリットは、安定した収入や福利厚生、先輩税理士からの指導を受けられることなどが挙げられます。特に経験の少ない新人税理士にとっては、まず就職して実務経験を積み、その後独立するというキャリアパスが一般的です。どちらを選ぶにしても、実務経験を通じて専門性を高め、信頼関係を構築していくことが長期的な成功の鍵となります。

まとめ
税理士試験の合格に向けては、体系的な準備と適切な心構えが重要となります。これまでの内容を踏まえ、以下が成功のためのポイントです。
- 会計学科目(簿記論・財務諸表論)は誰でも受験可能
- 税法科目には学歴、資格、職歴などの受験資格が必要
- 税理士資格取得には合計5科目の合格が必要
- 科目合格制度を活用した長期的な計画が効果的
- 過去問題や模擬試験を活用して実践的な対策を行う
税理士資格は、税務・会計のプロフェッショナルとして活躍するための強力な武器となります。難関試験ではありますが、計画的な学習と継続的な努力で必ず道は開けます。令和7年度の税理士試験合格を目指して、今日から準備を始めてみませんか?
——————————————–
レガシィでは毎月、オフィスツアーをかねた会社説明・座談会「Meet Legacy!!」開催しています。実際に職場環境をみつつ、弊社のメンバーとざっくばらんにお話ができます。是非お気軽に見学にきてみてくださいね!申し込みはこちら▼
「Meet Legacy!!」申込フォーム https://legacy.ne.jp/recruit/news/meet-legacy2505

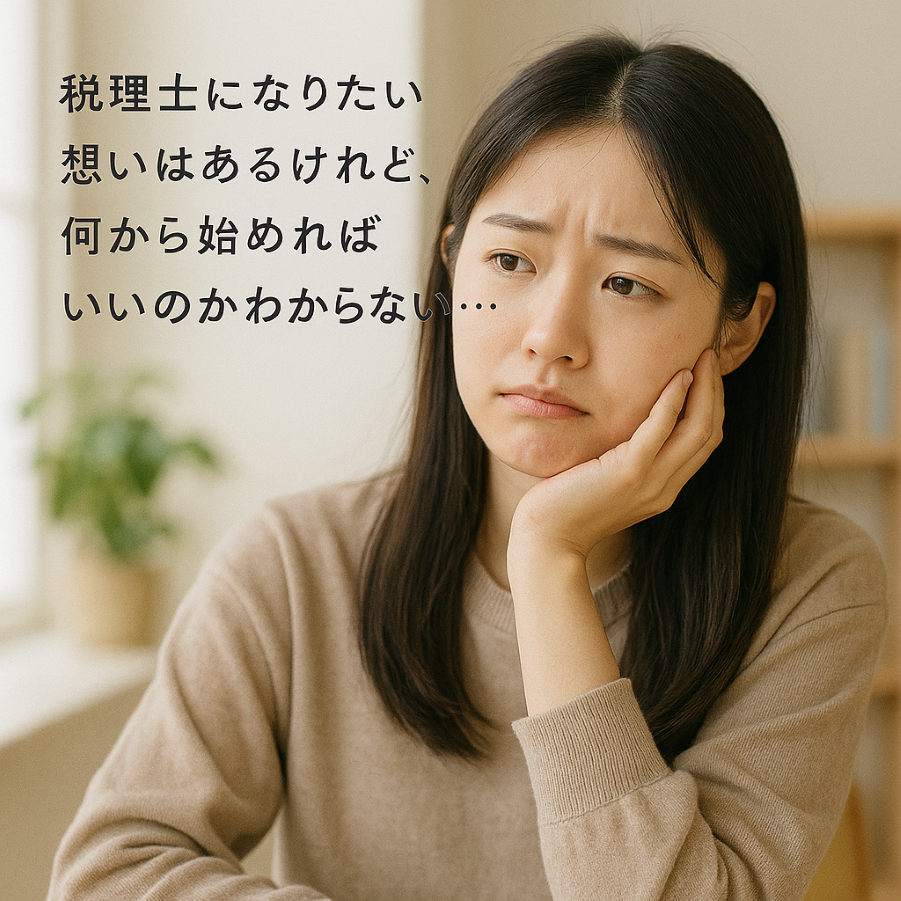
コメント