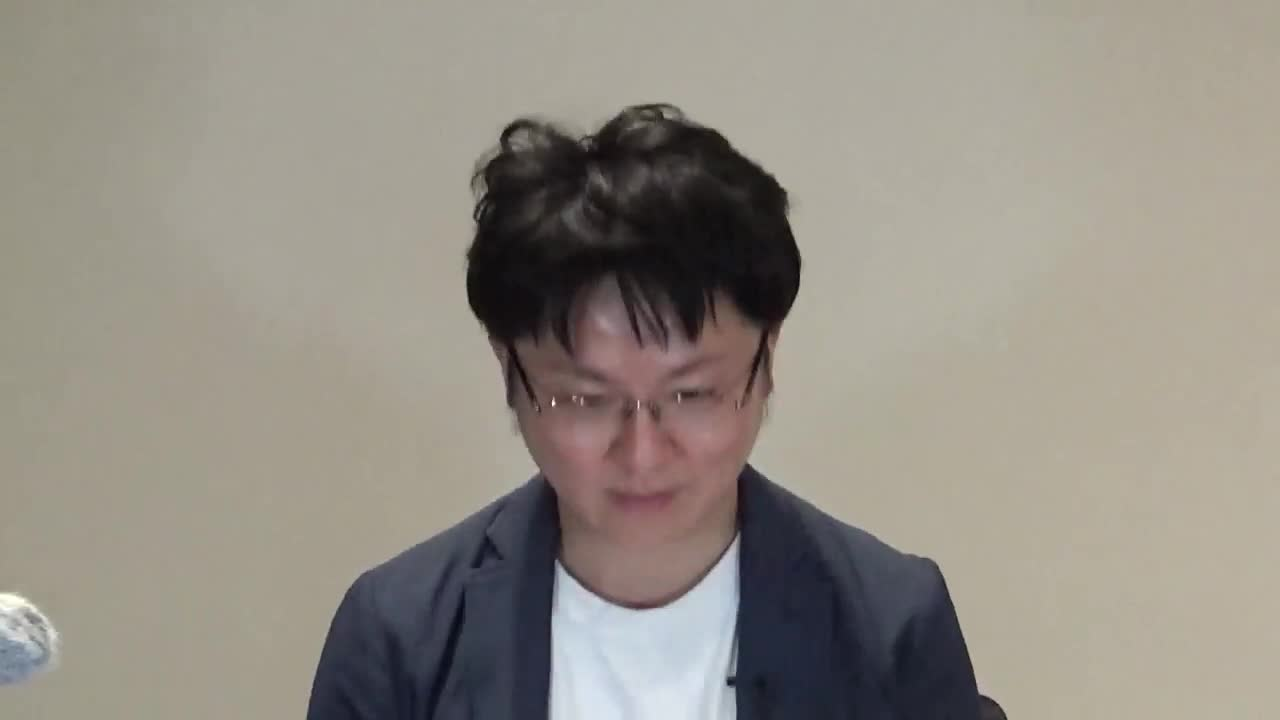レガシィクラウド ナレッジ
【税理士向け】創業融資支援の実務 会計事務所が押さえるべき成功のポイント
会計事務所にとって、新規顧問先の獲得は事業成長の要です。特に、将来の優良な顧問先となりうる創業期の企業をいかにサポートし、信頼関係を築くかは重要な課題と言えるでしょう。その絶好の機会となるのが「創業融資支援」です。
創業期の企業にとって、最大の課題の一つは「資金調達」です。会計事務所として創業者を支援する立場であれば、金融機関の視点や融資制度の特徴を踏まえた適切なサポートが求められます。しかし現場では、融資の基本的な流れや審査基準を十分に理解しないまま手続きを進め、思わぬ壁に直面するケースが少なくありません。
特に金融機関からの融資を円滑に受けられるかどうかは、事業の成否を大きく左右します。
事業計画がどれほど魅力的であっても、資金が調達できなければ計画は実現できません。こうした背景から実施されたのが、今回紹介する「創業融資支援」をテーマとした講演です。
本講演を収録した商品では、初回面談から金融機関同行までの流れを体系的に解説し、実務に直結する知識がわかりやすく整理されています。この記事では、その概要と実務的ポイントを紹介します。
創業融資を取り巻く背景と業界動向
近年、日本では新規開業率の引き上げが重要な政策課題とされており、国や自治体は創業者向けの融資制度を積極的に拡充しています。特に日本政策金融公庫の「新規開業資金」や自治体の制度融資は、創業間もない事業者にとって有力な資金調達手段となっています。
一方で、申請にあたっては事業計画書の完成度や自己資金比率など、金融機関が重視するポイントを押さえる必要があります。会計事務所がこのプロセスを的確にサポートできれば、クライアントにとっては大きな安心材料となり、事務所としても顧問契約や継続的支援につながる可能性が高まります。創業融資支援が「顧問先獲得の第一歩」と位置付けられる所以です。
創業融資支援の基本ステップ
支援者が意識すべき主要なステップは次の通りです。
1. 初回面談・ヒアリング
o 創業動機、事業内容、経歴、自己資金、希望融資額を確認
o 信用情報や納税状況など、融資を阻むリスク要因を早期に把握
2. 金融機関の選定
o 日本政策金融公庫か、制度融資(信用保証協会付)かを検討
o 「スピード重視なら公庫」「低金利重視なら制度融資」という使い分け
3. 事業計画書・収支計画書の作成
o 単なる書類ではなく「事業価値を伝えるプレゼン資料」
o 数値の根拠を明確にし、返済可能性を裏付ける
4. 面談ロールプレイング
o 創業動機や市場分析、収益計画について想定問答を準備
o 具体的に答えられる練習を重ねる
5. 金融機関との面談同行
o 支援者は「交渉人」ではなく「影のサポーター」
o 申請者本人の主体性を尊重しつつ、安心感を与える立場を取る
この流れを理解することで、支援の質が大きく向上し、融資成功の可能性も高まります。
各ステップにおけるポイント
1:初回面談・ヒアリング
創業者からの相談を受けたら、まず丁寧なヒアリングを行います。ここで確認すべきは、単なる事業内容や希望融資額だけではありません。金融機関が最も重視する「創業者自身の信頼性」と「事業の実現可能性」を見極めるための情報を引き出すことが目的です。
| 創業動機・目的 | なぜこの事業を始めたいのか?その情熱と覚悟は本物か。事業にかける想いは、面接官の心を動かす重要な要素です。 |
| 経歴とスキル | これまでの職務経歴や経験が、これから始める事業にどう活かされるのか。関連性・一貫性のあるストーリーは、事業の成功確率を高く見せる上で不可欠です。 |
| 自己資金 | いくら準備しているか、そして「どのように貯めたか」が重要です。コツコツと計画的に貯めた資金は、創業への強い意志と計画性の証と見なされます。 |
| 希望融資額とその内訳 | なぜその金額が必要なのか。設備資金と運転資金に分け、それぞれ具体的な根拠(見積書など)と共に説明できるかが問われます。単に「借りられるだけ借りたい」という姿勢は、計画性の欠如と見なされ、マイナス評価につながります。 |
<絶対に確認すべき「個人信用情報」>
事業計画がどれほど素晴らしくても、社長個人の信用情報に問題があれば、融資の土俵にすら上がれません。以下の項目は、最初に必ず確認し、もし該当する場合は対策を検討する必要があります。
• 個人信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)
• 税金や社会保険料の滞納
• 公共料金や家賃の支払遅延
• 他社での多額の借入
これらの情報は、創業者本人も気づいていないケースがあります。会計事務所として事前にリスクを洗い出し、適切なアドバイスを行うことが、信頼関係の第一歩となります。
2:金融機関の選定
融資を申し込む金融機関は、主に「日本政策金融公庫」と「民間金融機関(信用保証協会付融資)」の2つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、創業者の状況に合わせて最適な選択肢を提案することが求められます。
| 日本政策金融公庫 | 政府系の金融機関であり、創業者への融資に最も積極的です。特に「新創業融資制度」は、無担保・無保証人で利用できる場合が多く、創業者にとって心強い味方です。まずは公庫への相談を第一選択肢と考えるのが定石です。 |
| 民間金融機関(信用保証協会付融資) | 地域の銀行や信用金庫などが行う融資です。プロパー融資(金融機関が100%リスクを負う融資)は創業期にはハードルが高いため、多くは信用保証協会が保証する「制度融資」を利用します。地域に根差したサポートが期待できる一方、審査のプロセスが公庫より複雑になる場合があります。 |
創業者の事業規模や自己資金額、地域性などを考慮し、どちらがより有利な条件を引き出せるか、専門家として的確に判断しましょう。
3:事業計画書・収支計画書の作成
融資審査の核心となるのが、事業計画書と収支計画書です。ここで金融機関が知りたいのは、「この事業は本当に儲かるのか?」そして「貸したお金はきちんと返済されるのか?」という2点に尽きます。
<事業計画書作成のポイント>
• 「経験」と「事業内容」の矛盾をなくす: なぜ自分がこの事業を成功させられるのか、これまでのキャリアと結びつけて説得力を持たせます。
• 「強み」を明確にする: 競合他社と比較して、どこが優れているのか(差別化要因)。
価格、品質、サービス、立地など、具体的な言葉で表現します。
• 過大な数値計画はNG: 現実的で堅実な計画こそが信頼性を生みます。希望的観測ではなく、客観的なデータや根拠に基づいた計画を立てる支援が重要です。
<収支計画書作成のポイント>
• 売上高の根拠を明確に: 「客単価 × 席数 × 回転数 × 営業日数」のように、具体的な計算式で売上予測のロジックを示します。閑散期や繁忙期も考慮した、リアリティのある計画が求められます。
• 利益率の妥当性: 業界の平均的な利益率から大きく乖離していないかを確認します。
高すぎる利益率は、計画の甘さを疑われる原因になります。
• 固定費の見積もり: 家賃、人件費、リース料など、売上に関わらず発生する固定費を正確に洗い出し、過剰な負担になっていないかをチェックします。損益分岐点を意識した計画作りをサポートしましょう。
これらの書類は、創業者自身が自分の言葉で語れるよう、会計事務所はあくまで伴走者として、作成を支援する姿勢が大切です。
4:面談のロールプレイング
書類審査を通過すると、いよいよ担当者との面談です。創業者は緊張のあまり、本来の魅力を伝えきれないことが少なくありません。そこで効果絶大なのが、会計事務所による面談のロールプレイングです。
| 創業動機・事業概要 | なぜこの事業なのか?あなたの言葉で情熱を伝えてください。 |
| 市場・競合・差別化 | あなたの強みは何ですか?誰に、何を、どのように提供しますか? |
| 売上・利益の見込みと根拠 | 月商はいくらを想定していますか?その計算根拠を教えてください。黒字化はいつ頃の予定ですか? |
| 資金の使い道と借入額の妥当性 | 借りたお金は何に使いますか?自己資金はいくらですか? |
| 返済の見通し | 売上が計画通りにいかなかった場合、どうやって返済しますか? |
これらの質問に対し、創業者自身が自信を持って、矛盾なく、かつ簡潔に答えられるよう、何度も練習を重ねます。会計事務所は面接官役として、鋭い質問を投げかけ、回答をブラッシュアップしていく重要な役割を担います。
5:金融機関との面談同行
可能であれば、面談にも同行しましょう。専門家が隣にいるというだけで、創業者は精神的に大きな安心感を得られます。面談の場で会計事務所が主導して話す必要はありません。あくまで主役は創業者です。しかし、創業者が答えに詰まった際に補足説明をしたり、専門的な観点から計画の妥当性を裏付けたりすることで、金融機関に与える信頼度は格段に向上します。
まとめ
創業融資支援は、クライアントの第一歩を支える重要なプロセスです。適切な流れを理解し、具体的な支援方法を実務に活かすことで、スムーズな資金調達と信頼関係の構築が実現します。
創業融資支援は、会計事務所が未来の優良顧問先と出会い、長期的な信頼関係を築くための絶好の機会です。今回ご紹介した一連の流れとポイントをマスターすれば、創業者の夢を叶える強力なパートナーとなり、事務所のブランド価値を大きく高めることができるでしょう。
しかし、実際の現場では、本記事だけでは伝えきれない数多くのノウハウや、ケースバイケースの判断が求められます。今回の講演収録商品は、そのために必要な知識と実践的なノウハウを網羅的に提供する内容となっています。創業支援に関わる会計事務所や専門家にとって、確かな指針となるはずです。実務に直結する学びを得たい方は、ぜひこの収録をご活用ください。
収録商品の実務的な活用シーン
今回の収録商品は、会計事務所の新人職員教育や、創業支援チームの研修教材としても有効です。融資制度の基礎理解から、事業計画書作成の実務、さらには面談対応の具体例まで網羅しているため、事務所全体のスキル底上げに役立ちます。
また、既存の顧問先から創業支援の相談を受けた際にも、本収録で学んだ内容を活用することで、自信を持って提案やアドバイスができるようになります。単なる理論ではなく「現場で使える知識」が凝縮されている点が大きな特徴です。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら