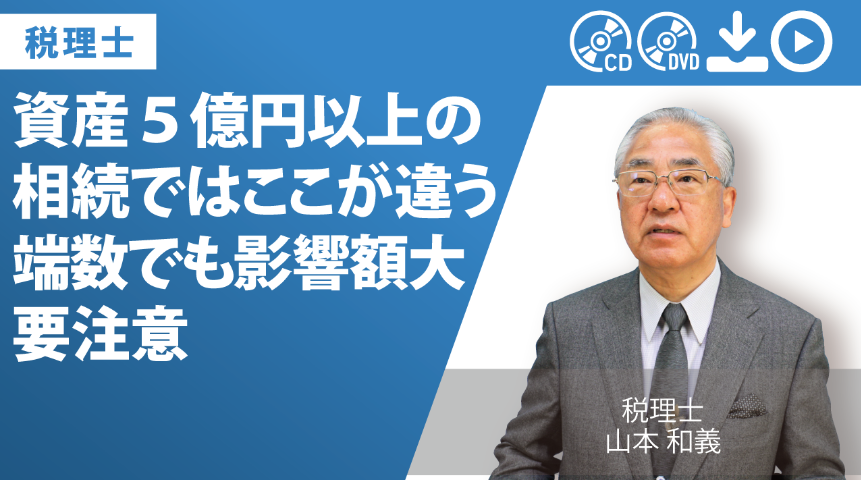レガシィクラウド ナレッジ
【税理士向け】相続財産5億円超富裕層の相続税申告と税務調査対応
相続財産の大口事案では、追徴税額が大きくなる可能性が高いことから、税務調査の対象に選定されることになると思われます。そこで、相続財産が5億円以上の相続税の申告の留意点と、税務調査対応について解説することします。
1. 相続税の申告状況
国税庁の令和4年度統計資料によれば、令和3年中の死亡した者が令和4年に相続税の申告(申告状況:以下同じ)を行うと仮定した場合の相続税の申告割合は、約13.1%(※1)となっています。
相続税の申告件数のうち課税価格3億円超の件数は、10,152件(※2)で、課税価格3億円以下の被相続人の割合は約94.6%(※3)、課税価格2億円以下の被相続人の割合は約89.3%(※4)となっています。
また、相続税の申告件数を税理士登録者数(日本税理士連合会調べ・令和6年12月末日現在)で除すと、2.32件(※5)となり、平均的な税理士は相続税の申告業務にかかわるのは、ほぼ半年に一回程度しかありません。
※1:189,138人÷1,439,856人
※2:5,972件+1,886件+1,105件+862件+327件
※3:(127,561人+41,314人+10,000人)÷189,138人
※4:(127,561人+41,314人)÷189,138人
※5:189,138人÷81,570人
2. 相続税の税務調査の現状
国税庁が令和6年12月に公表した相続税の税務調査の概要は、以下のとおりです。
令和5事務年度においては、令和4事務年度から、実地調査件数(8,556件)、追徴税額合計(735憶円)は、ともに増加(対前事務年度比104.4%、109.8%)しました。
また、1件当たりの申告漏れ課税価格は3,209万円(対前事務年度比90.9%、)、実地調査1件当たりの追徴税額(加算税を含む。)は859万円となりました。
なお、相続税の実地調査を受けた件数のうち約84%が修正申告となっています。申告漏れ財産のうち、現金・預貯金及び有価証券は40.9%となっていることから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。特に、相続人名義の預貯金や株式が被相続人の財産として判定され、課税されている場合が多いと思われます。
最近の傾向として、簡易な接触に積極的に取り組むことにより、接触件数は18,781 件(対前事務年度⽐125.2%)、申告漏れ等の非違件数は5,079件(同137.8%)、申告漏れ課税価格は954億円(同139.0%)、追徴税額合計は122億円(同140.8%)と、いずれも簡易な接触の事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最⾼となっています。
3. 相続税の申告状況から検証する税務調査の現状
先述のとおり、令和4年度の相続税の申告件数(申告状況:以下同じ)のうち課税価格3億円超の件数は、10,152件、また相続税の申告件数のうち課税価格3億円以下の被相続人の割合は、約94.6%となっています。
さらに、課税価格が5億円超の申告件数は4,180件で、年間死亡者数に占める割合は2.2%に過ぎません。
相続税の実地調査の件数は、令和4年事務年度では8,196件で、課税価格が3億円超の申告については、税務調査の対象になる可能性が高いと予想されます。
なぜなら、課税価格の大きい相続税の申告事案では、申告漏れ財産の額が1,000万円であった場合でも、相続税が超過累進税率であることから徴収税額が多くなります。また、財産の種類も多く相続財産の申告漏れの確率が高いと思われます。
4. 課税価格5億円以上の相続税の申告の留意点
(1)少額な資産についての申告漏れに注意
課税価格が大きい相続税の申告では、少額な財産(介護保険料や高額療養費の精算金など)の申告漏れでも追徴となる相続税額は大きくなります。そのため、漏れなく財産として申告するべく慎重に財産の有無の確認が欠かせません。
(2)グレーゾーンの財産
相続財産の中には、相続人名義の財産であっても被相続人の財産として課税される事例も少なくありません。特に、預貯金や有価証券などについては要注意です。
(3)配偶者がいる場合
① 通算相続税を考慮した遺産分割
夫婦がともに資産家である場合に、残された配偶者が何をいくら相続すれば、通算相続税の負担が最も少なくなるような遺産分割について慎重な検討が必要となります。
例えば、同年中に連続して相続が開始したときには、父と母の通算相続税が最も少なくなる割合については、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けないで、相次相続控除を適用して相続すれば、通算相続税が少なくなる場合もあります。
② あん分割合の調整
相続財産が高額で父が高齢で亡くなった場合に、母もそれなりの年齢であれば、母の相続は10年以内に開始する可能性が高いと予想されます。そのような場合には、父の相続の際に母が相続する財産のあん分割合を母に寄せるような調整をすることで、母が納付することとなった相続税は相次相続控除の適用を受け、母の相続の際の相続税を軽減することが期待されます。
③ 回収困難な同族会社への貸付金
生前であれば債権放棄などによって回収が困難な貸付金を処理することができますが、相続開始後は貸付金の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときを除き、貸付金の金額が相続財産として課税されてしまいます。
そこで、回収が困難な貸付金は配偶者が相続し、配偶者の存命中に債権放棄などを行うことで、第二次相続の相続税の負担を軽減させることができます。
④ 特定の評価会社に該当している株式
「比準要素数1の会社に該当している場合には、会社規模区分に関わらず、「類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75」で評価することとされています。そのため、類似業種比準価額が純資産価額より低い会社においては、株価は高く評価されることとなります。
そこで、相続開始後は、配偶者がその株式を相続し、配偶者の存命中に配当金を支払うなどの対策によって、一般の評価会社にしておけば、配偶者の相続の際には相続税が軽減されることになります。
(4)公的機関への照会
相続財産の有無の確認は、適正な相続税の申告などのために、以下のような内容については公的機関への照会が欠かせません。
① 贈与税の開示請求(被相続人の所轄税務署)
この制度を利用することによって、生前贈与を受けていたか否かを相続人からの聞き取り以外の方法で確認することができるので、誤りのない相続税の申告に役立ちます。
② 生命保険金の有無(生命保険協会)
一般社団法人生命保険協会から、生命保険会社(日本で営業する生命保険会社全42社)が照会を受け付けた日現在有効に継続している個人保険契約等の契約者及び被保険者の名寄せを行い、照会対象者にかかる保険契約等の有無について調査を行い、回答されます。
この制度を利用すれば、生命保険金の請求漏れ(相続財産への加算漏れ)を防止することができます。
③ 遺言書の確認(公証人役場)
相続手続きに当たって遺言書が残されていなかったかの確認は欠かせません。なぜなら、遺言については、遺言者の死亡によってその効力が発生し、遺言者の最終意思を尊重するという遺言制度の趣旨から、「遺言は法定相続に優先する」とされているからです。
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、最寄りの公証人役場でその作成の有無をすぐに確認することができます。
④ 証券会社との取引(証券保管振替機構)
この制度は、登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」)は、上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です。この制度を利用すれば、上場株式等の有無が確認でき、相続財産への計上漏れを防止することに役立ちます。
(5)書面添付
書面添付がある相続税の申告においては、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。
相続人にとって実地調査は精神的な負担も大きいので、書面添付をしておくことで調査が省略になる可能性や実地調査に移行することになっても、実地調査の時間が短くなることが期待されます。
5. 相続税の税務調査対応
相続財産の課税価格が5億円以上の場合には、税務調査が行われる可能性が高いことから、税務調査への対応も検討しておかなければなりません。
税務調査は適正・適法に申告されているのか確認するもので、決して税金の追徴を目的としているものではありませんが、調査対象先として選定されるのは追徴税額が予想される先を優先して選定していますので、追徴課税になる可能性が高いと思われます。
また、税務署員の心理として何等かの非違を見つけて、一定の成果を挙げたいと考えていると思われます。
(1)実地調査開始日前の対応
グレーゾーンの財産について相続財産としないと判定した事実関係を相続人にも再認識をしてもらい、税務調査当日はその部分についての税務署員の指摘に対し、具体的、かつ、事実関係の資料などを提示して相続財産でないことを主張することが重要です。
また、税理士が税務署員となって税務調査をしてみることも相続人にとっては安心感を得てもらうことができると思います。税理士が質問する事項は多分税務署員が疑問に感じる部分と同じであると思われることから、相続人がどのように回答するのか模擬テストをし、回答が適切でない場合には、模範解答などを解説しておくようにします。
税務調査では、貴重品置き場を確認することがよく行われます。そのため、調査日前に、税理士が貴重品置き場(例えば、自宅内においてある金庫や貴重品袋など)に何が置いてあるのか確認し、誤解を生じるような物は整理しておくようにします。また、印鑑なども確認し、使用していない印鑑なども整理しておくことがよいと思います。
(2)税務調査当日
相続人に対して、税務署員からの質問に対して回答しなければならない義務があることを説明し、事実関係が不明瞭なものについては後日回答することで良いことを念のため再度説明しておきます。質問事項へは端的に回答し、質問事項以外のことについて必要以上に回答しないようにすることも釘を刺しておくことが肝要です。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら