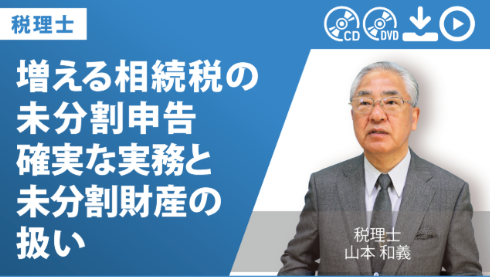レガシィクラウド ナレッジ
遺産分割協議が相続税申告期限までに調わない場合の留意点
令和5年の最高裁判所の統計資料によると、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数は7,297件で、遺産の価額が1,000万円以下の割合は33.9%となっています。自宅以外に分けるものがない場合など遺産の多寡に関係なく、遺産争いになっている現実を垣間見ることができます。
相続税の申告が必要な場合に、遺産分割協議が申告期限までに調わないときには、未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分の割合又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算することとされています。
遺産が未分割である場合には、一部の財産について未分割である場合もあります。また、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割協議が調った場合は、一定期間内に更正の請求などによって過大となっている相続税について還付を受けることができます。
そこで、遺産分割協議が相続税の申告期限までに調わない場合の相続税の申告と留意点について簡潔に解説することとします。
遺産が未分割である場合の相続税の申告
相続税法55条《未分割遺産に対する課税》は、相続税について申告書を提出する時又は更正若しくは決定をする時までに、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部の分割が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分の割合又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算することを規定しています(相基通11の2-2)。
その場合、相続税法55条に規定する「民法(904条の2を除く。)の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算する」とは、各共同相続人が相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から既に分割を受けた財産の価額を控除した残りの価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち、「穴埋方式」により課税価格を計算すると解するのが相当である」(平成27年6月3日裁決)としています。
申告期限までに遺産が未分割である場合の手続
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、
① 配偶者の相続税の軽減
② 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
③ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
④ 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
の適用を受けるために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書とともに提出することとされています。
また、3年以内に分割協議が調わなかった場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して税務署長の承認を受ける必要があります。
この承認申請書は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出しなければなりません。
やむを得ない事情の有無については
① 相続人又は遺産の範囲などの遺産の分割の前提となる事項について争いが存在し解決のための法的手続(訴訟)がとられている場合
② 遺産の分割に向けた法的手続がとられている場合
③ 遺産の分割が法的に不可能な状態にある場合と同視し得る事情があると認められる場合
をいうものと考えられ、相続人又は遺産の範囲などの遺産の分割の前提となる事項について争いがなく、客観的に遺産分割ができ得る状態にあるにもかかわらず、相続に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに遺産分割されなかった場合には、税務署長の承認を受けることはできない(国税不服審判所:平成26年6月2日裁決)と考えられます。
なお、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告ともに提出しなかった場合には、宥恕規定(相法19の2④)が設けられていますが、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」については、宥恕規定がありません(相令4の2②)。
そのため、期限が徒過すると配偶者に対する相続税の軽減などの適用を受けることができなくなります。
未分割財産の取扱い
(1)非上場株式等
相続人間で遺産分割協議が調っていない状況で、取引相場のない株式を評価する場合、各相続人に適用されるべき評価方式を判定するに当たって、基礎となる「株式取得後の議決権の数」は、各相続人ごとに、所有する株式数にその未分割の株式数の全部を加算した数に応じた議決権数とされます。
遺産未分割の状態は、遺産の分割により具体的に相続財産を取得するまでの暫定的、過渡的な状態であり、将来、各相続人等がその法定相続分等に応じて確定的に取得するとは限りません。そこで、その納税義務者につき特例的評価方式を用いることが相当か否かの判定は、当該納税義務者が当該株式の全部を取得するものとして行う必要があります。
(2)賃貸不動産から生じる賃料
遺産分割の効力は相続開始時点に遡って効力を生じますが、その相続財産から生じる財産は、その相続財産とは別の財産であると考えることになります。よって、遺産分割協議により確定したその相続財産と紐付きで分割されず、各相続人が法定相続分で取得することになります(平成17年9月8日:最高裁判決)。
ただし、賃料も相続財産から生じる果実ですので、賃料についても遺産分割協議で配分を合意するのが一般的です。
小規模宅地等の特例選択についての同意
遺言書どおり相続する場合で、他に未分割財産である特例対象宅地等があるときには、遺言書により取得した特例対象宅地等から小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、期限内申告において共同相続人全員の選択同意が必要となります。そのため、相続税の申告期限後において未分割財産である特例対象宅地等について、遺産分割協議が調ったとしても、「更正の請求」によってもこの特例の適用を受けることはできません。
なお、特例対象宅地等を相続した相続人等の全員の同意が得られない場合に、相続させるとしている宅地等についてその相続人が遺贈の放棄を行い、特例対象宅地等のすべてを未分割の状態に戻し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割されたときは、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます(措法69の4④)。
この場合において、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、この特例の対象になります(相法32)。
しかし、遺贈の放棄をした者がその後の遺産分割協議において、その宅地等を相続することができるとは限らないことに留意しておかなければなりません。
数次相続が開始した場合
一次相続(被相続人父)で未分割財産がある状態で、二次相続(被相続人母)が発生した場合には、まず、一次相続で未分割であった財産について、一次相続の相続人ら(包括受遺者及び被相続人の権利義務承継者を含む)により遺産分割を行います。その上で、被相続人の母に帰属することとなった財産について、母の固有財産と合算して、二次相続の相続人間で遺産分割を行います。
一次相続で未分割であった財産についての遺産分割を行うことが困難な場合は、一次相続において被相続人の母が法定相続分で一次相続に係る財産を取得したとして、課税価格及び相続税額を計算して申告を行います。
この場合に、一次相続が未分割であれば、配偶者に対する相続税額の軽減を受けることができませんが、相続人らによる一次相続の分割で、母が取得した財産として確定させたものがあるときは、その財産は母が取得したものとして取扱い、配偶者に対する相続税額の軽減を受けることができます。
相続税の申告のやり直し
相続税について申告書を提出した者は、一定の事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求をすることができます(相法32)。
更正の請求は「することができる」とする規定ですが、過大に相続税を納付していても更正の請求をしないと相続税額の還付を受けることができません。しかし、実務では更正の請求をしないことも考えられます。
例えば、以下のような事例で更正の請求をしないことを選択することがあります。
【設例】申告後の遺産分割において相続税の更正の請求をしないとした場合
相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかったことから、未分割で申告をしていた。その後、遺産分割協議が調ったことから、当初申告と異なる相続税額となった。
1. 被相続人 母(令和6年2月死亡)
2. 相続人 長男・長女
3. 遺産の額 2億円
4. 遺産分割(令和7年3月成立) 長男 1.2億円、長女 0.8憶円
長女は希望する財産を取得する代わりに、相続税の更正の請求をしないこととした。
5. 相続税の計算 (単位:万円)
| 期限内申告(未分割) | 【参考】分割後の申告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 長男 | 長女 | 長男 | 長女 | |
| 課税価格 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
| 各人の相続税 | 1,670 | 1,670 | 2,004 | 1,336 |
この事例の場合、長女は当初申告の相続税額1,670万円が、遺産分割を基に相続税を計算しなおすと1,336万円に減少します。そのため、更正の請求を行うことで334万円の還付を受けることができますが、遺産分割の協議の中で更正の請求をしないことを条件に長女が希望する財産を取得したことから、長女は更正の請求をしないこととしました。
一方、長男は当初申告の相続税額より、分割後の遺産を基に計算される相続税額が増加することになるため「修正申告」に該当することになります。しかし、未分割遺産が分割されたことに伴う修正申告は「することができる」とされていて修正申告書の提出は義務ではありません(相法31①)。
しかし、長女が更正の請求を行い更正の請求が認められた場合に、長男が修正申告書を提出しないときには、税務署長は更正処分をすることとされています(相法35③)。
相続税の更正の請求期限
未分割財産である特例対象宅地等が申告期限から3年以内に分割されたというのは、「すべての相続財産が申告期限から3年以内に分割された」と解釈することはできません。
そのため、土地を先行して遺産分割協議を調え、その後にその他の財産について遺産分割協議が調った場合に、すべての遺産について遺産分割協議が調った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うと期限を徒過したことになってしまいます。
【設例】
1. 当初申告 遺産が未分割であるものとして法定相続分によって相続税の申告期限(令和6年10月10日)に申告した
2. 分割協議成立
① 特例対象宅地等 令和6年12月1日に長男が相続し相続登記を行った
② その他の財産 令和7年4月10日にすべての財産について分割協議が調い、各共同相続人がそれぞれの財産を相続した。
3. 更正の請求
長男は、すべての財産について遺産分割協議が成立したので、特例対象宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税の更正の請求を行った。
4. 更正請求却下
更正の請求期限(令和6年12月1日→令和7年4月1日)を徒過しているため更正の請求は認められない。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら