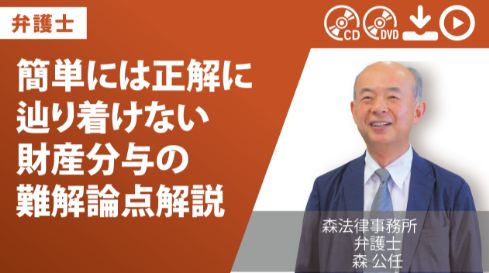レガシィクラウド ナレッジ
【弁護士向け】財産分与の論点|抽象的な財産分与請求権について
本講座では、改正された「民法768条3項(財産分与)」につき、財産分与に関する重要論点を解説していきます。本記事では特に抽象的な財産分与請求権について記載しています。
1.財産分与請求権と改正民法
改正民法で一番ホットなニュースは共同親権ですが、個人的には、1/2ルールを明記した「改正民法768条3項(財産分与)」だと思っています。女性の人権確保という観点から、非常に有意義な改正でした。
第768条(財産分与)
1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
そのほか、情報開示命令手続きと考慮事情の明記がありますが、一番影響が大きい改正は、除斥期間が5年に伸びたことでしょう。離婚して、「さあ、これから仕事どうする?子供どうする?」と考えていると、あっという間に2年経過してしまいます。
弁護士をたてずに二人で話し合って離婚したときは、財産分与という制度そのものを知らないまま離婚し、気が付いたときは2年経過していたということも珍しくありません。これに伴い、年金分割も5年に変更されるそうです。
2.夫婦別産制と財産分与請求権
ところで、この財産分与請求権、今一つ内容がはっきりしません。というのも、民法のもう一つの大原則である夫婦別産制と財産分与の関係がはっきりしないからです。
わが国は、夫婦別産制を採用しています。「夫婦でも財布は別」という思想です。
これと異なるのが夫婦共有制です。これは「夫婦なら財布は一緒」という思想です。夫婦別産制に立つ限り、もともと財布が別ですから、財産分与という制度はありえないはずです。逆に夫婦共有制なら、財産分与は共有物分割ということになります。
ところがわが国では、夫婦別産制を維持しながら、一方で財産分与制度と維持し、しかも、1/2ルールを確立しています。そのために「実質的夫婦共有財産」という概念を用いています。
これを当事者の側から見ると、婚姻中は、夫婦別産制ですから、「夫婦でも財布は別ですよ」となっています。ところが、夫婦関係が悪化すると、突然、実質的共有という言葉が登場してきて、「実は、夫婦の財布は一緒でした」と真逆なことをいわれるわけです。これは、当事者としては混乱すると思います。それならば、夫婦共有制を採用すればいいではないかと思われるかもしれませんが、夫婦共有制を正面から採用すると負債まで共有になってしまいます。
例えば、夫が事業に成功して財産を築き夫婦共有とするなら、夫が事業に失敗して負債を負ってしまいましたと言う場合にも、夫婦共同責任の借金としなければおかしいですよね。しかし、わが国で、こんな制度認めたら、大変なことになります。夫婦共有制は夫婦共有制で問題があるのです。
では、夫婦別産制と財産分与をどうやって両立させるのか?よくよく考えてみると、実質的夫婦共有という概念はわかるようでわからない概念です。形式的には単独所有だけど、実質は夫婦共有という趣旨なのでしょうが、つきつめて考えると何のことであるかわかりません。これが、財産分与でなかなか明確に一つの結論を論理的に導けない原因となっています。
実質的共有という概念を強調すれば、財産分与対象財産は、民法物権法の共有であるが、だけれども夫婦の場合は、共有物分割の特則として、財産分与が決められているということになります。書籍にも、財産分与が除斥期間経過で行使できないときは、共有物分割で処理することも可能だと書かれていたりいます。これは、財産分与を共有物分割の特則としてとらえているようです。
しかし、それなら、債務も共有なのかという問題に直面します。ローンを組んで夫が夫名義で不動産を購入しました。しかし、名義は夫単独でも、所有権は夫婦共有、ただしローンは夫だけというのでは、やはりおかしいし、そもそも金融機関が納得しないでしょう。
実務では、価値の配分と考えています。夫婦別産制だから、財産は別で、物権法の共有ではありません。だけれども、その価値は共有で、だから、離婚の際は、双方の資産価値が同じようになるようにしなさい、という運用です。
この価値配分請求権は、除斥期間内に行使する必要がありますから、除斥期間が経過したら、この価値配分は請求できなくなります。これは、個人的意見ですが、おそらく、ドイツ法を参考にしているのではないかと思います。ドイツでも、わが国同様、夫婦別産制で、だけど、離婚の際は、夫婦の財産の数字が同じようになるようにしなさいとなっているそうです。この運用は、わが国と非常に似ています。
3.抽象的財産分与請求権
(1)発生時期
では、この財産分与請求権、つまり価値の配分請求権はいつ発生するのか?ここも不明です。
離婚したら財産分与が請求できます。この請求権が合意とか審判で具体化された段階で、初めて財産分与請求権が発生します。例えば、財産分与として1,000万円支払えとなったら、1,000万円という財産分与請求権が発生します。しかし、請求する段階では、まだ具体的権利ではありません。具体的権利にしてほしいという請求権にすぎません。
このように財産分与請求権は、合意か審判で初めて発生する権利です。財産法では、要件事実に該当する事実があれば、当然に効果が発生するのとは違います。
お金を貸したら、返済義務が発生する、これは当然に発生します。同じ金銭給付請求権でも、全然違います。
では発生する前、たとえば財産分与の協議をしたり、審判をしてる間は何も権利がないのか?
裁判所は、この段階で具体的な権利ではないが単なる期待権でもない、抽象的な財産分与請求権は発生するとしています。最高裁判例です(最判小二昭55・7・11民集第34巻4号628頁)。
(2)権利性
では、この「具体的権利ではないが期待権でもない」という抽象的財産分与請求権は、どこまで権利性があるのか。これがはっきりしません。
(ア)詐害行為取消権と債権者代位権の場合
権利性が一番問題になるのが、詐害行為取消権と債権者代位権です。離婚訴訟をしている間に、唯一の財産である不動産の名義変更がされた、相手は不倫相手である、そういうときに、抽象的財産分与請求権があることを理由として、詐害行為取消権や債権者代位権を行使できるのか?
「期待権」と構成すれば行使できないのは明確であり、具体的権利と構成すれば当然できます。それでは、「抽象的財産分与請求権」と構成するとどうなるのか?
実は、裁判所は、代位権は行使できない(最二小判昭和55・7・11日民集 34・4・628)が、詐害行為取消権は行使できる(京都地判平成4・6・19 判タ813・237)としています。代位権の場合は、具体的権利ではないというのがその理由で、取消権の場合は、抽象的財産分与請求権は、既に発生しているというのが、その理由です。
抽象的財産分与請求権のあいまいな性格を使い分けています。
(イ)建物明渡請求の場合
もう一つ、離婚した元配偶者が、実質的共有財産であるが配偶者単独名義の家に相手方がいまだ住んでいる場合に、財産分与審理中に、相手方に「私の家だから出ていきなさい」という建物明渡請求を認められるかという問題もあります。
これも、明渡しが認められるという判例(東京地令和3・3・2(ウエストロージャパン))と、認められないとい判例(札幌地判平成30・7・26(判時 2423・106))があります。明渡しを認めない判例は、抽象的にせよ財産分与請求が発生しているといいい、明渡しを認めた判例は、具体的権利となっていないとしています。
(ウ)判例の検討
ここでも、抽象的財産分与請求権の持つ二面性を使い分けています。この二つの判決、どちらも結論からすると妥当な結論です。
明渡しを認めないという判決は、元夫が別の家に住んでいる元妻と子供に対して明渡しを求めた訴訟です。明渡しの必要性はなく、有利な解決を図ろうとしたことが明白です。
これに対し、明渡しを認めた判決は、逆に、元夫から元妻が子どもを連れて妻名義の家を離れ、別の賃貸に住んでいるが、賃料を支払うと生活が苦しいことから、自分名義の家に戻りたい、ついては元夫に出て行ってほしいという裁判です。この元夫は、別の住居を持っていたので、そこに住む必要はなかったのですが、嫌がらせのために居座り続けていた事案です。裁判所は、建物利用の必要性は、元妻の方が高いとして、明渡しを認めました。
裁判所は、抽象的財産分与請求権の持つ二面性、これをうまく使い分けで妥当な結論を導き出そうとしています。
4.総括
一方で夫婦別産制を採用し夫婦でも財産は別としながら、いざ夫婦関係が破綻すると180度方針が返還し、夫婦なら名義に関係なく財産は共有とするというのがわが国の法制度です。この180度急転する過程で発生する抽象的財産分与請求権は、わかったようでわからない権利です。
判例は、具体的権利はないが、抽象的権利があるというスタンスで、言語明瞭・意味不明瞭な感じがしますが、個々の事例をみると、この抽象性をうまく使いわけ、個々的に妥当な結論を導き出しているように思います。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちら