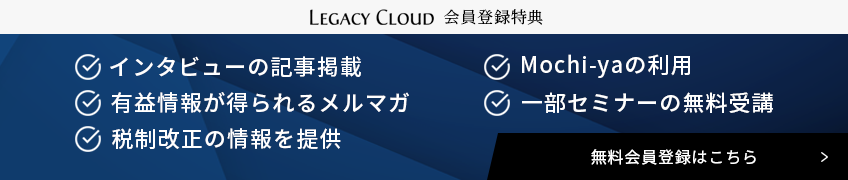お客様の「クッション役」として寄り添い続ける税理士を目指す

渡邊由美子税理士事務所 税理士 渡邊由美子
損害保険会社勤務を経て税理士資格を取得。結婚・出産・子育てを経験しながら複数の会計事務所での社員・パート勤務を通じて実務経験を積み、2018年に独立開業。お客様に親身に寄り添う相談役として、地域に根ざした信頼される事務所づくりを目指している。
損害保険会社での営業事務から税理士への転身、そして子育てと両立しながらの独立開業まで、様々な経験を積まれた渡邊先生にお話を伺いました。
税理士を目指したきっかけを教えてください
私は短大の英文科を卒業したのですが、当時は税理士という職業について特に考えたこともなく、卒業後は損害保険会社で営業事務として働いていました。2年ほど働いた頃、「この仕事を一生続けるのは少ししんどいな」と感じるようになり、転職を考え始めました。そんな時、損保の代理店の方から「税理士は女性も活躍できる仕事だから良いのでは?」と勧められたのがきっかけです。それで初めて税理士という職業について調べてみると「簿記」という資格があることを知り、最初は名前からして難しそうで躊躇しましたが、半年ほど経って改めて転職への思いが強くなり、簿記3級の勉強を始めることにしました。
3級は本屋で参考書を買って独学で勉強しました。最初は「貸倒れ引当金」などの専門用語が全く理解できませんでしたが、簿記2級からは専門学校に通い、3ヶ月講座で96点という高得点で合格し、簿記1級もすぐに受かるだろうと軽く考えていました。しかし1級の範囲が広いせいもあり、働きながらだと最後の単元を受講している頃には最初の単元はすっかり忘れてしまっており、1回目の受験は不合格でした。結婚することとなったのを機に勉強に専念できるようになり簿記1級合格⇒税理士試験の勉強へと進みました。税理士試験は思ってたよりも全く大変で、5科目全てに合格するまで約5年かかりました。特に苦労したのは簿記論で、簿記検定に受かっていたので簿記論は一番楽勝だと思っていたのに、実際は最初から最後までずっと苦戦しましたがどうにか合格できました。
合格後は20人ぐらいの税理士事務所に入りました。ただ、長いブランクがあったことと、会社員時代もワードやエクセルを使いこなしていたわけではなかったので、エクセルで相続税の資料を作成するといった基礎的な業務から覚えていくことになりました。そこでは申告書の作成や担当を持ってお客様への対応など、税理士業務の基本を一通り経験させていただきました。振り返ってみると、この仕事は本当に面白いと感じます。経営や会社の核の部分であるお金の流れに関わることができるのは、会社員時代では経験できなかった貴重なやりがいでした。しかし、子供ができたため退職することになりました。出産後もパートなどに移行して働く女性はいなく、がっちり働く必要があったので、子育てとの両立は難しいと判断しました。その後、専門学校時代に一緒に勉強していた方が事務所を立ち上げたので働かないかとのお声がかかり、週2、3回のパートとして働かせていただくことになります。そこでは10年ぐらい、途中2人目、3人目の出産などもありながら、飛び飛びでお世話になりました。この2つ目の事務所では、より幅広い業務を経験することができ、個人事業主から中小企業まで様々なお客様を担当し、月次監査や決算業務、年末調整など実務経験を積むことができました。また、税務相談への対応や経営者の方々とのコミュニケーションスキルも身につけることができました。
独立したきっかけを教えてください
複数の会計事務所でパートなどの勤務を通じて税理士業務の実務経験を積んできましたが、パートですとはやり業務範囲が限られていたため、お客様と深く関わることが難しく、自分の力を十分に発揮できないもどかしさがありました。また、会社の研修制度も十分とは言えず、税制改正などにどう対応すべきか、知識面での不安も感じていました。そうした中で、下の子が小学校に入る前のタイミングで、「何のために資格を取ったのか」という思いが強くなり、2018年に独立を決意しました。税理士の勉強を始めた頃は、独立することまで考えていたわけではありませんが、手に職をつけて、長く働き続けたいという思いは当初から持っていました。
独立当初は本当に大変で、お客様が全くいない0件からのスタートでした。新規顧客の獲得が最大の課題で、とにかくいろんな研修に出て、異業種交流会にも積極的に参加し、人とのネットワークを築くことから始めました。名刺交換だけでなく、その後のフォローアップも大切にし、継続的な関係性を構築することを心がけました。最初のお客様は、近くにできた喫茶店でした。ママ友の知り合いがやっているということで、ランチを食べに行ったところ、たまたま税理士を変えたいと思っていたそうで、タイミング良くお客様になっていただけました。その後は口コミや紹介でお客様が徐々に増えていきました。税理士登録をしたからこそ、様々な研修に参加できるようになったのも大きな変化でした。税理士会の研修はもちろん、弁護士や司法書士の方との勉強会にも参加し、他業種の専門家との交流を深めることができました。お客様から税務以外のことを聞かれることも多いので、気軽に相談できる専門家のネットワークがあることはとても心強く、現在の業務に大いに活かされています。
今力を入れている取り組みや今後力を入れていきたいことはありますか
現在最も大切にしているのは、親身になって一緒に考えていける税理士になることです。お客様からのご相談は税金のことが一番多いのですが、経営に関わることで「誰に聞いていいのか分からない」という内容も数多くあります。契約書の内容に関することや人事労務の問題、融資相談など、税務の範囲を超えた幅広い相談をお受けすることがあります。厳密に言えば税理士の契約書に書いてある内容ではないかもしれませんが、お客様にとって一番困っているのは「誰に相談していいのか分からない」ということなのです。私自身がその分野の専門家ではなくても、適切な専門家をご紹介したり、「まずはこういうところに相談してみてください」というクッション役を務めるようにしています。お客様との信頼関係を築く上で、このような幅広いサポートは欠かせないと感じています。単に数字を処理するだけでなく、経営者の方々の悩みに寄り添い、問題解決の糸口を一緒に探していく過程を大切にしています。「この先生に言えば何とかしてくれる」と思っていただけるよう日々努力しています。
また、継続的な学習も重要な取り組みの一つです。税理士試験で学んだことは本当に一部分に過ぎず、実務では税制改正への対応、新しい会計基準への理解、IT化への対応など、本当に多種多様な知識が必要になります。自分一人では判断が難しい専門的なことは、信頼できる他の先生方と連携して対応しています。今後特に力を入れていきたい分野としては、相続業務があります。現在は年に1、2件程度ですが、高齢化社会の進展に伴い、今後ますます需要が高まると予想されます。相続は税務だけでなく、不動産評価や家族間の調整など、総合的な知識とコミュニケーション能力が求められる分野なので、しっかりと勉強して対応力を高めたいと考えています。また、組織再編についても関心があります。中小企業においても買収や合併などの相談を受けることが増えており、実際に現在2件ほどそういった案件を抱えています。これは税金と同時に会計の知識もより重要で、法人税の理論だけでは対応できない複雑な分野です。失敗するとリスクが大きいため、そういった組織再編を豊富に経験してきた税理士の方と連携したり、直接指導を受けたりしながら、徐々に対応力を向上させていきたいと思っています。さらに、デジタル化への対応も重要な課題です。クラウド会計ソフトの活用やAIを使った業務効率化など、時代の変化に対応していく必要があります。お客様にとってもメリットの大きい分野なので、積極的に取り入れていきたいと考えています。
最後に、プライベートとの両立についてお聞かせください
現在、家事と子育てとこの仕事で手一杯の状況です。3人の子供(大学生、高校生、中学生)がいるため、毎朝のお弁当作りから始まり、それぞれの学校行事や部活動のサポートなど、まだまだ手のかかることが多いです。一方で、自宅で仕事をしているため、時間の融通は利きやすい環境にあります。お客様との打ち合わせも夜の時間帯に設定することができますし、子供の学校行事がある時は仕事の時間を調整することも可能です。
他の税理士の方や他業種の専門家の方と話していると、忙しいのに読書の時間を作っている方も多く、自分ももっと幅広い知識や教養を身につけたいという思いがあります。月に5冊以上は必ず読むというようなことをおっしゃる方もいて、そういう話題の引き出しがあると、お客様や他の専門家との会話がより豊かになるのではないかと感じています。以前、カウンセリングをしている方から「週に1時間でも自分を育てる時間を取ると違った自分が見えてくる」と言われ、そういう自己投資の時間を意識的に作りたいと思っているのですが、まだ実現できていないのが現状です。将来的には、もう少し時間に余裕ができたら、地域の商工会議所の活動に参加したり、税理士会の委員会活動により積極的に関わったりして、より幅広いネットワークを築いていきたいと考えています。また、後進の指導にも携わってみたいという思いもあります。
仕事と家庭の両立は決して簡単ではありませんが、家族の理解と協力があってこそ今の仕事を続けられています。子供たちも成長とともに自立してきているので、今後は仕事により集中できる環境が整っていくのではないかとワクワクしています。