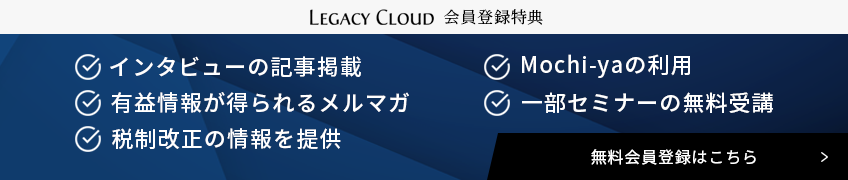会計士・税理士の二刀流でサステナビリティ業務に挑戦 時代の変化を捉える専門性

川上公認会計士事務所 公認会計士・税理士 川上拓哉
大学卒業後、大手銀行に入行。公認会計士の資格を取得後、大手監査法人にて6年間勤務し、ライフサイエンス業界を中心としたグローバル企業の監査業務に従事。 その後、「川上公認会計士事務所」として独立。会計監査・税務顧問の両面から幅広いクライアントを支援している。
銀行や監査法人での勤務を経て独立された川上先生に、独立したきっかけや今後の取り組みについてお話しを伺いました。
税理士を目指したきっかけを教えてください
父が公認会計士・税理士でしたが、当初は全く意識していませんでした。大学卒業後は新卒で大手銀行に入行し、5年ほどサラリーマンとして働いていました。しかし、20代後半になった頃、銀行という企業の特性として転勤が多く、競争も激しい中で、出世や成功に運的な要素が大きく影響することを実感しました。どれだけ努力しても、配属される部署や上司との相性、時代の流れなど、自分ではコントロールできない要素によって評価が左右される現実を目の当たりにして、そこに一喜一憂し続けるような不確定要素の多い人生に疑問を感じたのです。
また、私は大学まで陸上競技の長距離をやっていて、スポーツ推薦で入学したため、実は受験勉強をしたことがありませんでした。周りの同僚たちが難関大学を受験して入学してきた中で、自分の中で「受験勉強をちゃんとやったことがない」ということに対するコンプレックスのようなものもありました。学歴に対する劣等感というよりも、自分の学力や勉強に対する姿勢を試したことがないという心残りがありました。
そういった思いが重なり、父が公認会計士・税理士だったという身近な影響もあって、資格取得により手に職をつけることで、これらの課題を解決できるのではないかと考え、公認会計士の受験を決意しました。専門性を身につけ、自分の力で勝負できる環境を作りたいという想いがありました。
独立したきっかけを教えてください
銀行を辞めてから勉強し、公認会計士に合格後、大手監査法人に就職しました。そこで6年間、主にライフサイエンス部門の会計監査を担当していました。製薬会社や医療機器メーカーなど、グローバルに展開する企業が中心でした。
この分野は日本国内で完結する業務ではなく、全世界にまたがる事業展開をしている点が特徴です。新薬の開発状況などによって業績の変動が大きく、マクロな視点で全体を見渡す能力が求められました。国際会計基準への対応や、各国の会計基準の違いを理解しながら、統一的な監査手続きを実施する必要があり、非常に専門性の高い業務でした。この経験は、現在のスタートアップ支援や国際的な企業の税務顧問業務でも活かされていますね。
監査法人での仕事自体に不満があったわけではありませんが、最後の1年ほどは人から与えられた仕事で非常に忙しくて、朝から晩まで目の前の業務に追われる日々でした。それでいっぱいいっぱいになって、自分がやりたいことを考える余裕もない状態でした。これが独立を決意する最も大きな理由でした。
具体的には、監査のピーク時期になると、連日深夜まで作業が続き、土日も返上で働くことが当たり前になっていました。そうした中で、「今日やるべきこと」に追われるだけで、「将来どうしたいか」「どんなキャリアを築きたいか」「どんな専門性を身につけたいか」といった根本的なことを考える時間が全くありませんでした。考える時間がないということは、自分の人生の方向性を見失うことで、これは銀行時代に感じていた「運に左右される人生」とは違う意味で、自分の意志で人生をコントロールできていない状況でした。
また、監査法人には大学在学中や卒業直後に合格する22、23歳の若手も多く、年齢差がある中で同じように進んでいくことに焦りも感じていました。30代半ばという年齢を考えると、このまま組織の中で与えられた仕事だけをやるのではなく、自分の責任のもとで仕事を選択し、納得のいく仕事をしたいと強く思うようになりました。
そこで、時間の使い方を自分でコントロールし、じっくりと考える時間を確保できる環境を作るために、独立を決意しました。現在は父の事務所内に席は置いていますが、完全に独立して活動しています。
現在力を入れている取り組みについて教えてください
税理士業務では、スタートアップ関連の会社の税務顧問に力を入れています。銀行での経験もあるため、資金調達や銀行対応といった分野も守備範囲に含めることができ、これが他の税理士との差別化要因となっています。
創業間もない会社の場合、単に「1,000万円欲しい」と言うのと、「来年の売上計画に基づいて運転資金として1,000万円必要で、回収サイクルを考慮すると3か月分の運転資金が必要」と具体的な根拠を示すのでは、融資の通りやすさが全く違います。そういった見せ方や銀行の視点からのアドバイスができることが強みです。事業計画書の作成や財務予測の精度向上についても、銀行員としての経験を活かして実践的な指導を行っています。
会計士業務では、学校法人の監査、不動産特定共同事業法監査、ベンチャーキャピタルとの協業によるスタートアップ評価業務、そして特に力を入れているのがサステナビリティ関連業務です。
学校法人の監査を担当している理由は、教育機関特有の会計処理や法的要件への対応が必要で、一般企業とは異なる専門性が求められるからです。また、学校法人は地域社会に根ざした重要な存在であり、その健全な運営を支援することで社会貢献できるという意義も感じています。私立学校の補助金や寄付金の処理、減価償却の特殊な取り扱いなど、複雑な会計処理を正確に行うことで、教育の質の向上に間接的に貢献できることにやりがいを感じています。
サステナビリティ関連業務については、企業の環境対策や温室効果ガス削減の取り組みを数値化し、それを確認する業務です。具体的には、電気やガスの使用量から温室効果ガスの排出量を算出し、全世界の事業所で統一的に測定・報告する仕組みを構築します。非常に地道な作業ですが、計測方法の標準化や全世界の従業員への周知なども含めて支援しています。この分野は今後重要性が増すと予想されるため、早期から専門性を身につけることで、将来的な差別化要因にしたいと考えています。
業務をするうえで心がけていることはありますか
仕事をする上では、スピード感と、他人事のように接しないことを心がけていて、お客様の気持ちや立場になって親身に対応することを大切にしています。これは銀行時代に培った姿勢で、士業の方の中には一般論で答えたり、責任回避的な対応をする方もいますが、そうではなく、お客様の中に入り込んで一緒に解決策を考えるスタンスを大切にしています。
また、独立すると自分で考え、方向を決めて進んでいかなければなりません。そのため、朝5キロのランニングを続けており、これが内省の時間となっています。走りながら「今日はどうしようか」「この案件はどう進めよう」などと考える時間が、自分にとって非常に大切な時間となっています。
今後の展望について教えてください
税理士業務では、相続なども含めて守備範囲の広い税理士になりたいと考えています。現在は会計士業務が半分以上を占めていますが、徐々に税務業務の比重も高めていきたいと思います。特に、個人の資産管理や事業承継といった分野にも力を入れていきたいと考えています。
組織面では、現在は基本的に一人で対応していますが、将来的には組織的に対応できる体制を作りたいと考えています。20~30人規模の事務所を目指し、私自身は現場から少し離れて全体のマネジメントに集中できるような体制を築くことが目標です。
父の事務所では従来型のソフトウェアを使用していますが、私が税務顧問を担当する場合は、インターネットでリモート対応が可能な環境を整えています。
個人的には、業務の効率化のためにAIの活用についても積極的に研究しています。税理士の仕事がAIでなくなるという報道もありますが、重要なのはAIをどう活用するかです。記帳代行のような単純作業は確実に減少しますが、相続のような人間味が必要な業務は残ると考えています。AIを活用することで、単純作業の時間を短縮し、より付加価値の高いコンサルティング業務に時間を割けるようになることを期待しています。