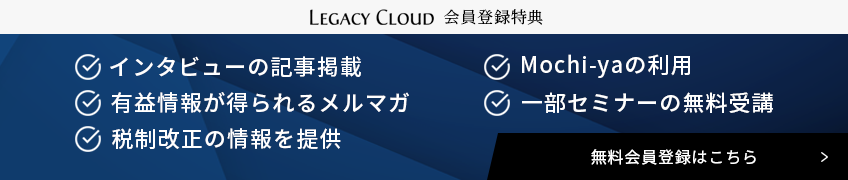AIと共に、会計事務所の未来をつくる

東日本税理士法人 公認会計士・税理士 長 英一郎
中央大学卒業後、公認会計士試験に合格。医療法人分野に強みを持ち、特定医療法人や社会医療法人の認定申請アドバイザリー業務をはじめ、税務・会計の実務経験を積む。副所長として10年以上にわたり経営に携わった後、41歳で東日本税理士法人の所長に就任。現在はAI活用による業務革新を進めている。著書に、『医療のための生成AI実践ガイド 』(日本医学出版)がある。
生成AIを実務に活用している長先生に、事務所の承継や力を入れている取り組みをお伺いしてきました。
公認会計士を目指されたきっかけを教えてください
父が公認会計士・税理士という環境で育ったこともあり、子どもの頃から「自分もいずれ継ぐことになるのだろうな」という感覚が自然とありました。強く意志を持って目指したというよりは、ある種の“宿命”的に進んだというのが正直なところです。
明確に意識したのは高校3年生のとき。中央大学の指定校推薦の話があり、その推薦理由に「公認会計士を目指す」と書くことがプラスになると考えたことで、具体的な道が定まりました。他の選択肢を真剣に考えたことはなかったですね。
大学卒業後は、父の会計事務所で帳簿入力などのアルバイトをしながら、試験勉強に励む日々を送りました。そして27歳のときに公認会計士試験に合格。そのタイミングで父の事務所に正式に入所し、本格的な実務の道に進みました。
事務所に入所された当時はどんな仕事をされていましたか?
最初は、会計入力や仕訳作成など、税理士業務の補助からスタートしました。比較的小規模なお客様については、法人税や所得税の申告書を作成する機会もあり、実務を通じて経験を積んでいきました。
当時、事務所は医療法人のお客様を多く抱えており、特定医療法人や、現在で言う社会医療法人に関連する申請アドバイザリー業務など、医療業界特有の手続きにも携わりました。特定医療法人の認定申請に関わる中で、医療分野における制度や実務への理解を深めることができました。
また、公認会計士試験に合格して実務に入った直後から、父の方針でいきなり現場に出され、20人、30人規模の講演を担当することもありました。十分な準備やトレーニングをする間もなく現場に立つという経験を繰り返す中で、人前で話すことへの苦手意識は徐々になくなり、現在の講演活動にもつながっています。さらに、医療分野に関する実務書の執筆にも携わる機会を得ました。出版社から直接声をかけていただいたもので、貴重な経験となり大きな励みになりました。
一方で、若手時代には苦い経験もありました。税務処理を担当した案件で、税務調査の結果、多額の追徴税額が発生しました。お客様に多大なご迷惑をかけたことを痛感しました。この経験から、税務リスクの見極めや、調査に備えた慎重な対応の重要性を学び、以降の業務に生かしています。
事務所を承継するにあたって心がけていたことを教えてください
私が所長に就任したのは9年前、41歳のときでした。それまで副所長として長年経営に関わっていたため、業務的なギャップはほとんどありませんでしたね。父も会長として残っていましたし、職員との関係性も築けていたので、比較的スムーズな承継だったと思います。
ただ、職員の中には会長(父)派と私派が混在していたので、指示系統や役割の整理には多少の苦労がありました。そこは時間をかけて、丁寧に移行していく必要がありました。
一方で、組織運営において反省点もありました。かつて「残業はさせない」という方針を強く打ち出し、夜8時に蛍の光を流すなどの施策を行ったところ、逆に複数の税理士が一斉に退職してしまうという事態に直面しました。良かれと思って進めた方針でも、実際には人によって受け止め方が異なる。その経験から、今は一律の制度ではなく、柔軟で多様な働き方を尊重するスタイルに切り替えています。
AI活用に力を入れていると伺いました
今、私たちが最も力を入れているのが生成AIの活用です。目標は「日本で一番AIを活用する会計事務所」。単なるツールの導入にとどまらず、日々の業務にしっかり組み込んで使いこなすことを意識しています。
たとえば、申告書のチェック業務では、事前に作成したチェックリストをClaudeに覚えさせておき、法人税別表と損益計算書の数値に誤りがないかを確認させる使い方をしています。これによって、以前はベテラン職員でなければ気づきにくかったミスを、早い段階で確認できると期待しています。
また、会計ソフトから出力した元帳を読み込ませることで、税務調査で指摘されやすいポイントをClaudeが自動で拾い上げてくれる仕組みも導入しています。たとえば「修繕費の額が大きいため、資本的支出と区分すべきでは?」といったアラートが表示されるなど、判断の手がかりが得られます。また、消費税の課税・非課税・不課税の判定もClaudeで行えるようにしています。
こうした仕組みを整えることで、税理士の資格を持たないスタッフであっても、一定の精度で業務を進められるようになっています。もちろん最終的な判断は人が行いますが、チェックの効率が格段に上がり、職員全体の作業品質も高まりつつあります。
職員にも積極的に使ってもらえるように、社内での勉強会や情報共有も行っています。GASというプログラミングによる返信メール文案を利用したり、Gammaによりお客様へのプレゼン資料を作ったりと、それぞれが自分の業務に応じて活用しています。ChatGPTのDeep Researchにより、クライアントからの専門的な税務の解釈について調べたりする職員もいて、日常的に「AIを使って仕事をする」ことが当たり前になりつつあります。
こうしたAI関連のツール利用には毎月10万円以上のコストがかかっていますが、それ以上の成果が出ていると実感しています。
テレワークについては、コロナ禍の2020年4月から継続しています。現在は、神楽坂にある本社に常時出勤している職員はごく少数で、ほとんどが在宅勤務です。電話・FAXの確認からオンライン会議、ファイル共有まで、すべてクラウド上で対応しており、物理的なオフィスに縛られずに業務が行えるようになっています。
また、地方に住む事務スタッフとも業務委託で契約し、秘書業務や会計入力などをリモートでお願いしています。今では、郵便や電話の応対すらもクラウド上で完結する仕組みがあり、働き方を変えていきました。
これからの会計事務所の在り方とは?
これからの会計事務所は、「AIとどう付き合うか」で明暗が分かれていくと感じています。すでに税務や医療経営相談の大部分はAIに依拠しながら、最終確認だけを税理士などの担当スタッフが行なっています。記帳代行や申告書作成といった業務も、AIが搭載された会計ソフトに置き換わる部分が増えていくでしょう。そうなると、我々人間に残されるのは、「この人に相談したい」と思ってもらえるかどうかだと思います。
よくAIによって仕事が奪われると言われていますが、私はAIを使いこなすことでよりお客様の満足度を高められるのではないかと考えています。すでに、AI活用により質問回答のレスポンスが従来よりも格段に速くなっています。
もちろん、AIを使えばすべてがうまくいくわけではありません。過去と比べると減りましたが、AIは間違った回答をするリスクがあります。そのため、引用元をもとに正しいかどうか判断できる能力が人間には求められます。また、なぜAIの回答のうちそれを選んだのかをクライアントに説明し、納得してもらえるかどうかも必要とされるでしょう。
我々の事務所としては、AIが集められない一次情報の収集し、お客様に信頼される人間力の向上を目指して日々研鑽していきたいと思います。