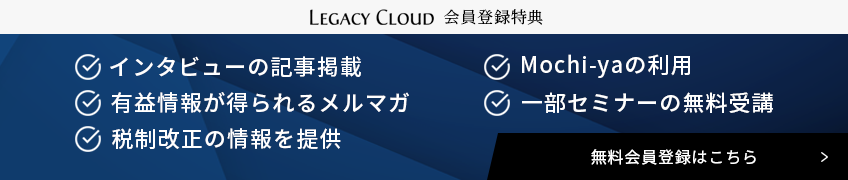外での修行を経て父の事務所へ――デジタル化と事業拡大で目指す次世代型税理士事務所

小池税理士事務所 税理士 小池康晴
大学卒業後、都内の会計事務所や税理士法人で幅広い業務に従事した後、父が代表を務める小池税理士事務所に入所。クラウド会計やAIツールの導入を通じた業務効率化、SNS等を活用した情報発信、事務所の拡大、相続分野への対応強化などを視野に、地域に根ざした発展的な組織づくりを目指している。
大手会計事務所での豊富な経験を経て、現在は父親の事務所で働きながら、次世代の事務所運営を模索する小池先生にお話を伺いました。
税理士を目指されたきっかけを教えてください
父が税理士でしたが、当初は全く税理士になるつもりはありませんでした。大学では経営学部に在籍していましたが、銀行など金融関係を志望していました。しかし、就職活動を進める中で「何か自分がやりたいこととは違うな」という違和感を覚えました。そこで「税理士ってどういう仕事なのか」と父に相談したことが、税理士という職業に関心を持つきっかけでした。
それまで父の仕事について詳しくは知らなかったのです。 お客さんがどんな方々なのか、何人従業員がいるのか、どんな業務をしているのか、全く把握していませんでした。父も自分から仕事の話をしてくることはほとんどなく、家庭と仕事は完全に分けている感じでした。忙しくしている父の姿は見ていましたが、具体的な業務内容までは理解していなかったというのが正直なところです。
ただ、元々数字に関わる仕事に興味があったことは確かです。そういう意味では、税理士という職業は自分の志向と合っていたのかもしれません。
今の事務所の前にいくつか別の事務所に勤めたと聞きました
卒業後はすぐに父の事務所に入るのではなく、まず他の会計事務所で経験を積むことにしました。なぜ他の事務所で経験を積もうと思ったかというと、いきなり父の事務所に入ってしまうと、そこでのやり方しか知らないまま成長してしまう危険性があると感じたからです。他の会計事務所の方々と話していても、それぞれ全く違うやり方をしていることが分かります。まずは外で様々な経験を積んで、幅広い視野を持ちたいと考えました。
勤務していた事務所は、かなり営業に特化した珍しいタイプの事務所でした。一般的な会計事務所では、上司がお客様との料金設定や契約内容を決めることが多いのですが、そこでは入社3ヶ月程度の新人でも、自分でお客様にプレゼンテーションを行い、サービス内容や顧問料を決める裁量権が与えられていました。
そして、営業成績が給料に直結する仕組みで、売上がないとほとんど給料がもらえないというフリーランスのような働き方でした。東京本社だけで80〜90人程度の規模でしたが、皆がまるで個人事業主のような感覚で働いていましたね。
ここでの経験は非常に貴重でした。他の会計事務所で働いていた方と話すと、お客様と直接話したことがない、ずっと入力作業などの裏方業務だけをやっている、という方も多かったです。中には5年、10年働いていても、いざお客様の前に出るとうまく話せないという方もいらっしゃいました。私の場合は、入社3ヶ月目からリスティング広告やホームページ経由で問い合わせをいただいたお客様との商談を任され、最終的には30社程度のお客様を担当し、打ち合わせから入力、申告まで全て一人で行っていました。
しかし、担当するお客様が増えるにつれて収入は増えましたが、その分プライベートの時間は削られていきました。 土日出勤は当たり前、夜10時、11時まで働くのも日常茶飯事でした。休日でも会社携帯が鳴り続け、プライベートと仕事の境界がなくなってしまったんです。最も辛かったのは、電話が鳴っていないのに鳴っているような幻聴が聞こえるようになったことです。これは相当参っているなと自分でも感じました。
そして、管理職になりかけていたタイミングで、税理士業界に踏み入れた時から描いていた『独立をする』という想いが強くなり、退職という決断をしました。
当時を振り返ると、忙しすぎて詳細を調べる時間がなく、税務的なリスクや会計処理において綱渡りのような状況になってしまっていたと思います。よくクレームがなかったなと思うほどです。現在では、もっとお客様とじっくり向き合い、リスクの少ない申告や将来を見据えた提案をしたいという思いが強くなりました。
父と働くことのよいところや難しいところを教えてください
2020年に税理士登録を済ませ、父からはいつでも入ってきていいと言われていましたが、前職でもう少し経験を積みたいと思い、結果的に35歳のときに父の事務所に入ることになりました。父と一緒に働くことの難しさは、やはり上司と部下の関係でありながら親子でもあるという複雑さです。
感情的になってしまうこともありますし、私が他の会計事務所での経験をもとに「こうした方が良いのではないか」と提案しても、父が長年築いてきたやり方に対する意見として受け入れられないこともあります。ただ、理解して取り入れてくれることもあるので、段々良くなってきていると思います。ちなみに、最初の相談事は、名字が同じ為、職場でのお互いの呼び方をどうするかでした。笑
現在、お客様の8割程度を私が担当しています。父が担当しているのは、代表者が高齢で後継者がいない会社が中心で、私は、社長がまだ若く、2代目、3代目への事業承継が予定されているようなお客様が多いです。父も70歳になり、事業承継について話し合うことが増えました。税理士には定年がないとは言え、いつまでも現役でいられるわけではありません。現在は、ゆっくりと引き継ぎを進めている状態です。お客様の情報はもちろん、重要書類の保管場所や事務所の運営方法など、様々なことを少しずつ教えてもらっています。
これから力を入れていきたいことを教えてください
まず営業面で力を入れたいと考えています。父の事務所はこれまでホームページはあるものの、積極的な営業活動はしておらず、基本的に受け身の姿勢でした。しかし、税理士事務所は数多く存在する中で、どのようなサービスを提供できるのかを積極的に発信していく必要があると感じています。 SNSなどを活用した積極的な情報発信にも取り組みたいと考えています。
技術面では、AIやクラウド会計の導入をさらに進めたいと思います。前職で少し経験していたfreeeやMONEYFORWARDなどのクラウド会計ソフトを、今の事務所でも導入を検討しています。これまで何時間もかかっていた作業が数分~数十分程度で完了するなど、劇的に効率が向上します。ただし、お客様にもネットバンキングを利用していただくなど、協力をお願いする必要があり、導入には時間がかかりますね。
また、事務所の規模拡大も視野に入れています。現在は私と父、そして職員2名の小規模な体制ですが、将来的には20〜30人規模の事務所にしたいと考えています。そのためには、他の会計事務所の承継なども検討する必要があるでしょう。税理士業界は高齢化が進んでおり、後継者のいない事務所も多いため、そうした事務所との連携や統合も重要な選択肢だと考えています。
さらに相続業務にも力を入れていきたいと思います。高齢化社会の進展や税制改正により、相続申告が必要な方は今後さらに増加すると予想されます。現在は年に2、3件程度ですが、病院や葬儀社などとの連携も視野に入れながら、相続業務を拡充していきたいと考えています。
最終的には、自分が現場からは少し離れ、優秀な職員に実務を任せながら、事務所全体のマネジメントに集中できるような体制を築くことが目標です。その実現のためには、人材の確保と育成が最も重要な鍵になると考えています。